【前回の記事を読む】凶作と飢饉で苦しむ仙台藩に黒船来航――軍制改革と財政政策はどう進められたのかこの政策は、洋式兵備の促進を望む藩主や一部の藩士に歓迎されたものの、財政の原則である「出を制し入りを計る」を無視するものであり、放漫経済に陥った。藩主慶邦は、芝多の軍備の促進に功労を賞し、「三十貫」を加増した。一方では、領民の生活難が激化した。しかし、芝多は、自宅に数寄をこらした茶室を新築する、或いは…
評論の記事一覧
タグ「評論」の中で、絞り込み検索が行なえます。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
-
評論『戊辰戦争』【第6回】吉野 敏

江戸時代に行われたインフレ政策…落ち込んでいる景気を刺激し好景気を図ったが、財政の原則を無視するもので…
-
評論『源氏物語探訪 ゲーテとともに』【第6回】田中 宗孝,田中 睦子

父は職を奪われ、権力者は弱者を嘲笑った――14歳の少女の怒りが1000年先まで残る物語に変わるまで……
-
小説『新事記』【第7回】吉開 輝隆

天上では、転生せず根源の国にとどまる神々と、転生のある伊弉諾の国に移る神々が選び分けられている
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【最終回】宮本 和俊

人生の中で同じ小中高を卒業し、大学の学部まで同じ、という人は何人くらいいるのでしょうか? 定年退職を目前に控えたある日…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第11回】宮本 和俊
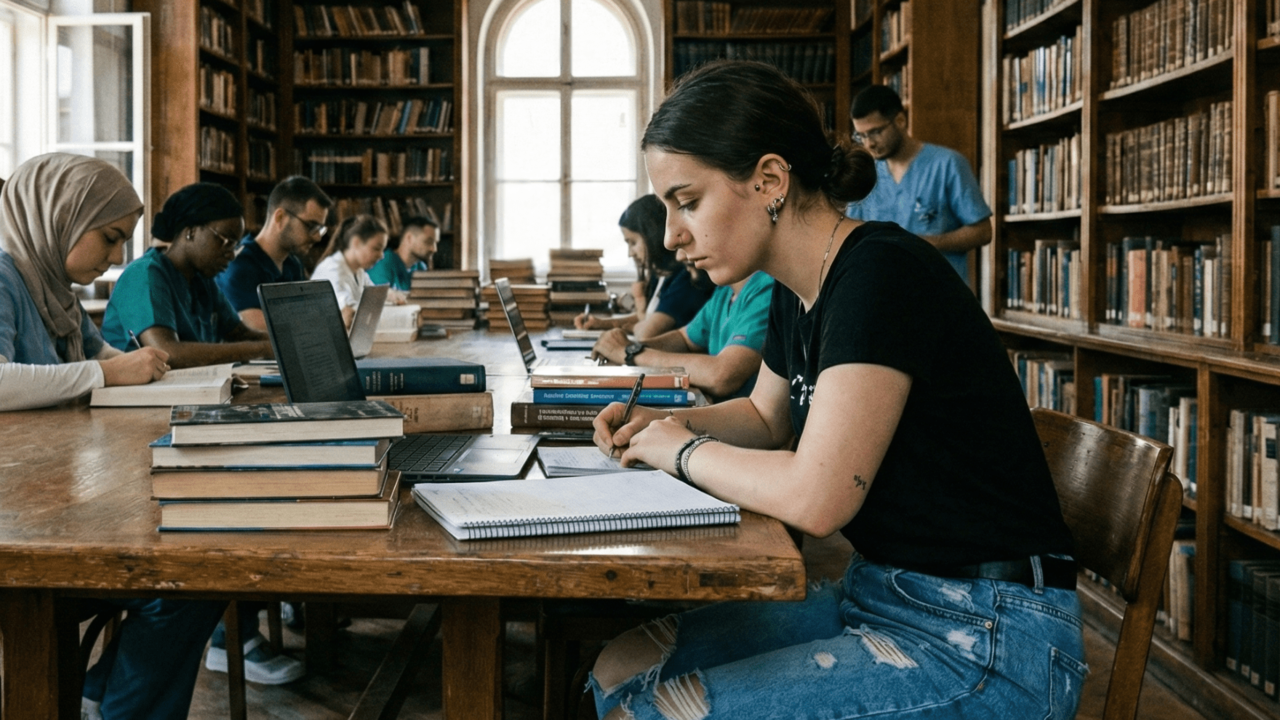
日本の教育はまだ「ゆとり」であることを痛感――ラミーヤの医学部での3年間は、1日15時間の勉強だった。それは学校の…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第10回】宮本 和俊

留学生・ラミーヤの歓迎会。「日本でオシムが有名なんだ!」と驚く一方で、過去のセルビアとの確執や辛い戦争体験に涙ぐむ
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第9回】宮本 和俊

パニックに陥る息子に「まったく根性のない子なんだから。押さえつけて…」と声かけするご両親。その目には涙があふれ…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第8回】宮本 和俊

オリーブオイルを数日かけて注入し浣腸をすると、肛門からてのひら山盛り2つ分ほどの〇〇が。彼の腸は緩くガバガバで…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第7回】宮本 和俊

「先生……ちょっとお話いいですか?」副院長が明かした衝撃の事実。思わず顔をまじまじと見てしまった。かつて彼は…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第6回】宮本 和俊

「わたし次の子必ずつくりたい……」部屋を去るとき、彼女にひたと見つめられた。えっ、何を……と思う間もなく彼女は泣きだした
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第5回】宮本 和俊

同僚の執刀医になった――手術当日、彼は鼻に太いイレウス管を入れられ、頬はげっそりとこけていて…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第4回】宮本 和俊

「人工肛門だね」術衣に着替えている際、学生のお腹の手術創に気がついた。なぜわかったのか?と不思議がる学生に…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第3回】宮本 和俊

「学校で友達に体の傷を見られるのがいやだった。だけど、今は…」コウスケ君とのやり取りが電話でよかった。なぜなら…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【第2回】宮本 和俊

「泣いてしまってごめんなさい、覚悟はしていたのに…」生後9か月で3度目の手術。腸が再び胸の中に脱出していることが発覚し…
-
健康・暮らし・子育て『たたかうきみのうたⅢ[注目連載ピックアップ]』【新連載】宮本 和俊

君が生まれて27年――人生の10分の1を病院で過ごし、毎日、点滴につながれてきた女性から「医師に届いた一通の手紙」
-
評論『“魔法の国”日本 ~駐日アメリカ大使夫人が見た明治・大正の日本~』【第5回】中村 信弘

壊れた帽子を被っていると罰を受ける!? 数世紀前の韓国は皇帝の命令で、男性は〇〇を被らなければならなかった
-
ビジネス『よみがえろう 日本のデジタル産業の未来へ』【第2回】河原 春郎

「日本企業はこれでは勝負にならない」…アメリカの東海岸の金融政策を見て、大きなショックを受けたワケとは…
-
評論『戊辰戦争』【第5回】吉野 敏

凶作と飢饉で苦しむ仙台藩に黒船来航――軍制改革と財政政策はどう進められたのか
-
評論『源氏物語探訪 ゲーテとともに』【第5回】田中 宗孝,田中 睦子

理想の男性・光源氏が“サイコパス”……? 75年苦しみ続けた“賢明な人”ゲーテの人生が突きつける源氏物語の闇
-
小説『新事記』【第6回】吉開 輝隆

「天上界の人間は、地上界の人間と同じようにみえたかもしれませんが、肉体のない、霊体だけの人間です。いや、神なのです。」







