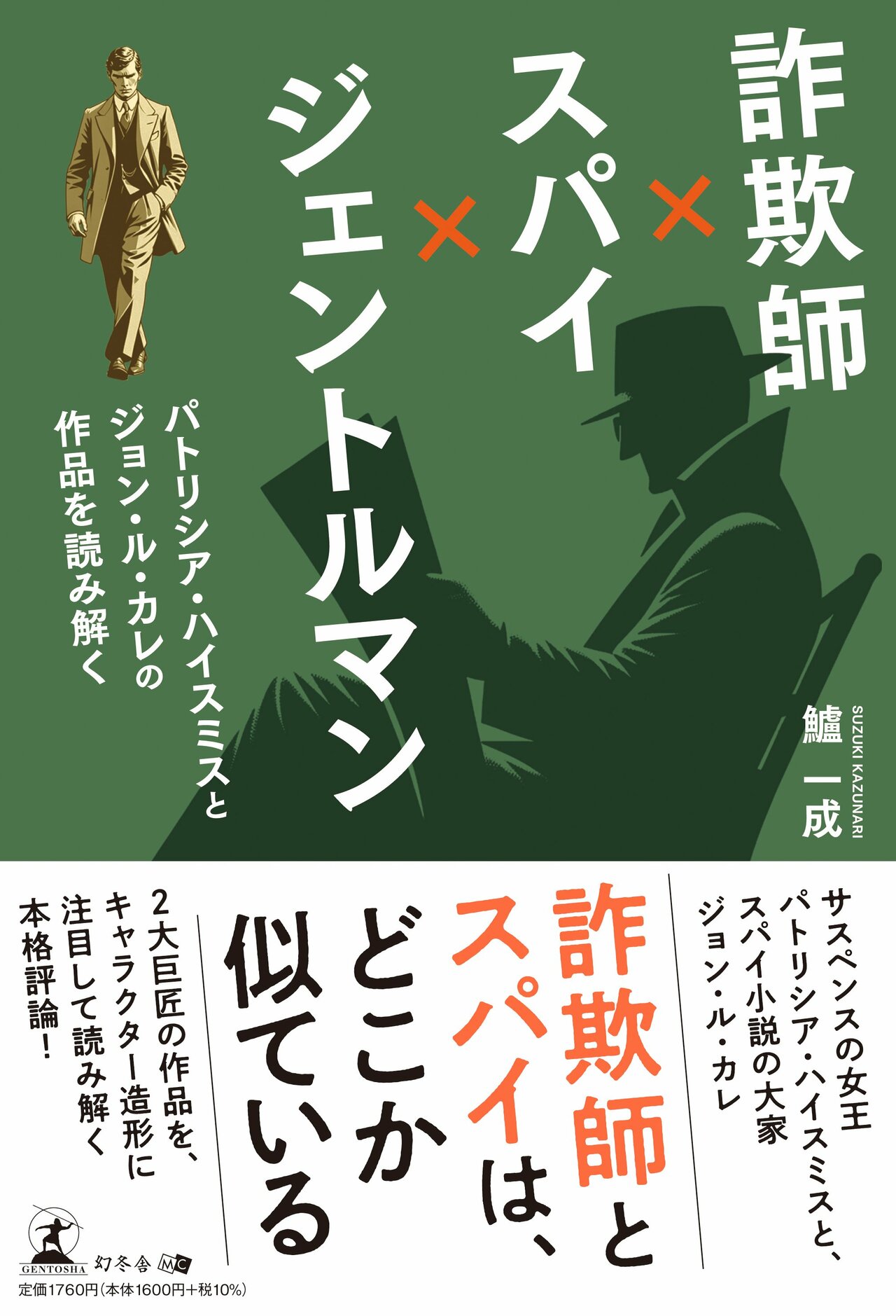【前回の記事を読む】紳士の仮面をかぶった詐欺師リプリーが立ち上げた危険な同盟関係。ある事件をきっかけに綻びが…【ハイスミス作品論】
第一部 トム・リプリー論
第1章 コンマン&ジェントルマン
―アメリカン・デモクラシーに背を向けた男トム・リプリー
2 『贋作』―紳士同盟のゆくえ
真贋Ⅱ
『贋作』は、絵画を題材にしながら、真贋をめぐる重要な問題について問いかけてくる。まず、「本物か偽物か」と問うことにどれほどの意味があるのか、という問題だ。
小林秀雄氏は、真贋をテーマにとても面白い文章を書いている。
『ニセ物は減らない。ホン物は減る一方だから、ニセ物は増える一方という勘定になる。需要供給の関係だから仕方がない。例えば雪舟(せっしゅう)のホン物は、専門家の説によれば十幾点しかないが、雪舟を掛けたい人が一万人ある以上、ニセ物の効用を認めなければ、書画骨董界は危殆(きたい)に瀕(ひん)する。商売人は、ニセ物という言葉を使いたがらない。ニセ物と言わないと気の済まぬのは素人(しろうと)で、私なんか、あんたみたいにニセ物ニセ物というたらどもならん、などとおこられる』(「真贋」。『モオツァルト・無常という事』所収。新潮文庫二二九頁)
詐欺師リプリーは、「ニセ物の効用」をむろん知っていた。ダーワット作品は商売になるとふんでいた。では、マーチソンには真贋を見抜く目があったのだろうか。これは怪しい。
なぜなら、彼が本物と確信していたダーワットの『オレンジ色の納屋』と『鳥の妖怪』は、バーナードの贋作だったのだから。彼は、これは偽物ではないか?などと疑わずに、ただ絵画を鑑賞し、ダーワットらしさを楽しんでいればよかったのかもしれない。
私見では、作者ハイスミスは『太陽がいっぱい』で、マルチタレントの輩出を予言していた。複製技術が蔓延する近現代では、偽造の技術も含め、才能の発揮の仕方には様々なかたちがあること、リプリーのようなマルチな才能をもった人々が成りあがって地位と名誉を手にする様を描いた。
本作では、『ニセ物と言わないと気の済まぬ』マーチソンを、プロとアマの境界線がくずれつつある複製技術時代の象徴的な人物―素人が専門家のように振る舞い、訳知り顔で何にでもコメントしたがる―として描いた、と筆者は読み解く。
真贋の問題はまた、自己のアイデンティティーを問うことにもつながってくる。リプリーは以下のように自問した。
『もし画家が自分自身の作品よりも贋作のほうを多く描いたとしたら、その画家にとっては贋作が自作よりもずっと自然な、ずっとリアルな、ずっとほんとうのものになるのではなかろうか? 贋作を描こうとする努力が最後には努力の域を脱し、その作品が第二の本性になるのではないだろうか?』(本書三三頁)