【前回の記事を読む】「またお会いする日を楽しみにしています。」と言っていたのに、“またお会いする日”はお葬式になってしまった。1985〜1990年頃、お笑いタレント全盛期で、笑いを取るための悪ふざけテレビ番組が、毎日のように垂れ流されていました。時を同じくして、学級崩壊やいじめ、不登校が都会の規模の大きな学校を中心に全国的に広がり、担任たちはもちろん、対象地域の学校も教育委員会も困り果てていたの…
評論
ジャンル「評論」の中で、絞り込み検索が行なえます。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
-
『「子どもの幸福のための教育」を求めて』【第6回】宮内 藤夫

80年代の小学生アンケートに驚愕!…「好きな遊び」第3位に入ったのは「弱いものいじめ」だった。
-
『百人一首を〈私〉が選んでみました』【第10回】多田 久也

深草少将と呼ばれ、小野小町とロマンスを楽しむほどハンサムだった遍昭――出家後も洒脱明朗で飄逸(ひょういつ)な歌を詠んだ
-
『宇宙の成り立ちへの試論』【第10回】手島 浩光

個人も社会も、制御不能な「濁流」の中にある。しかし地球は全てが奇跡であり、中でも人間はとりわけ貴重な存在であるのに。
-
『今のこのままの日本でいいのか』【第11回】一粒 野麦

文化祭で演奏することになった。「何弾くの?」「当ててみ?」ロックじゃないけどベースを入れた方が恰好つくからと言われ…
-
『外科医が歩いてきた道』【第8回】笠原 浩

手足の切断が最小で、絶対的な救命策だった戦時下の医療。腹や胸の深い創傷は手の施しようがなかった――
-
『いざという時の命の糧』【新連載】大谷 洋樹

雑穀が主食だった岩手県。「雑穀は貧しさの象徴で岩手の後進性を示すもの」と言うが、本当か?
-
『我が陣営にあるべし』【第8回】林口 宏

16歳で戦場に立ち、敵の首を取った少年武将——桶狭間の戦いに名を刻んだ水野太郎作清久と、丸根砦で散った片山勝高の真実
-
『紫式部日記を読む』【第8回】神明 敬子

【紫式部日記】書くことがなかった正月のはずが...寛弘六年・七年正月の日記は、後に加筆修正されている
-
『カイト地名と縄文遺跡 謎の関係』【第8回】井藤 一樹

突然「君の奥さんは霞のような人だね」と言われたが、意味がよくわからなかった…驚いて理由を聞くのを忘れてしまった
-
『Allez, Japon! 日本フェンシングチーム躍進!陰の立役者たち』【第18回】公益社団法人 日本フェンシング協会

金メダルを手にした瞬間、思わずこぼれた『ああ、よかった』——舞台裏で支え続けた者の想いと、諦めなかった者だけが見た景色
-
『菟狭津彦が見た倭国の歴史』【第4回】宇佐津彦 清智

日本書紀と三国史記の記述差から読み解く、継体天皇暗殺説と倭国・伽耶・新羅をめぐる6世紀東アジア政変の真相とは
-
『ラスコーリニコフ 苦悩の正体』【第4回】岩澤 聡史

殺人犯を襲った“孤独”と“疎外感”。この感情はいったいどこから——ドストエフスキーが読者に求めた「共感」とは
-
『“魔法の国”日本 ~駐日アメリカ大使夫人が見た明治・大正の日本~』【第5回】中村 信弘

壊れた帽子を被っていると罰を受ける!? 数世紀前の韓国は皇帝の命令で、男性は〇〇を被らなければならなかった
-
『300年先まで残る国であるために』【第5回】堀 源太郎

日本は江戸時代以来、「民を富ませる」意識に欠けていた。日本人が高度成長を経験しながらも、真の豊かさを実感できない理由とは
-
『理科的文科人のすすめ』【第5回】影山 光太郎

社会主義の失敗…旧ソビエト連邦等で発展した「公平」を目指す“システム”には欠陥があった。それは、上に立つ者の権力が——
-
『ICFと日本の健康福祉』【第5回】丹羽 國子

「産んで人生を狂わされた」と言う母は、「3回するまでは大丈夫」と赤ちゃんのオムツ交換を省略するようになり…
-
『プレストレストコンクリートと都市トンネル工法』【第5回】西川 和良

PC構造物に用いられるPC鋼材・シース・定着具の防食性能と耐久性
-
『パーキンソン病の真実』【第5回】北田 徹
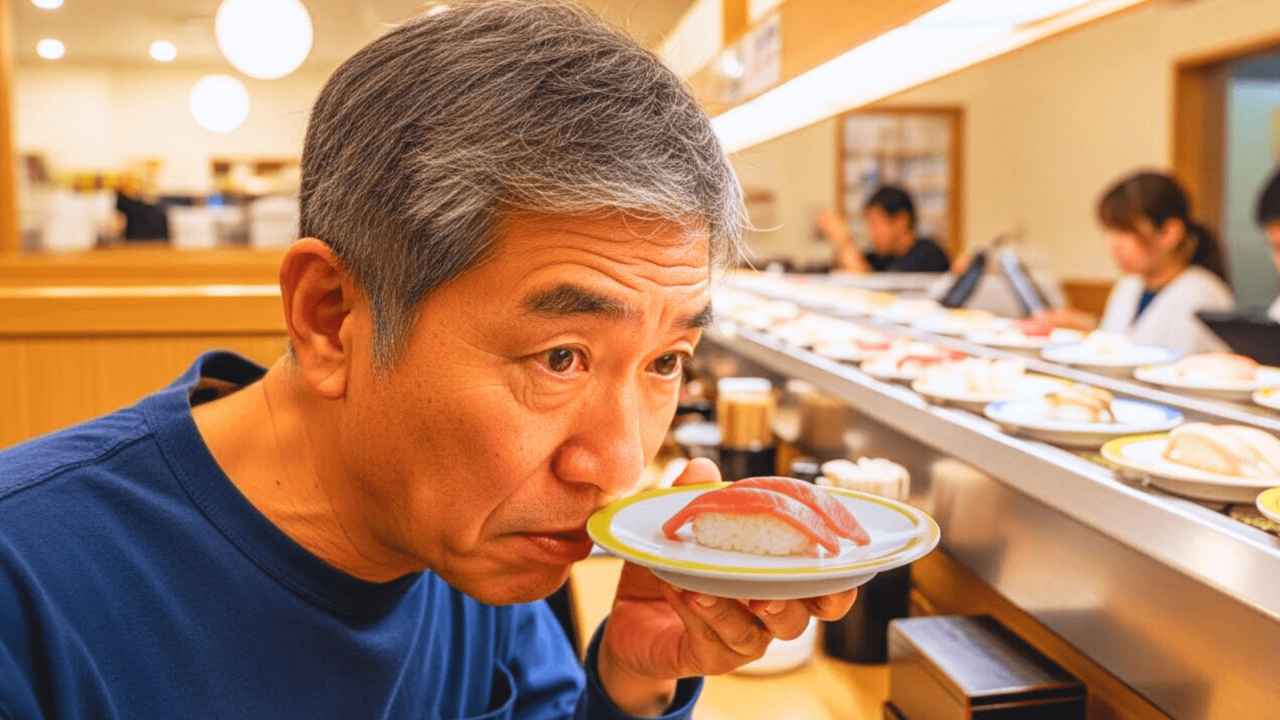
“時間差”で訪れる病気。「パーキンソン病」の原因は、発症の数十年前から体内に蓄積されていき…
-
『桶狭間の戦いは迂回奇襲説、長篠の戦いは鉄炮三段撃』【第5回】坂田 尚哉

今川本軍の進軍経路は「織田方」に遺された史料で判断できるのか。鳴海方面説に残る論拠の欠如
-
『ながれ星 冬星』【第7回】石田 義一郎

「先月も額を割られた不審な仏が2人も出た。」…誰がやったかわからない、不審な変死体が発見され…






