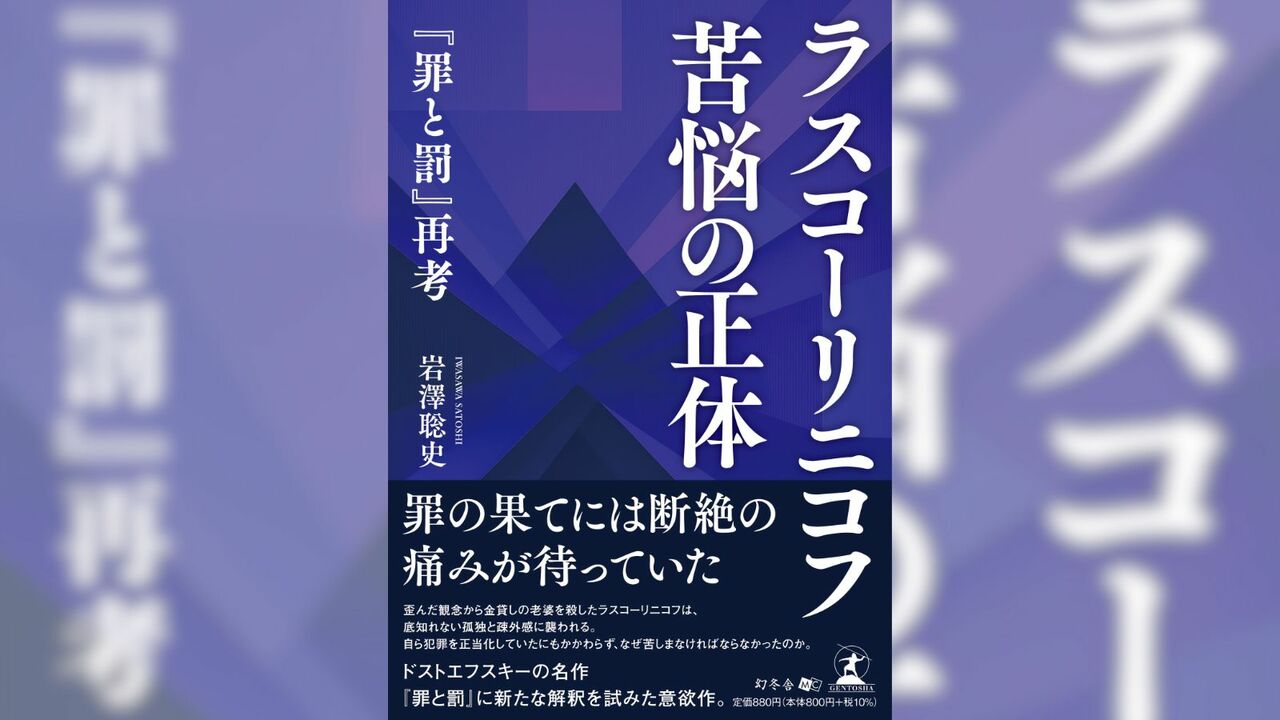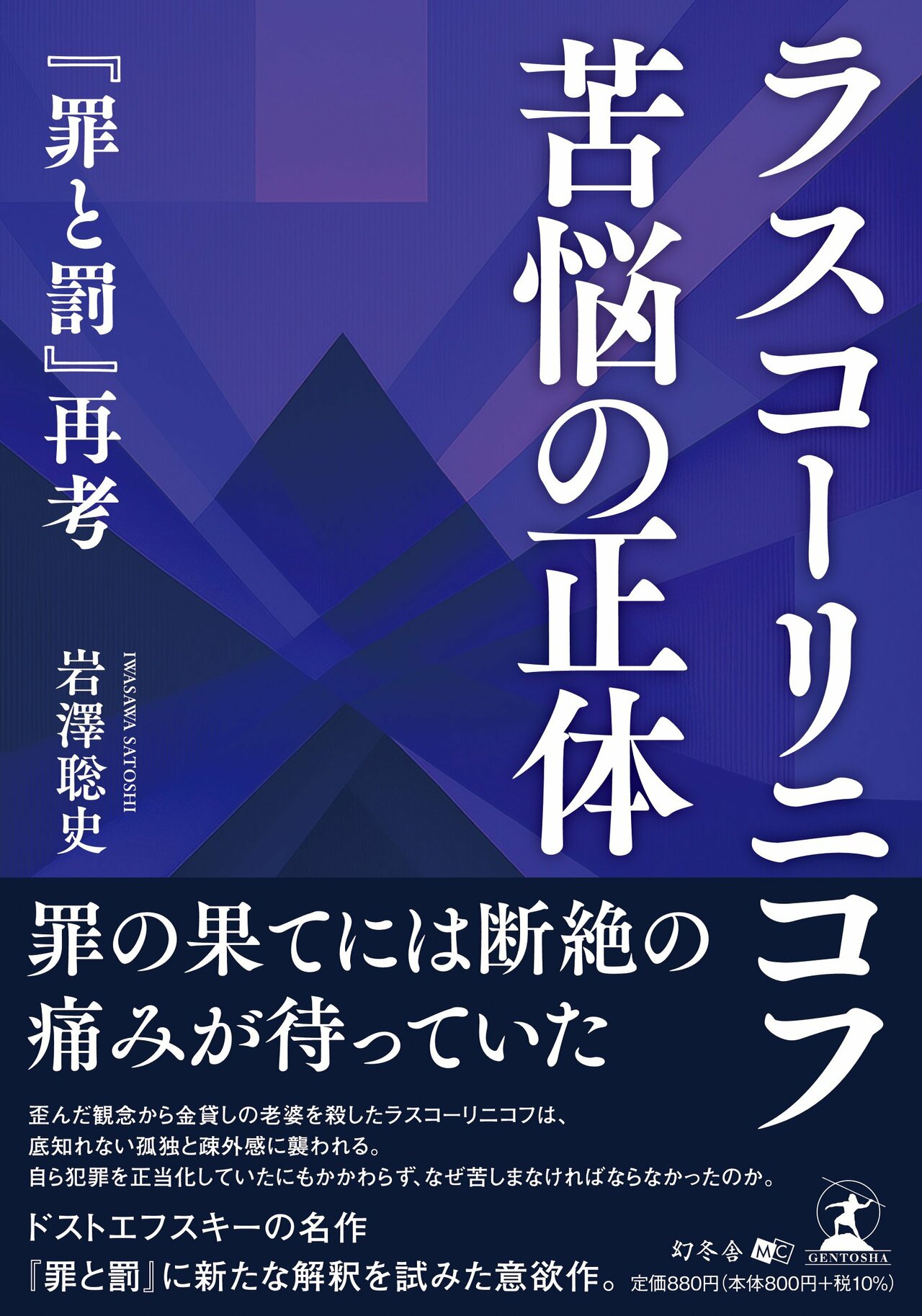序
『罪と罰』再考、と副題に示したとおり、本書は『罪と罰』という小説についての独自の解釈を提出しようとするものだ。
なぜ、いまさら『罪と罰』なのか。
それは私のささやかな人生を通じて、もう何十年にもわたって、この作品のことを考え続けてきたからだ。
この作品を初めて読んだのは、大学に入った直後、おそらく十九歳であったと思う。
当時の私は典型的な五月病であった。もともとネクラで人づきあいが苦手、これといって熱中できる趣味もなかったので、受験勉強から解放されたとたんあり余る時間をもてあますようになった。大学のクラスメートたちはよい友人であったが、私自身の消極的な性格が災いしてか、つきあいを深めることができなかった。暇つぶしに英会話のサークルに入ってみたが、楽しいと思えず長続きしなかった。
あるとき、学内で活動する小さな演劇集団に熱心に勧誘され、芝居の公演を観に行った。わけの分からない不思議な芝居だった。終演後のオリエンテーションに参加し、劇団のリーダーである演出家の学生に「今日の芝居にどんな意味があったのか」と思いきって聞いてみた。
その先輩学生は「あの劇の脈絡は完全に破壊されたものであるが、その破壊された脈絡をいかに観客に信じさせるか、つまり破壊されていないもののように思わせ観客を感動させるか、それが劇の重要なテーマであったのだ」と語った。これはついて行けないと思い、一気に興味を失った。万事がそんな調子だった。自分がやるべきことが分からず、生きることになんの意味も見いだせなかった。
空白の時間を、私は本を読むことで埋めていった。とりわけ海外の古典的な名作とされる小説を好んで読んだ。キャンパスの近くの繁華街に居心地のよい行きつけの喫茶店を見つけ、薄暗い店内の片隅の席を選んで、一時間でも二時間でも読書に没頭した。そうやってなじみ深い孤独にこもり、現実から切り離された安全地帯で、未熟な悩みを抱えながら、自分が生きることの意味を探っていた。
そうした日々に、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフといったロシアの作家たちと出会ったことは必然であったろう。大学の第二外国語としてロシア語を選択したのはたまたまだったが、そんな偶然もロシア文学への愛着に拍車をかけた。