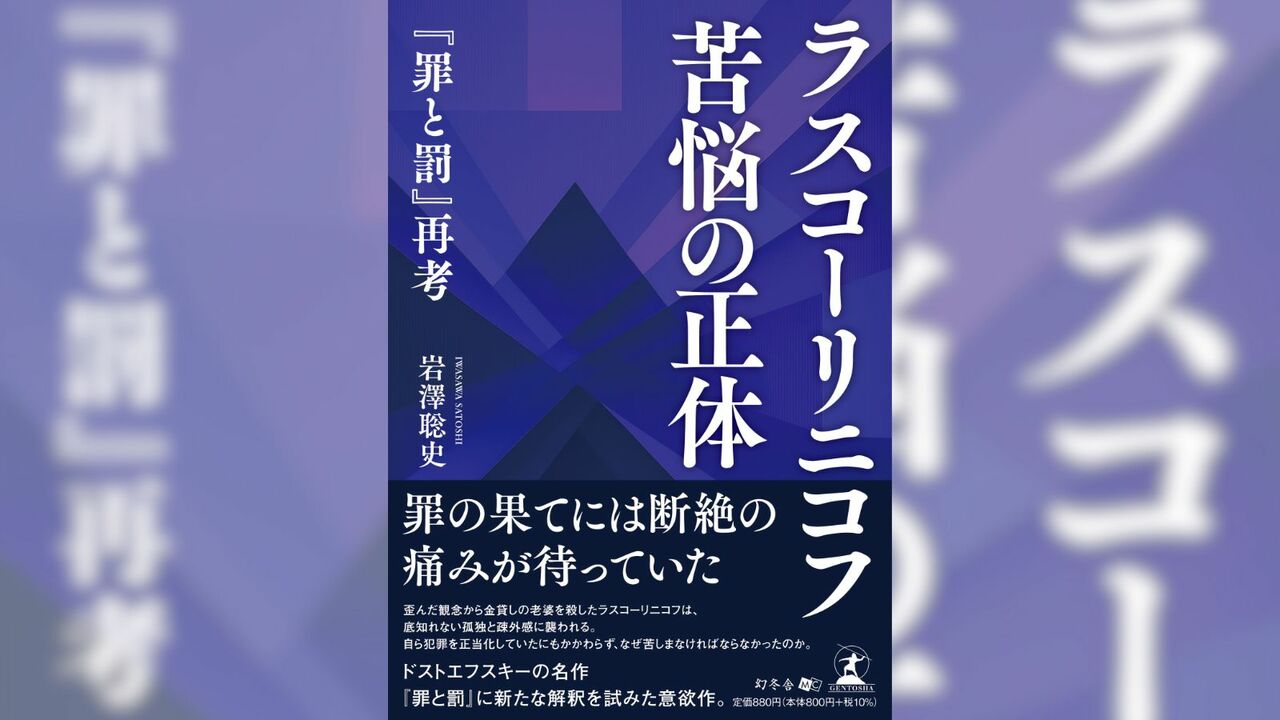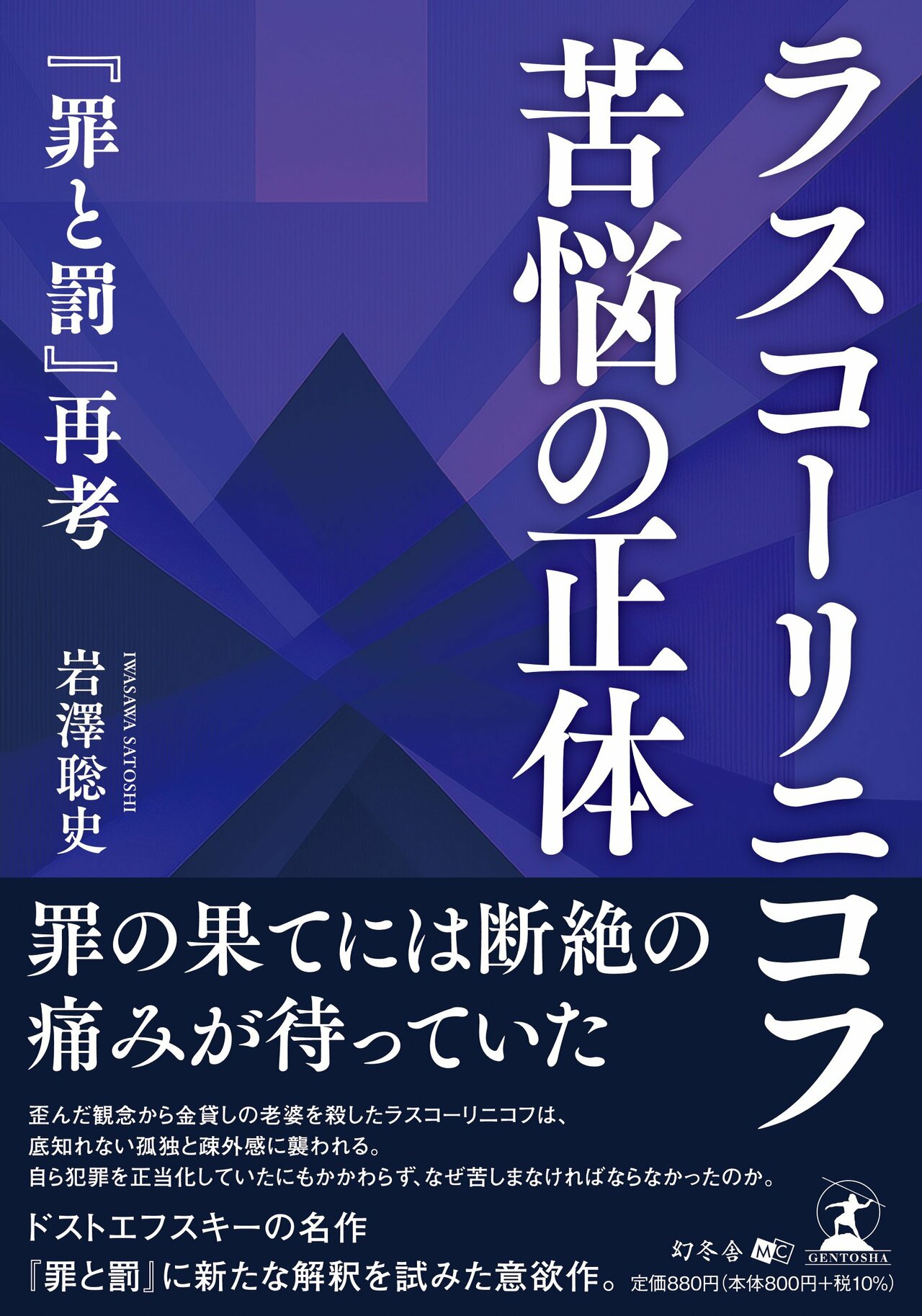【前回の記事を読む】新解釈『罪と罰』:ラスコーリニコフの苦悩の正体――犯罪を正当化していたにもかかわらず、なぜ苦しまなければならなかったのか
第一章 問題の所在
十九世紀ロシアを代表する作家F・M・ドストエフスキー(一八二一︲一八八一)の『罪と罰』(一八六六)は、世界文学史上あまりにも有名な作品である。
舞台は、当時の帝政ロシアの首都ペテルブルグ、主人公は、貧乏な元大学生のラスコーリニコフだ。ラスコーリニコフは、強盗殺人の罪を犯す。意地が悪く、強欲で、他人の生き血を吸うような金貸しの老婆を殺害し、金品を強奪するのだ。
それは衝動的な犯行ではなく、彼が考えに考え抜いた末の計画的な殺人だった。
私が理解できなかったのは、犯行後のラスコーリニコフに生じた突然の精神的な変化である。
ラスコーリニコフの犯行の主たる動機は(少なくともその一部は)、彼の極度の貧乏にあった。彼が有為の人材として世に出ていくために、いや、それ以前に、日々の暮らしにも事欠くような赤貧から脱け出すためには、金が必要だった。
ましてや、故郷で母と暮らす最愛の妹ドゥーニャが、好きでもない男の求婚を受け入れたことを母の手紙で知り、どうやらその理由が、将来の夫からの兄に対する援助を当てにしたものであることを悟ってしまったラスコーリニコフは、なんとしてでもその結婚を阻止せねばならなかった。
母や妹を安心させ、無謀な結婚を止めるためにも金銭問題を解決することが急務である。そのためには行動を起こさなければならない。
作者は、ラスコーリニコフの切羽詰まった心理状態を次のように描いている。
明らかにいまは、問題解決の困難さばかりあげつらい、受け身にまわって悩んだり、煩悶(はんもん)したりしているときではなく、是が非でも何かをしなければならないときだった。
それも、いまただちに、一刻も早く。どうあっても何かを決行しなければならない、せめて何かを、でなければ……。(第一部四)(1)
その「何か」が「強盗殺人」であるというのはあまりにも突飛な飛躍であるが、その老婆殺しの「計画」はすでに久しくラスコーリニコフにとりつき、もはや肥大化した強迫観念となっていた。
しかし、なんといっても殺人は「悪」だ。倫理的にも、もちろん法律上も「悪」である行為が、果たしてどのように正当化され得るだろうか。