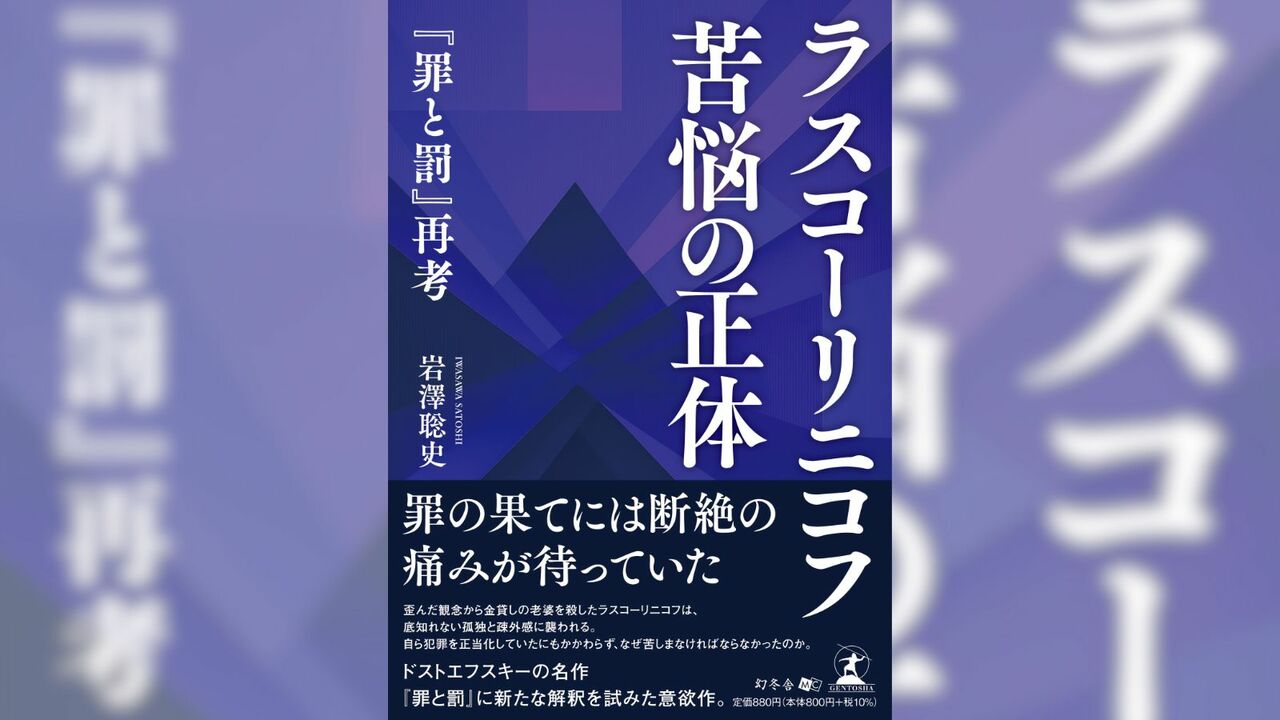【前回の記事を読む】計画的な殺人を犯したラスコーリニコフ。その正当性は自身の中で事前に決着済みのはずだったが、さて実行してみると…
第一章 問題の所在
ラスコーリニコフの心の中に生じた変化について、少し長くなるが、作品から引用する。
いま彼の身に起こりつつあったのは、彼にとってまったく未知の、新しい、思いがけぬ、ついぞこれまでに例のないことであった。頭で理解したというのではなかったが、彼は明確に、全感覚をつらぬくほどの力で感じとったのだった――。
ほかでもない、彼はもう二度と、さっきのような感傷的な打明け話はもちろんのこと、たとえどんな種類の話であっても、警察署のこういう人間どもを相手に話しかけることはできない、
いや、たとえ相手が警察署の警部ふぜいではなく、彼と血を分けあった兄弟姉妹であっても、今後、生涯のいかなるときにも、彼らに話しかける理由はまったく失われてしまった、ということをである。
いま、この瞬間まで、彼は一度としてこんな奇怪な、恐ろしい感覚を経験したことはなかった。
そして、何よりもやりきれなかったのは、意識とか、観念とかいうよりも、むしろ感覚であったこと、直接的な感覚、これまでの生涯で彼が体験した感覚のうちでも、もっとも苦しい感覚であったことである。(第二部一。太字の強調は引用者による。以下同じ)
これに続く場面では、ラスコーリニコフは、放心状態でペテルブルグの街なかを彷徨し、ふと立ち止まったネワ川に架かる橋の上で、「いっさいの人間といっさいのものから、自分の存在を鋏で切り離しでもしたように」感じる。
これは、どういうことなのだろう?
ラスコーリニコフは、殺人という行為の後に、誰であれ他の人間と正常な人間的な関係を結ぶ能力を失ったかのようだ。彼は、なぜそのような不能に陥ってしまったのか。
「良心の呵責」に耐えられなくなったのだ、と考えることはもちろん容易である。しかし、犯行後のラスコーリニコフになんら悔恨の情が生じなかったことは、作者が明確に繰り返し述べている。