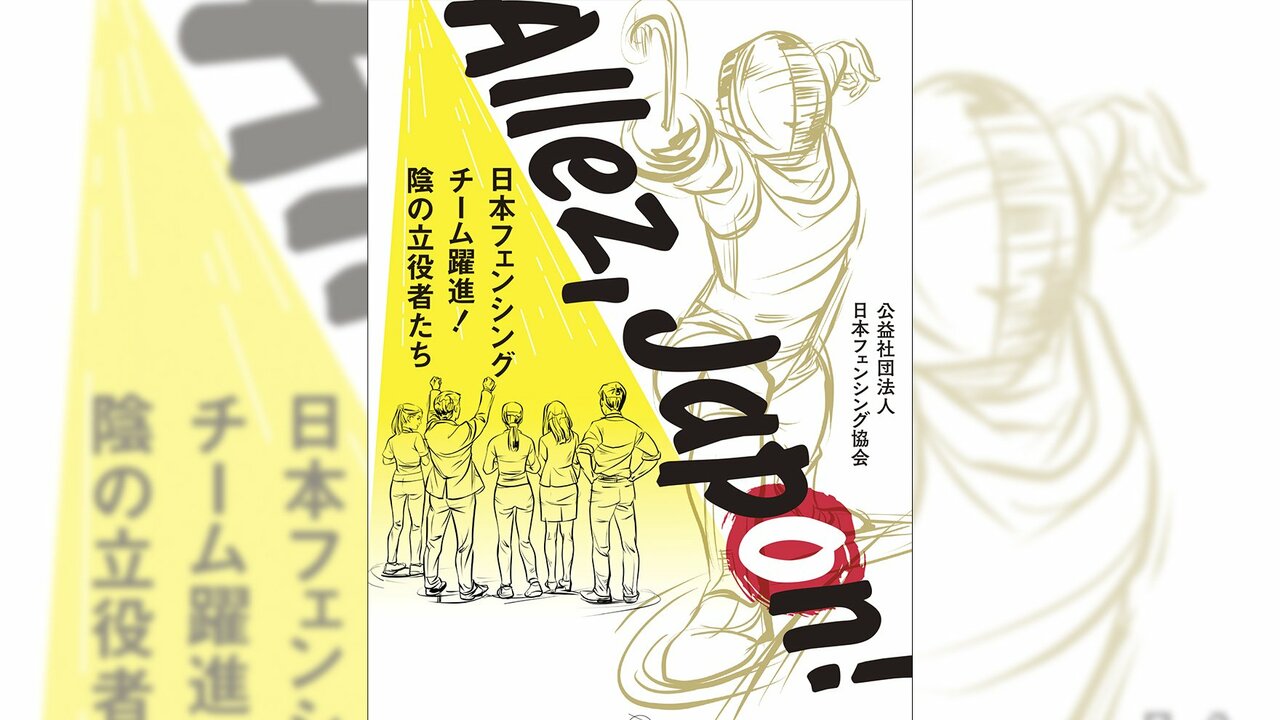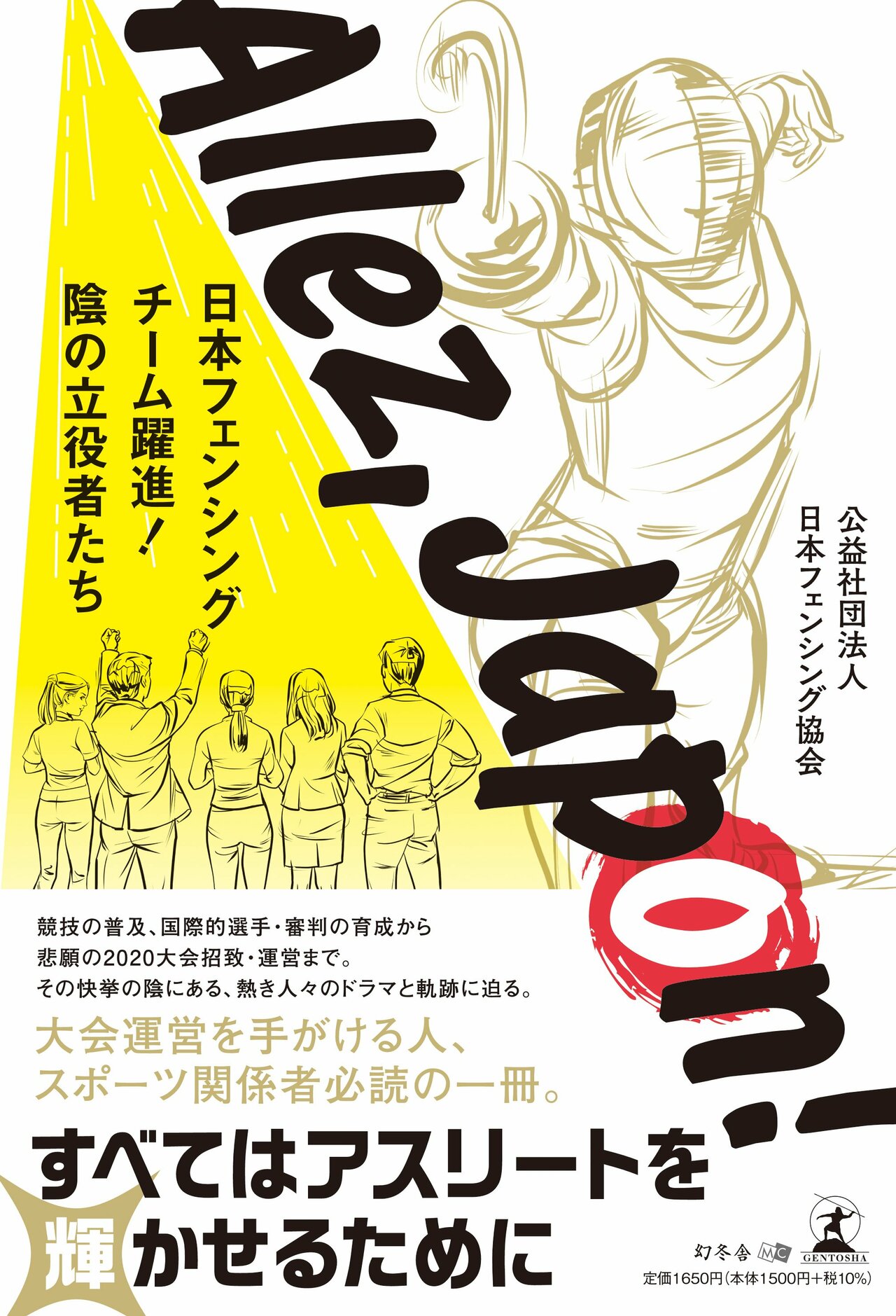【前回の記事を読む】「このままじゃ世界で勝てない!」敗北の世界選手権から始まった日本フェンシング改革──若きコーチの覚悟と、本気の挑戦とは?
兄貴としての役割 齊田 守
「オレグ、俺たちはどうすればいいかな? どうすれば日本が勝てる?」
問うたび、オレグはこう答えた。
「齊田さん、フェンシングの“世界”を見て下さい。日本人はどれだけいますか? 審判コミッションにもいない。ルールを決めるセクションにもいない。どこを見ても日本人はいない。こんな状況で勝つこと自体が難しいですよ」
選手の競技力を高めることはもちろんだが、それだけでは勝てない。微妙な判定になっても欧州諸国と比べ強弱をつけられないよう、世界の舞台に立つ審判が必要だ。
何よりFIEに日本人の理事を入れなければならないし、国際大会を日本へ招致するためには会場運営のトップであるDT(フランス語“Directoire Technique” の略)も日本人でなければならない。
「雄貴はどんどん世界で勝って行く。でもそのたび、絶対に理不尽な悔しさも味わうんです。あの1本は、絶対に俺だったのに、と思うこともたくさんあったはずです。
世界の舞台で戦え、と言った選手が本当に世界で戦う選手になり、五輪のメダルだって十分狙える位置へ行き、北京では本当に銀メダルを獲ってきた。ここからは組織として強くならないとダメだろう、と心の底から思いましたね」
国際フェンシング協会の理事になるには、まずアジアで理事に選ばれる事も重要で、そのための選挙がある。北京五輪で太田が個人の銀メダル、さらに4年後のロンドン五輪では男子団体フルーレで銀メダルを獲得し、国内外でフェンシングの知名度も上がったからこそ、一段階先へ進む。
東京五輪招致へ向け気運も高まる中、相次いでアジアで理事を当選させた。北京五輪までは男女フルーレを統括するオレグだけだった外国人指導者も、女子フルーレや男女エペ、サーブルとそれぞれに専門のコーチを招聘。その交渉役を買って出たのも齊田だった。