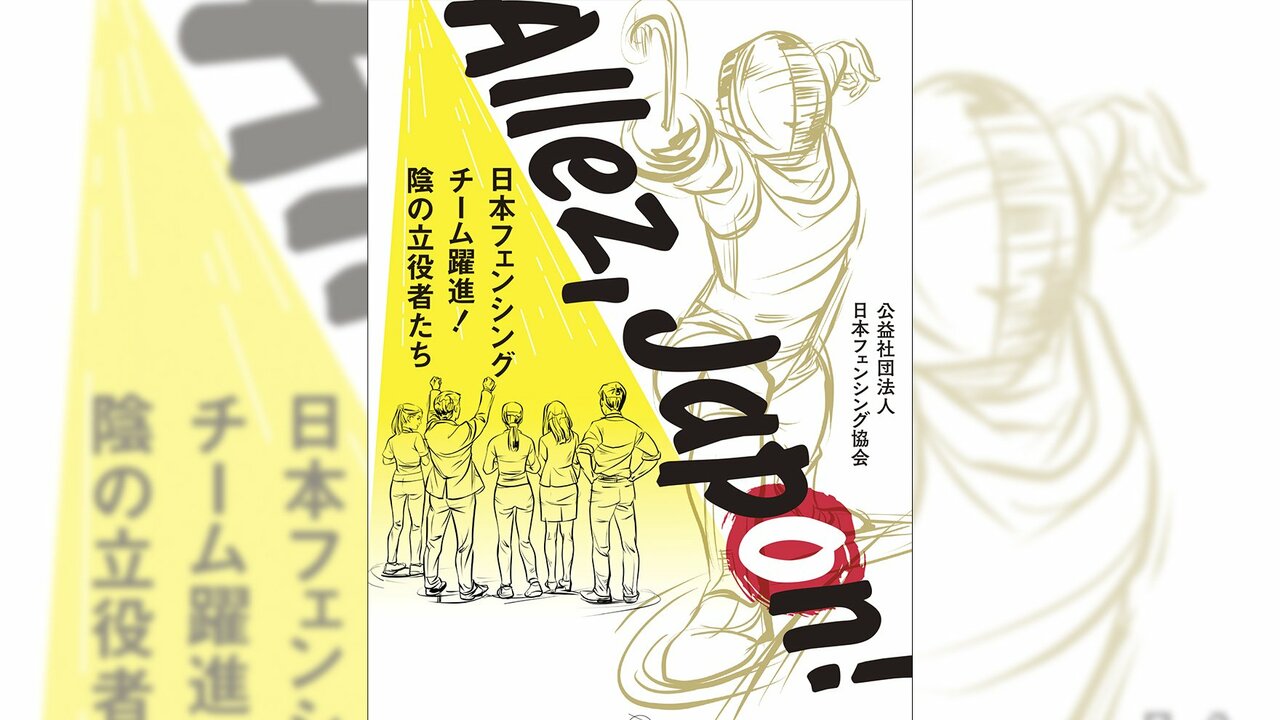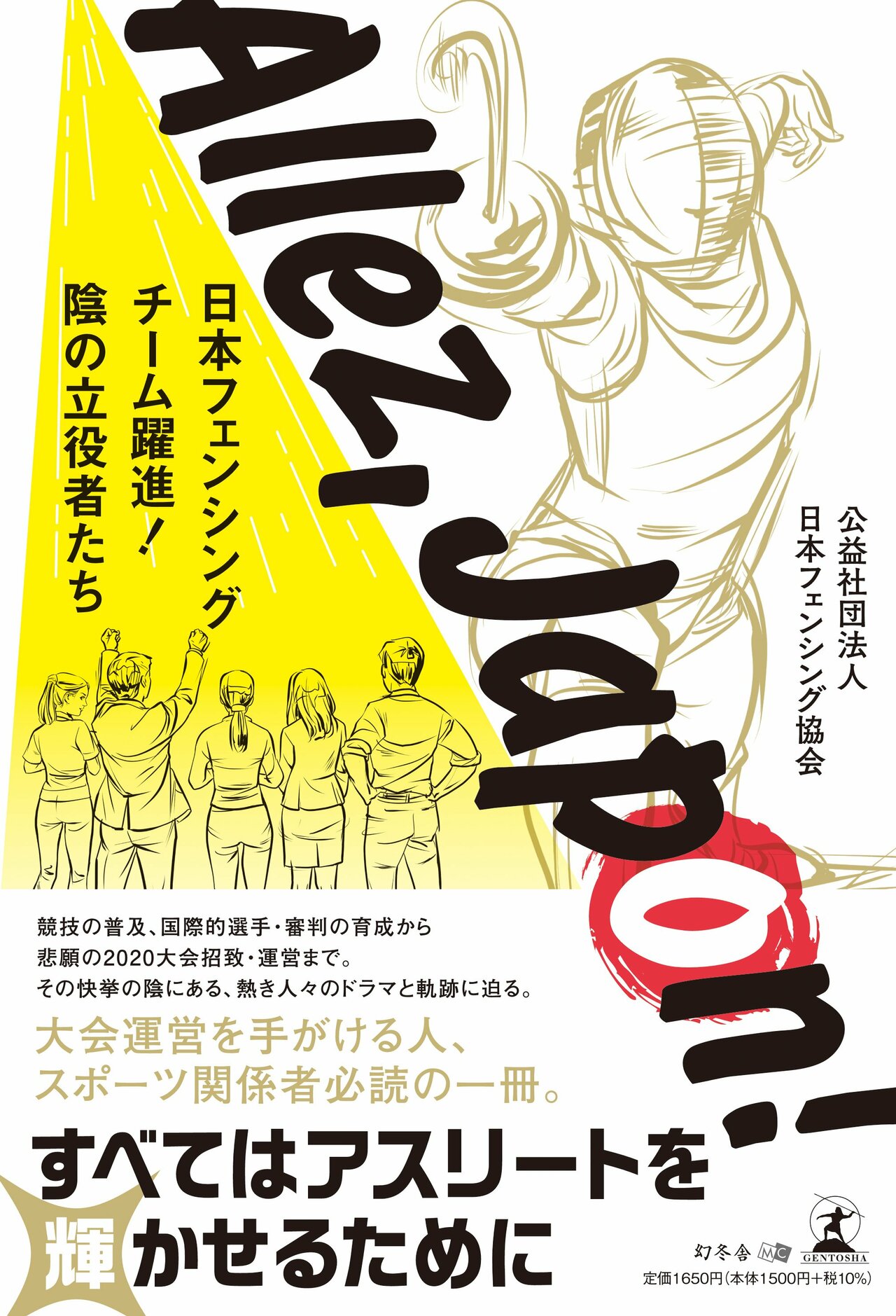【前回の記事を読む】フェンシング日本代表が強くなった本当の理由――選手よりも先に動いたある男の決断
兄貴としての役割 齊田 守
自国開催の五輪。どれだけ盛り上がるのか、とお祭り気分で胸躍らせる人たちが少なくない中で、齊田が抱いたのは危機感だった。
「ここでメダルが獲れなかったら、もう日本のフェンシングは終わる、と思っていました。今まで支えて下さったたくさんの方々のおかげでここまで頑張ってこられたこともすべてなくなって、もう1回初めから、それこそ50年前までさかのぼらないといけない。
東京五輪でメダルが獲れないということはそういうことだと思っていました」
北京で太田が初めて銀メダルを獲得した際、メディアやさまざまなイベントで引っ張りだこになる中、マネジメント事務所に所属するまでの間、太田のアテンド役として齊田は共に全国を回った。
帰国当初こそ、目まぐるしく変わる世界を楽しみながら、フェンシングを広めるチャンスと目を輝かせていた太田も、連日連夜、あちらこちらを飛び回り取材では繰り返し何度も同じことを聞かれる。
日に日に疲弊する姿を見かね、「これ以上は無理」と日本フェンシング協会との調整をしながら、太田には「何とか頑張ってほしい」と労った。
「ようやくこの時が訪れたわけですから。苦しいし、大変なのはわかるけれど、でも何とか頑張ってくれ、踏ん張ってくれ、と。ここで一気に人生が変わるし、フェンシング界が変わるから、と僕も雄貴に託しましたよね。でも現実はというと、そんなに簡単でも甘くもない。
念願だったメダルを獲った。僕たちはメダルを獲った"から"に続いて行くと思っていたけれど、実際はメダルを獲った"けど"だった。あんな思いをさせちゃいけない。ここから前に進むために、何としても銀から金へ、壁を越えなければならない。それだけでした」
北京五輪の後やロンドン五輪の後、メダルを獲った後は一時的に露出も増える。選手たちもこの機を逃さぬように、と懸命に駆け回り、それぞれが「フェンシング」をアピールする。
だが日本で開催される大会は年に1~2度、五輪出場に向けた世界各国でのグランプリやワールドカップに出場しなければならないため、海外での試合がメインになる。
国内で定期的にリーグ戦が行われる他競技と比べれば露出の頻度は限定的で、実際に2013年の日本選手権は千田健太と三宅諒、銀メダルを獲得した選手同士の決勝戦であったにもかかわらず、スタンドはガラガラ。
同じメダリストであっても、園遊会や紫綬褒章を受章するのは金メダリストだけ。
悲願を叶えてもなお、頂点に届かないからこそ味わう現実を、齊田は忸怩たる思いで見つめ、打破するためのいわば最後のチャンスが東京五輪だと思っていた。
選手の練習場所がない。指導者がいない。そんな苦難の時代は北京を機に少しずつ変化を遂げ、ロンドン、リオデジャネイロと五輪のたびにJOCからの支援は増え、補助金も増えた。
かつては「団体戦は3名プラス1名、計4名がメンバーだから」と伝えても、1名は補欠なので自己負担。二度の五輪やアジア大会で男子フルーレだけでなく、女子フルーレや男子エペ、女子サーブルも結果を残し、日本のフェンシング全体がレベルアップしていると強く印象付けた。