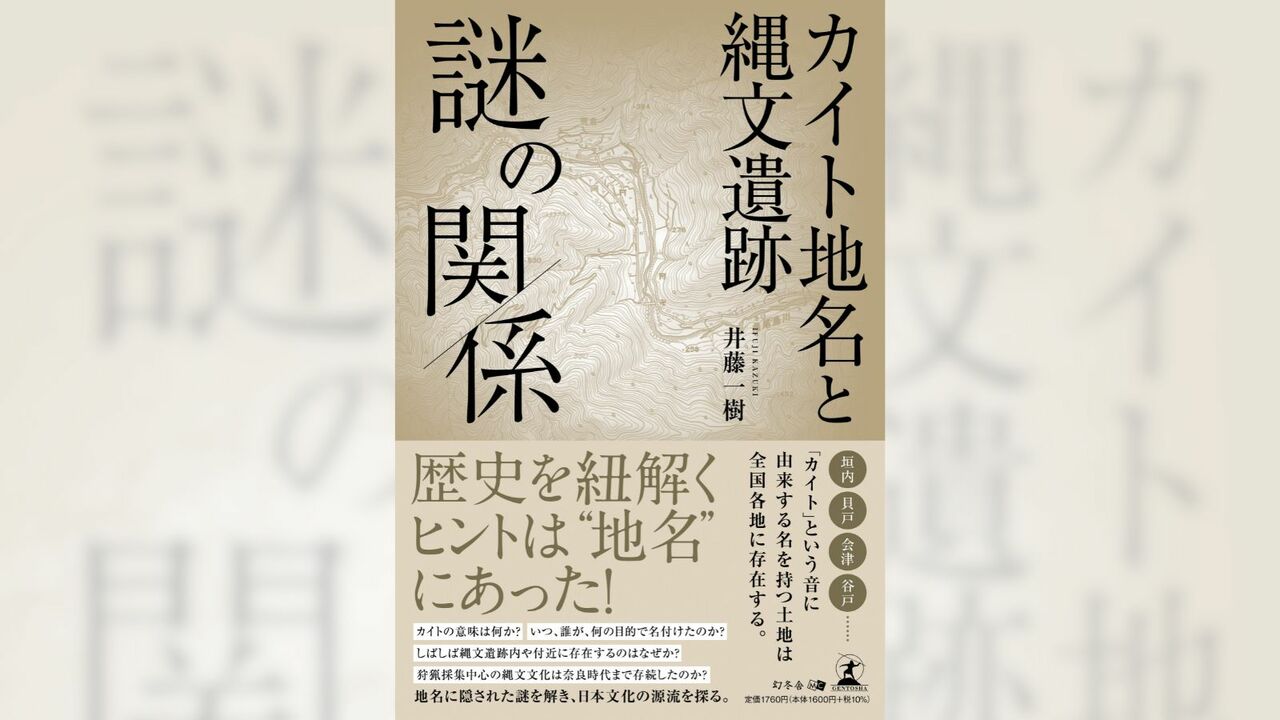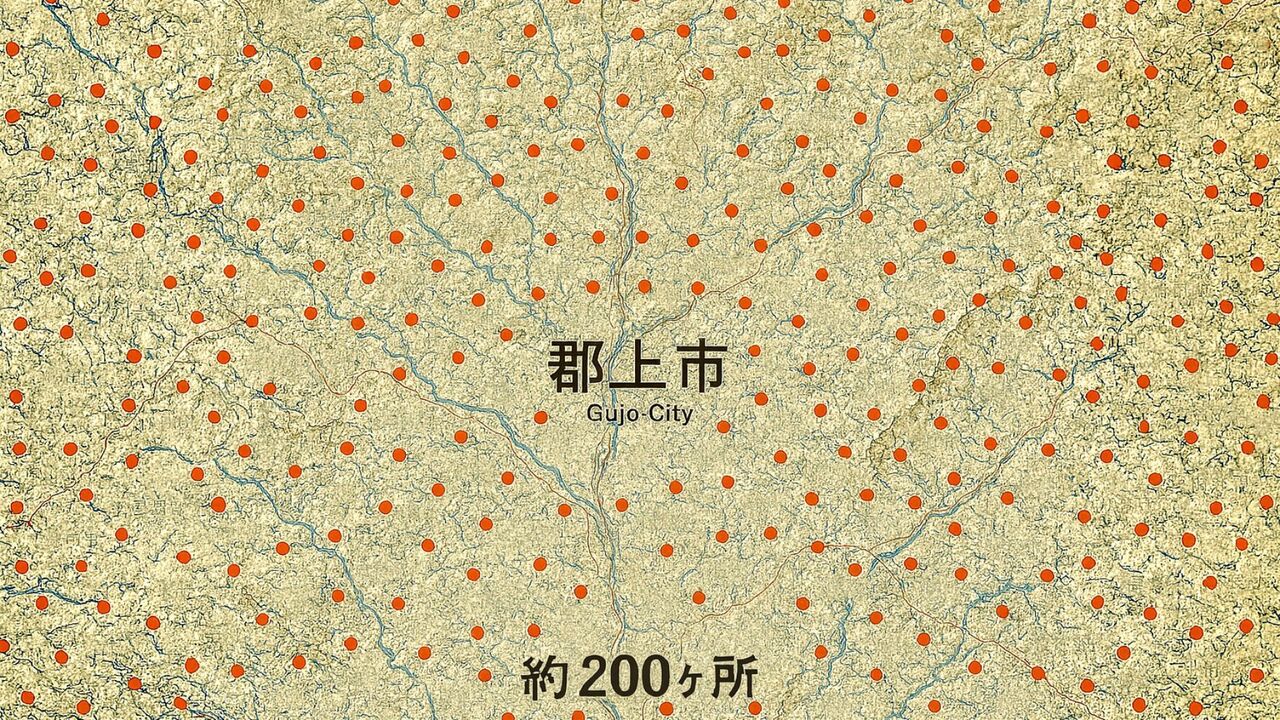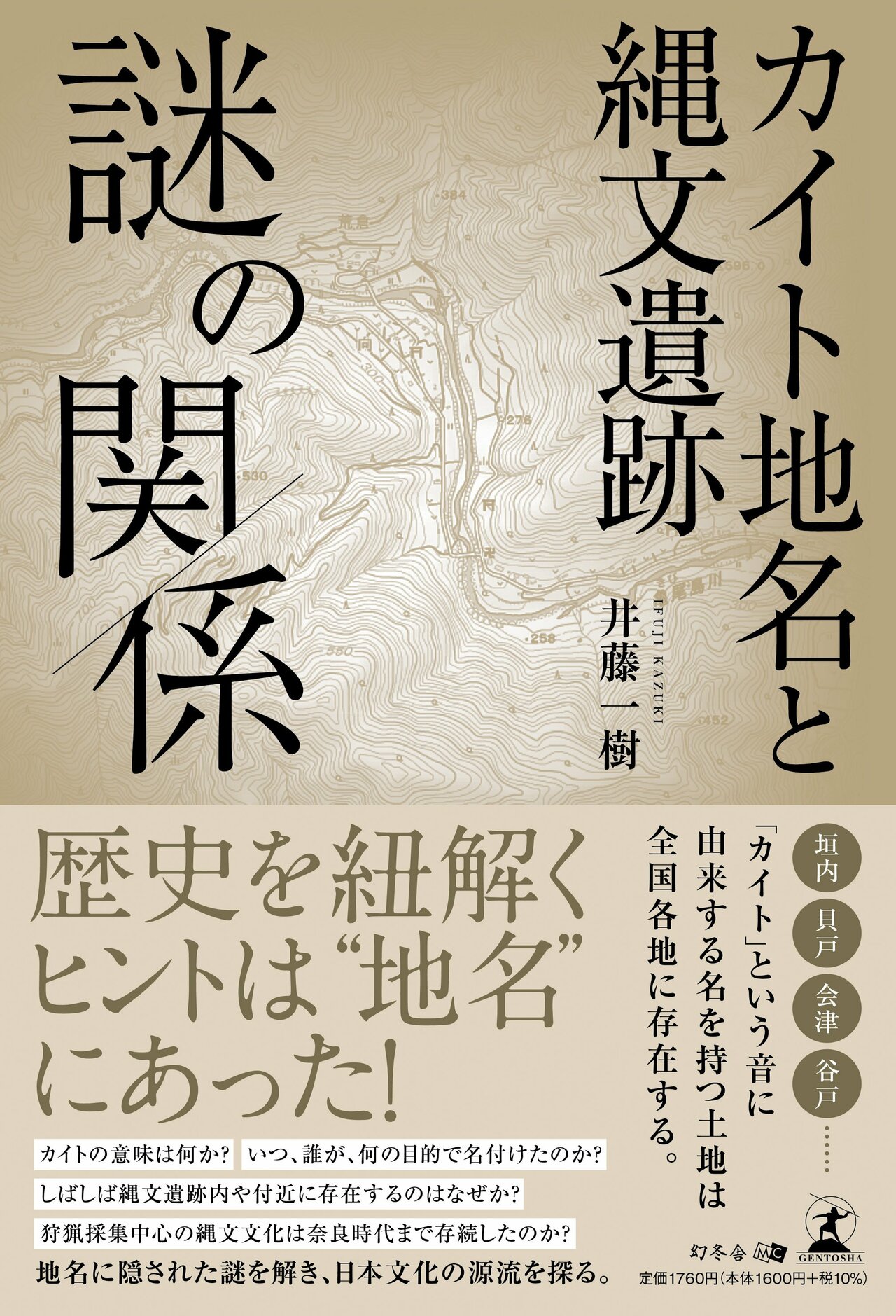【前回記事を読む】全国にひっそりと残る謎の古地名「カイト」とは? 市町村名にもならなかった理由と小字に隠された日本の歴史的背景
第一章 カイト地名とは
三、小字とは
それによると小字地名は現在より数倍多く、現在の小字に併合された様子がよくわかります。その資料ではカイトの小字地名が二ヶ所のみとなっていますが、併合後の現在の小字では四ヶ所あります。
これを見た時一瞬目を疑いました。しかし何度見ても間違いなく、いろいろと調べた結果、以前からカイトも使われていたことが判明しました。
どこの地区も区長の引継ぎで重要書類の入った箱を引き継いできていますが、その中の一番重要なのは区内の土地の所有者を表示した大きな手製の地図です。
森区にもあったそうですが近年になって紛失したそうです。それには四ヶ所のカイト地名が記入されていたようです。おそらく、分家等で分筆されて便宜上いくつかの小字に分けられていたものが地租改正で復活したものと考えられます。
最近になり、私の隣組になる黒佐区の区長箱を見せていただく機会がありました。
こんな古い書類は見ることも無いので捨てたい、と言われていたものを店のお客様が持ってきて下さったのです。
中身は先にも述べた小字ごとの田畑・山林の詳細図と検地帳をさらに詳しく地価等も記入されたものであり、地租改正の折の資料であると考えられます。
驚いたことに、一冊目の「洞口」という小字地名が朱線で抹消され、「大洞開津」と訂正されていたのです。さらにその横に「字違エハ 大ニ困却ス 改テ 大洞開津 以下倣之」と朱書きされていました。
この冊子は黒佐区で作成されたものであり、明治になって村の役場が江戸時代の領主から引き継いだ書類と突合して訂正したものと考えられます。長い間に意味のわからない「開津」が住民の間では「洞口」(大洞の入り口)に変わっていたのでしょう。