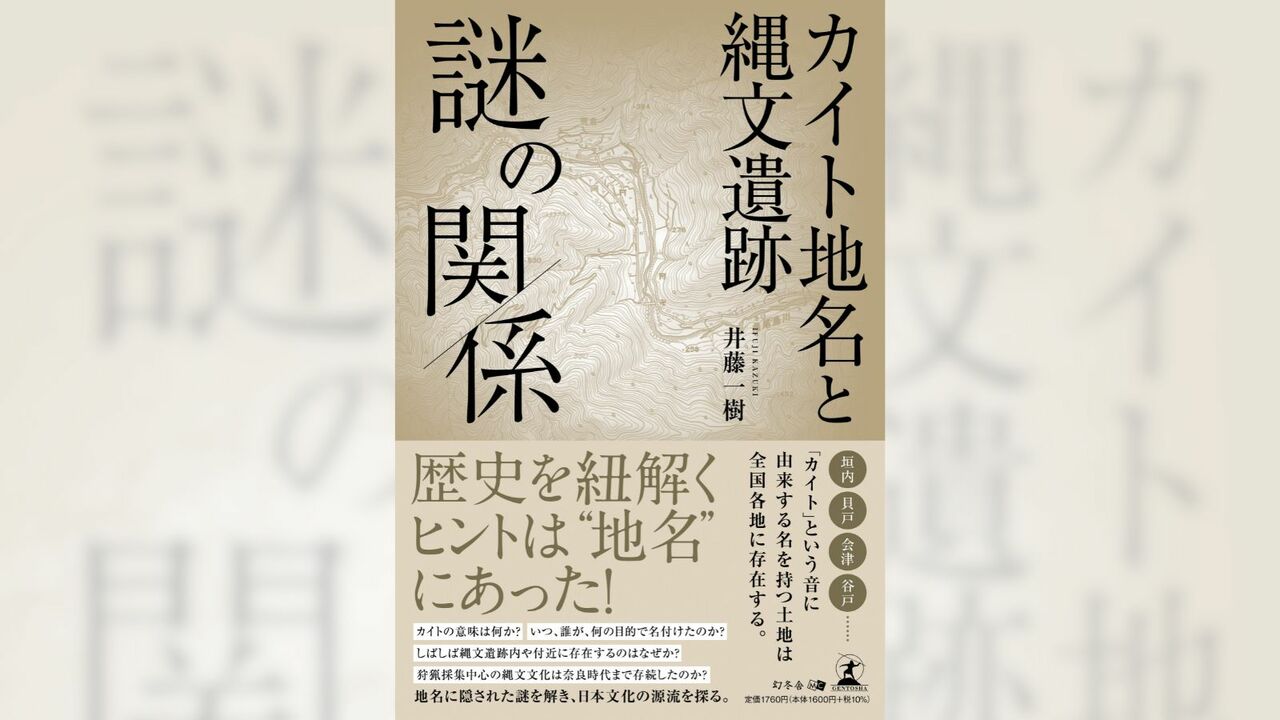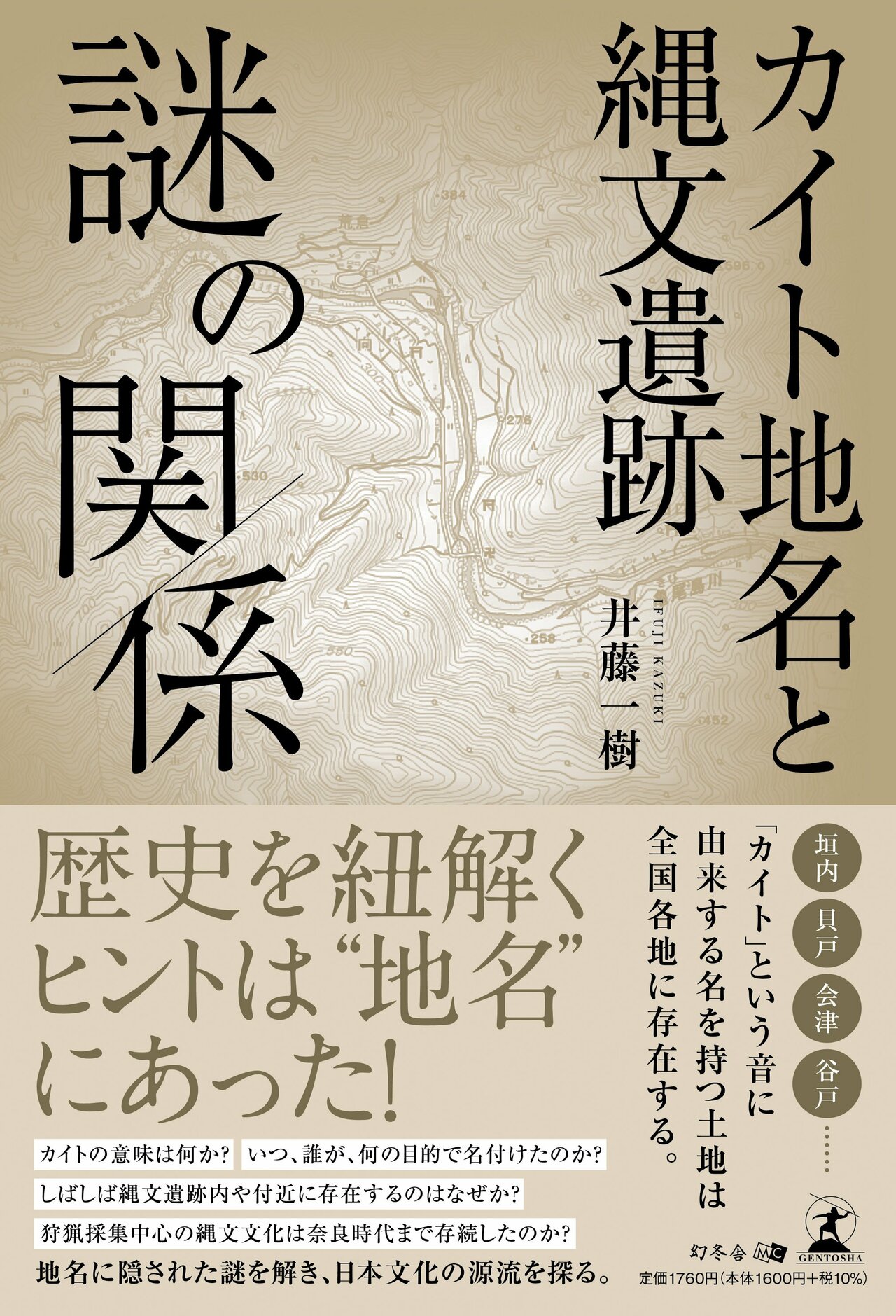【前回記事を読む】郡上市約4500の小字のうちカイト地名は約200ヶ所に及ぶ
第一章 カイト地名とは
四、 カイト地名の漢字表記
カイトが奈良県起源であれば「垣内」が一番正しい表記と考えられますが、「垣内・かきうち→かきち→かいち→かいと」と音転、音便変化・転訛したのではないかと推測されます。
「垣」を「かい」と読む例として「垣間見る・かいまみる」があり、「垣・かき」の「き」がイ音便化したとも考えられます。
しかし、全国のカイト地名表記を見ると、カイトは「かきうち」が変化したものではなく当初から「かいと」表音であったと考えた方が妥当かもしれません。
したがって、奈良県、岐阜県飛騨地方においても「かいと」表音に「囲われている土地」というカイトの概念を考慮して「垣内」という漢字を当て字したとも考えられるのです。
全国的に大字ごとにほぼ同じ表記が使われており、長い間にカイトの意味が忘れられ、地域ごとに適当に漢字を当てたと考えられるため、漢字表記からカイトの意味を探るのは無理があるようです。
また、小字全体に占めるカイト地名の割合は郡上市で四・五パーセント、全国一多いとされている奈良県は約五〇〇〇ヶ所以上のカイトがありますが、小字の総数も約一三万ありますので四パーセント前後となり、そんなに突出しているわけではありません。
奈良県、関東地方のカイトについては、別章で詳細に記述いたします。