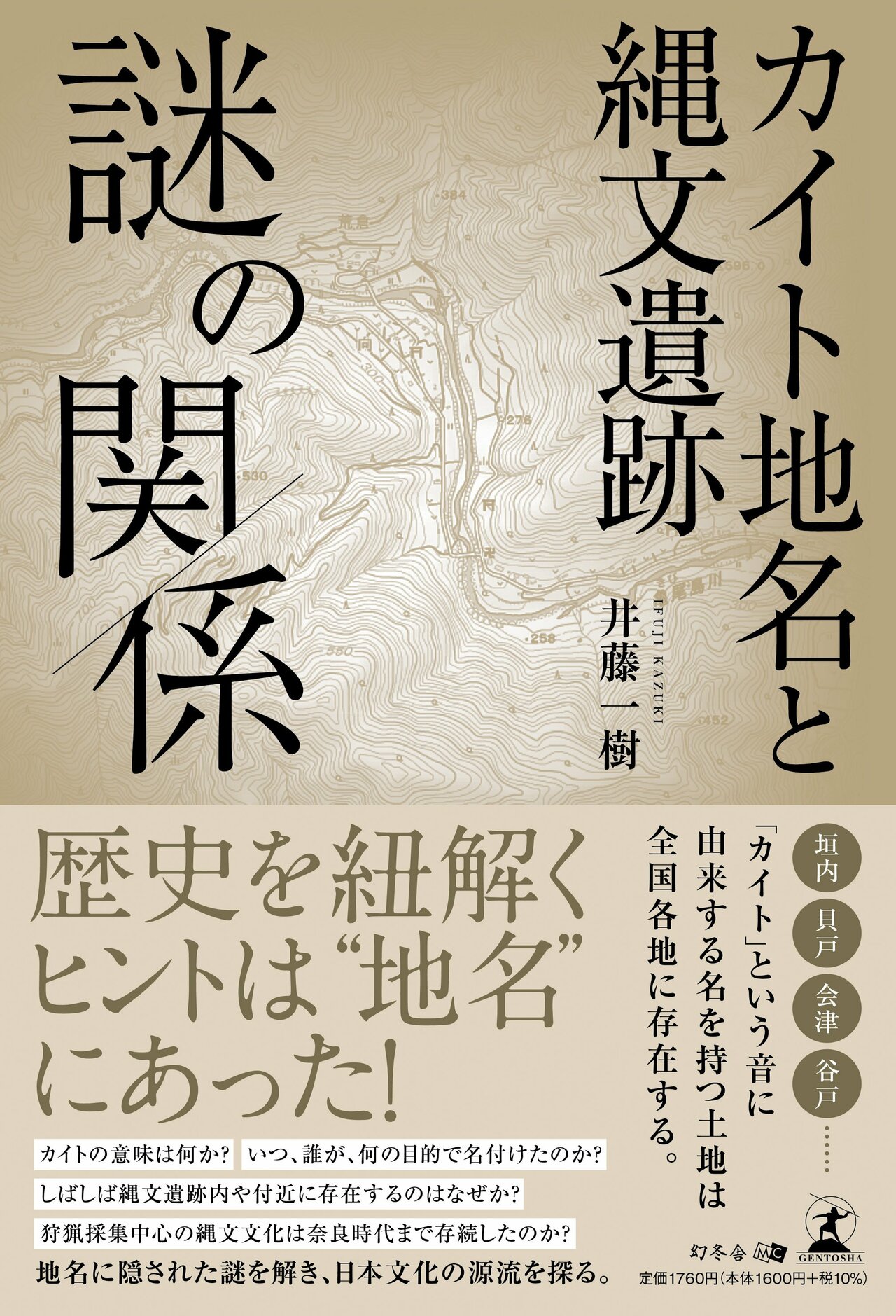六、カイトはいつ頃できたのか
カイトと思われる記載が確認できるものが、『万葉集』大伴家持の歌に二例見受けられます。
「わがせこが 古き可吉都(かきつ)の 桜花 未だ含(ふふ)めり 一目見に来ね」の場合、万葉かなで「可吉都」と表記されています。
もう一首では「可伎都」と表記されていますが、私はこの例はカイトではないと考えます。
おそらく彼が北陸へ赴任した時の屋敷内に咲く桜のことを歌った歌だと思いますが、越中の国、国司という高官であったから、さだめし豪邸であったと考えられ、「垣ノ内」ではなかろうかと推測します。
カイト地名の記録については、鎌倉時代以降に多くの記録が残されているようですが、カイト起源の時期、意味についての記述は残されていません。
ここからは、私が調査した結果からカイト起源の時期を解き明かしていきたいと思います。そこで、以下の仮説を立ててみました。
(一)カイトの発祥は一一八九年以前である
カイトはほぼ全国にありますが、私が調査した範囲では岩手県、青森県・秋田県・山形県には一ヶ所もありません。
また、宮城県・福島県についても極端に少なく、東北地方には部分的にしか国の権力が及んでいなかった時代に付けられた地名であることが読み取れます。
一一八九年、奥州合戦により平泉の藤原氏は源頼朝により滅ぼされます。これによりようやく日本は全国がほぼ統一されました。
したがって、一一八九年以降にカイトが実施されたのであれば岩手県、青森県等にもカイトがあるはずです。
このことによりカイトの発祥は一一八九年以前であることは確実と言えます。
(二)カイトの発祥は七八四年以前である
奈良県大和盆地のカイト地名分布図を作成したところ、藤原京跡地と平城京跡地のカイト分布に大きな違いがあるということに気付きました。
藤原京跡地には多くのカイトが存在するのに、不思議なことに平城京跡地にはわずかしか存在しないのです。
藤原京は六九四年に飛鳥京より遷都して、七一〇年に平城京に遷都されるまでの一六年間、平城京は、七八四年に長岡京に遷都されるまでの七四年間大和朝廷の都でした。いずれも大和盆地の中に位置します。
したがって、カイトの発祥は平城京が廃止された七八四年以前と考えられます。
【イチオシ記事】まさか実の娘を手籠めにするとは…天地がひっくり返るほど驚き足腰が立たなくなってその場にへたり込み…
【注目記事】銀行員の夫は給料50万円だったが、生活費はいつも8万円しかくれなかった。子供が二人産まれても、その額は変わらず。