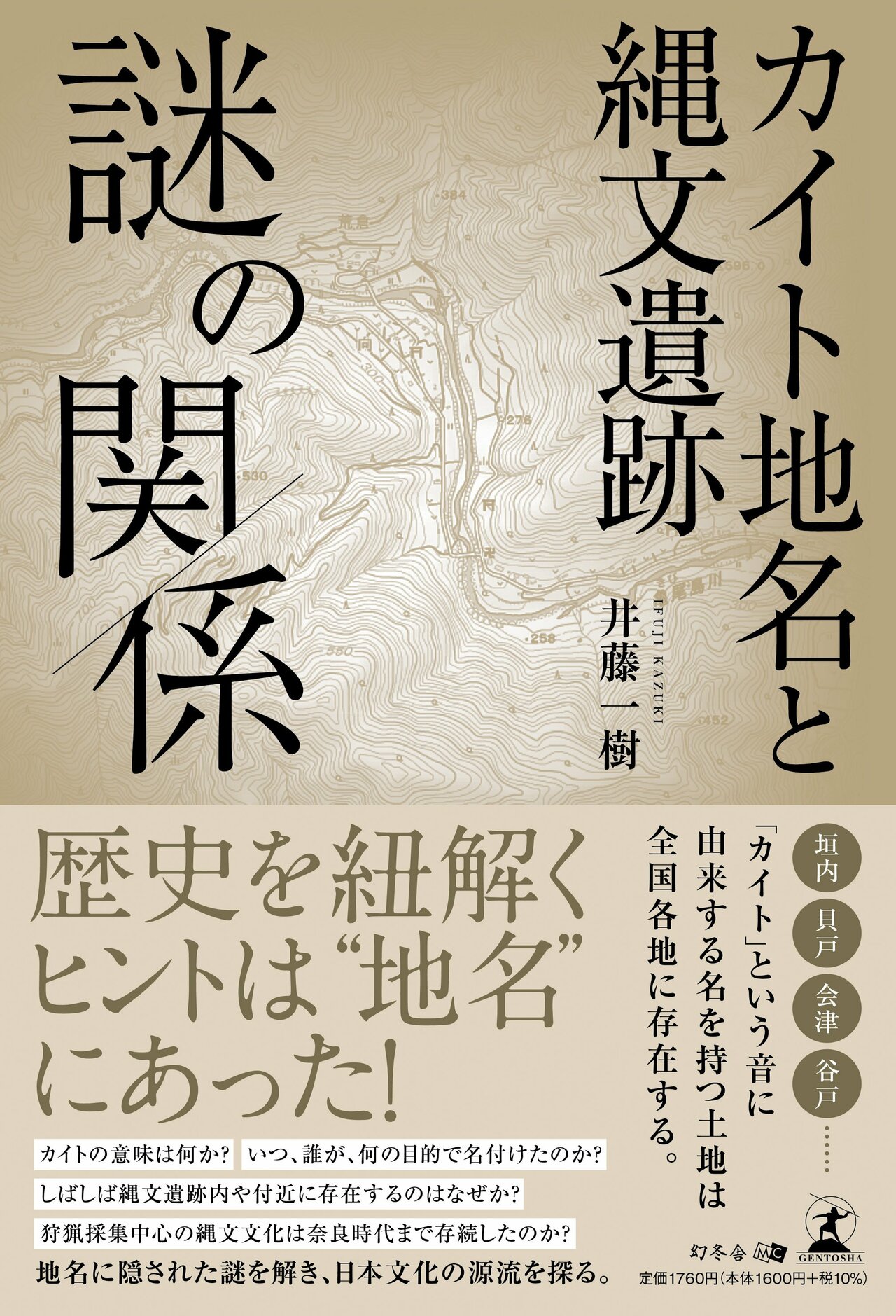五、カイト地名の複合語について
カイト地名は「垣内」のみの単語で用いられる場合もありますが、ほとんどの場合は「東垣内」のように「東」等の語と「垣内」の複合語で表されます。複合語の場合、後に来る単語が主たる意味を表し、その語頭が、か・さ・た・は行の場合は「連濁」といって濁って発音される場合が多くなります。
カイトの場合、同じ地域(大字等)にカイトが複数箇所ある場合にどこのカイトか区別するために前に名詞が付加されて複合語になったものです。
「東垣内」の場合、後ろに来た体言の「垣内」がこの複合語の主たる意味を表すものであり、連体助詞の「の」を加えてみると「東の垣内」であり、カイトには違いありません。
これの前後が入れ替わると「垣内東」となり、「垣内」の東側の場所を表す地名であり、もはやカイトではなくなります。
したがって、ある区域に「東垣内」のみがある場合、中心となる「垣内」もしくは「中垣内」、および対極となる「西垣内」が何らかの理由で消滅したものもあると考えてよいと言えます。
このことは東西南北のみでなく、大小・前後・上下の場合も当てはまります。