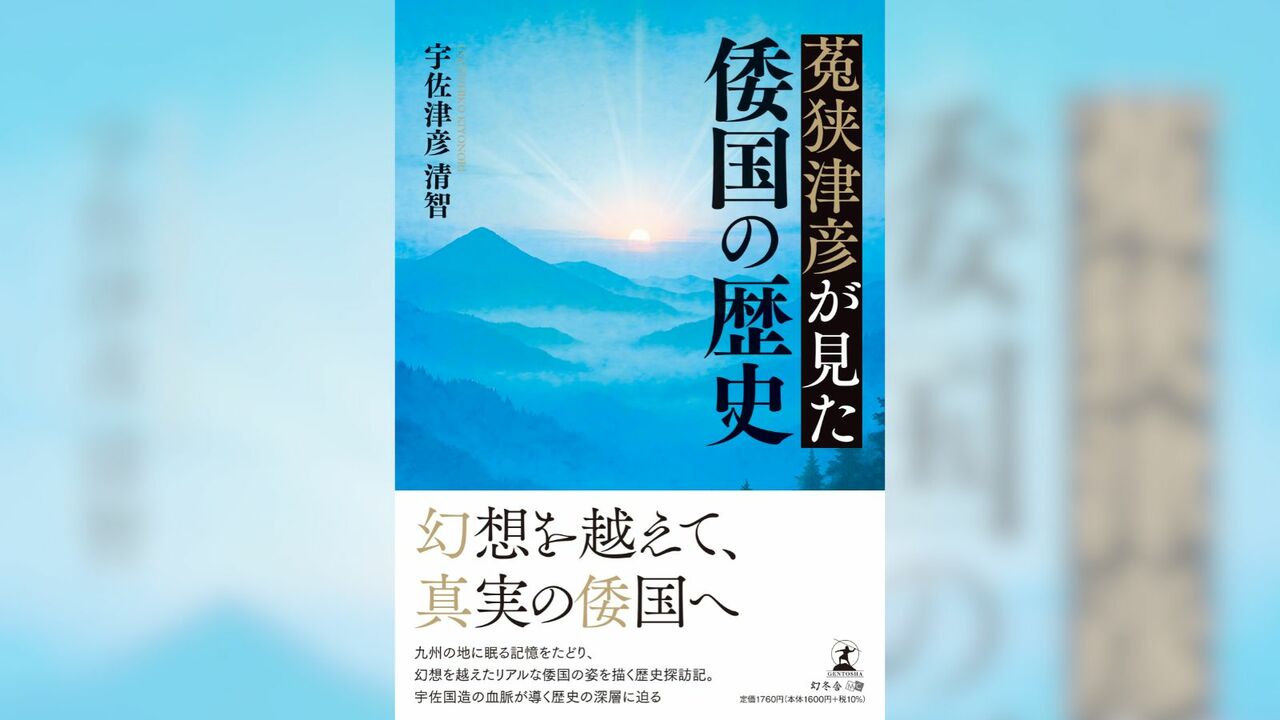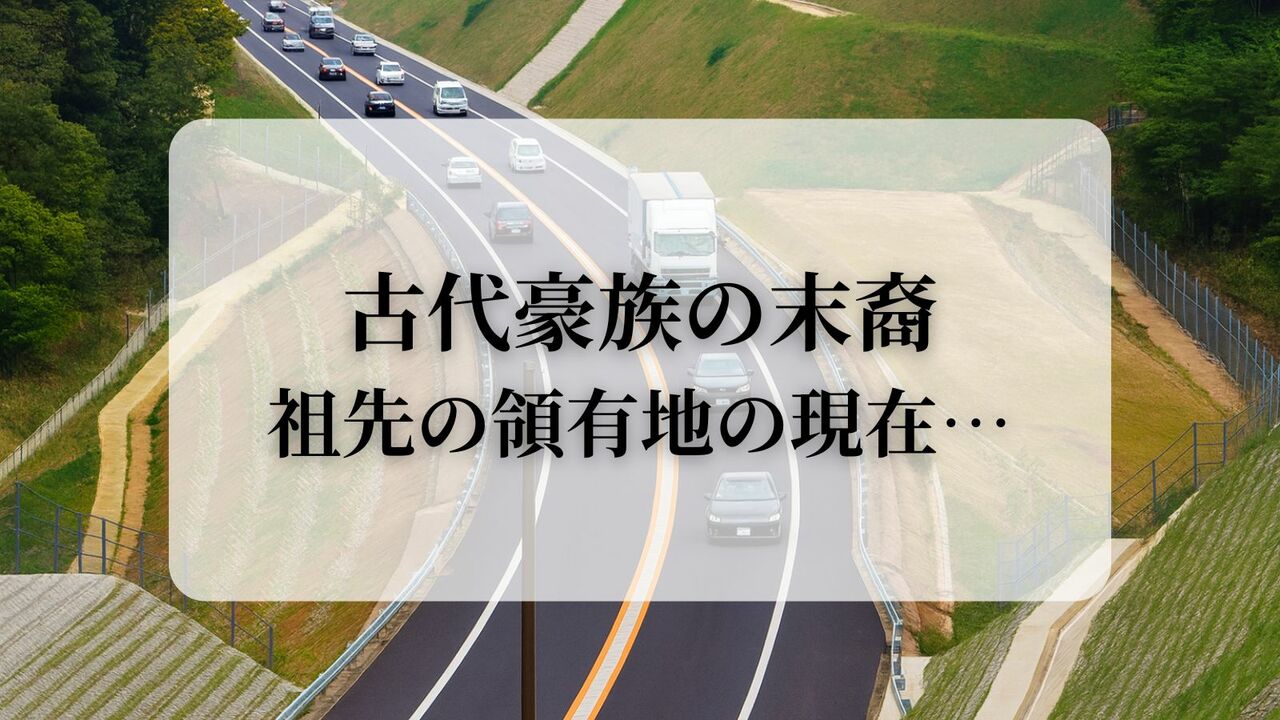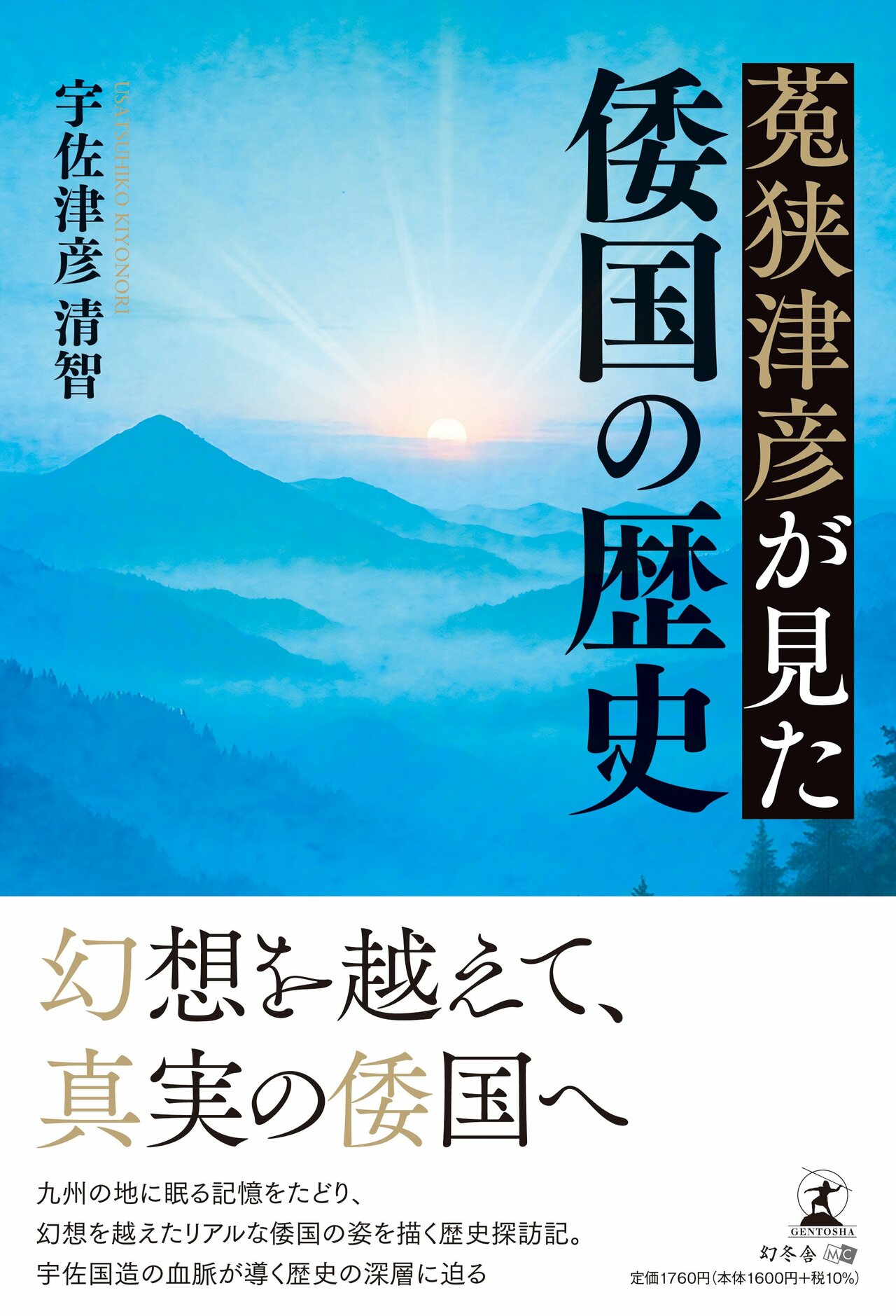はじめに ~偉大な先祖達に捧ぐ~
稲用(いなもち)家というのは、宇佐公豊が鎌倉御家人として稲用太郎を名乗ったところからはじまる。
中津市三光西秣(にしまくさ)に屋敷を構え、泰源寺というお寺を菩提寺としている。昔はこの辺りは野仲郷弁分で、三十町の荘園を管理する猪山(いやま)八幡宮の経営に充てていた。同族に安心院(あじむ)家があり、大友宗麟との戦いで滅亡する。
この歴史調査報告書を書き上げる前に、わたしは先祖の墓にお参りをした。人の一生というのは、決してその人ひとりだけのものではない。わたしには大学生と高校生の子供が二人いるが、わたしは彼らの人生にも責任を持たなくてはならない。
そしてその逆に、父母を含めたご先祖様への感謝という意味において、わたしは彼らの功績に責任を負っている。今ここに生きているわたしという存在は、次の代へ先祖から引き継いだもの全てを延べ送りするための存在なのだ。その気持ちを忘れることがあってはならない。人が生きるにあたって大した意味はない。
しかし命を次に渡していくという責任は常にわたしのなかにある。そしてそれは、心のなかにあればいい。人の世は平家物語が伝えるように不確かで儚いものだ。絶対と信じられるものはこの世にはない。今日はこの家に眠ることができたとしても、明日再び同じように眠ることができるかは分からない。この世のなかで確かなものなど、どこにもないのだ。
しかし多くの人々は、自分の思い描いている幻影を信じようとしている。それは決して悪いことではない。ひとりひとりが信じることによって、それが社会という繋がりを生じさせていることも事実だ。社会を信じるということによってのみ、我々は生きることが可能になる。例えそれが幻想であったとしても、明日という夢を見ることができる。
この歴史調査レポートは多くの人々にとって、その幻想を吹き飛ばす悪魔の囁きであるかもしれない。一部の人々は、次の幻想を描く原動力になるかもしれない。わたしは破壊者でもあり創造者でもあるのだ。
現在は明治維新の御世から百五十年を超えた。そろそろ次の時代の到来を深く考えなければならない。時代が変わる時、これまでの価値はことごとく失われるが、それに負けない創造力が必要なのだ。
わたしがここで先祖の菟狭津彦達の視点にこだわるのは、彼らは古い時代の終焉と新しい時代の息吹をその目で見てきた生き証人だからだ。わたしもまたそんな生き証人のひとりになってみたいと思っている。
旅立ちの準備は整った。さて、歴史調査に出発するか。
2025年7月26日
宇佐津彦 清智