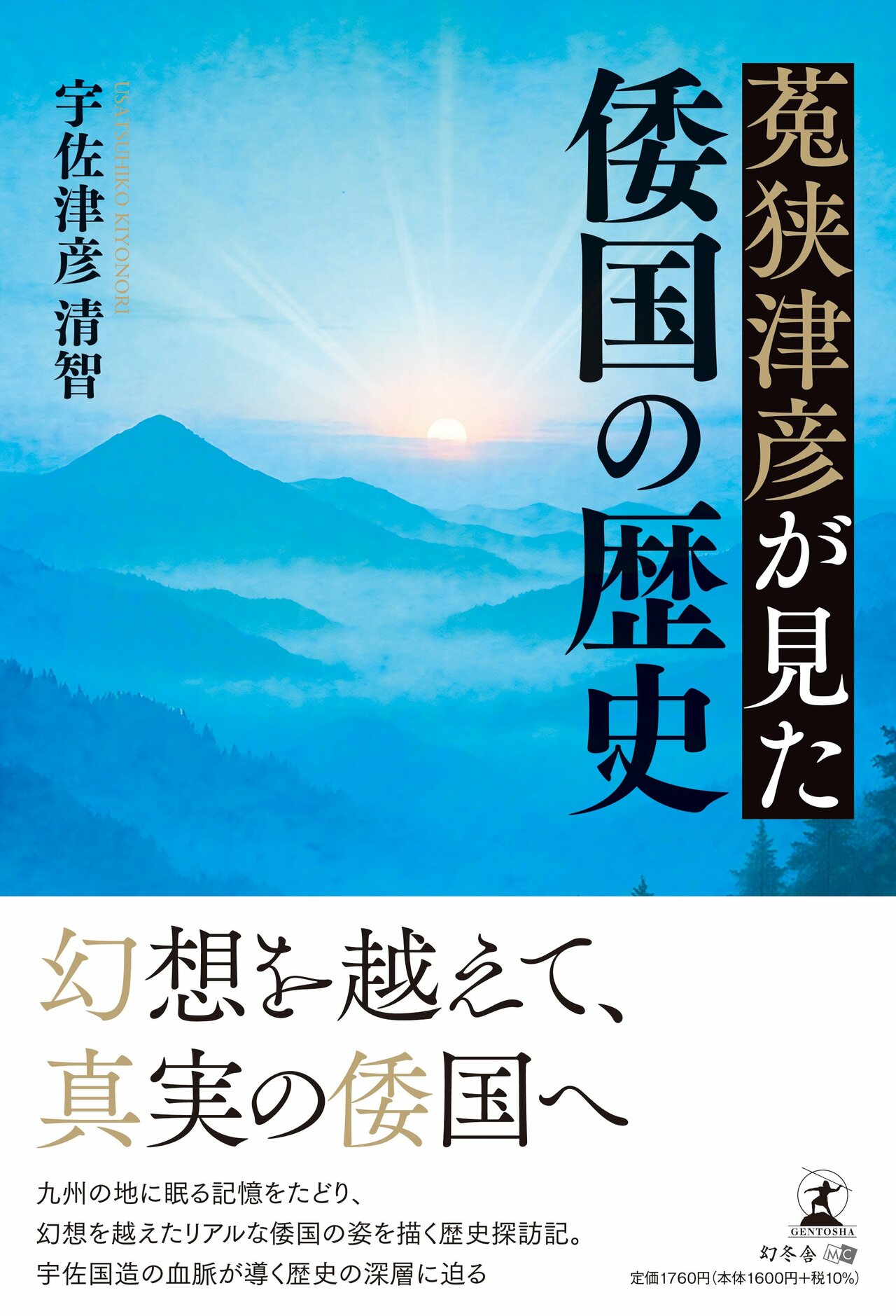プロローグ
自らの身体のなかに流れる古代からの先祖達の感覚に寄り添いながら、わたしは長い年月をかけて九州を中心に古い歴史の記憶が残された場所を折々にわたって訪ねてきた。時間のかなたからおぼろげに、ただ心を集中させるとしっかりとした声で語りかけてくるものがあった。
それぞれの地に刻み込まれた人々の生業や思いに共鳴するように、自分が知る歴史の謎解きを自らの考察と直感を元に試したものがようやくこの1冊になった。
まとまったのは20に及ぶ「歴史調査報告」。風土記の残片や古事記・日本書紀以前から、平安・鎌倉へとつづく悠久な時間のなかで繰り広げられた王朝や有名無名な氏族の興亡を、九州の古代豪族(宇佐国造)の血脈につながる、わたしがまとめた紀行歴史探訪集である。
1 野仲郷のこと
宇佐公仲の次男に宇佐公成という人物がいた。彼は遠縁に当たる宇佐(益永)清輔の娘と婚姻し公邦を授かる。清輔の死後、清輔が領有していた野仲郷は最終的に外孫であった公邦が相続することになった。
これらの経緯は、嘉禄2年(1226年)八月に宇佐宮擬大宮司であった宇佐公邦から申し出があり、宇佐宮がそれを認めている。その後、公邦の子の公豊の時代に元寇に従軍し、永仁5年(1297年)九月に軍資金の形に野仲郷を深水上野入道に売却していた。
これを徳政の法により、従兄弟に当たる宇佐八幡宮大宮司宇佐(安心院)公泰によって買い手の知行であることを停止し、公豊の知行とする了承を受けている。
この辺は鎌倉遺文5及び26と稲用文書による。とにかくいつの世も相続は煩わしいものだが、この土地は今ではわずかとなってしまった。ただ現代でも稲用家また稲用智鶴子が嫁いだ井下田(いげた)家によって守られ続けている。最近では牧草地だったところを東九州自動車道路に供出している。

【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...