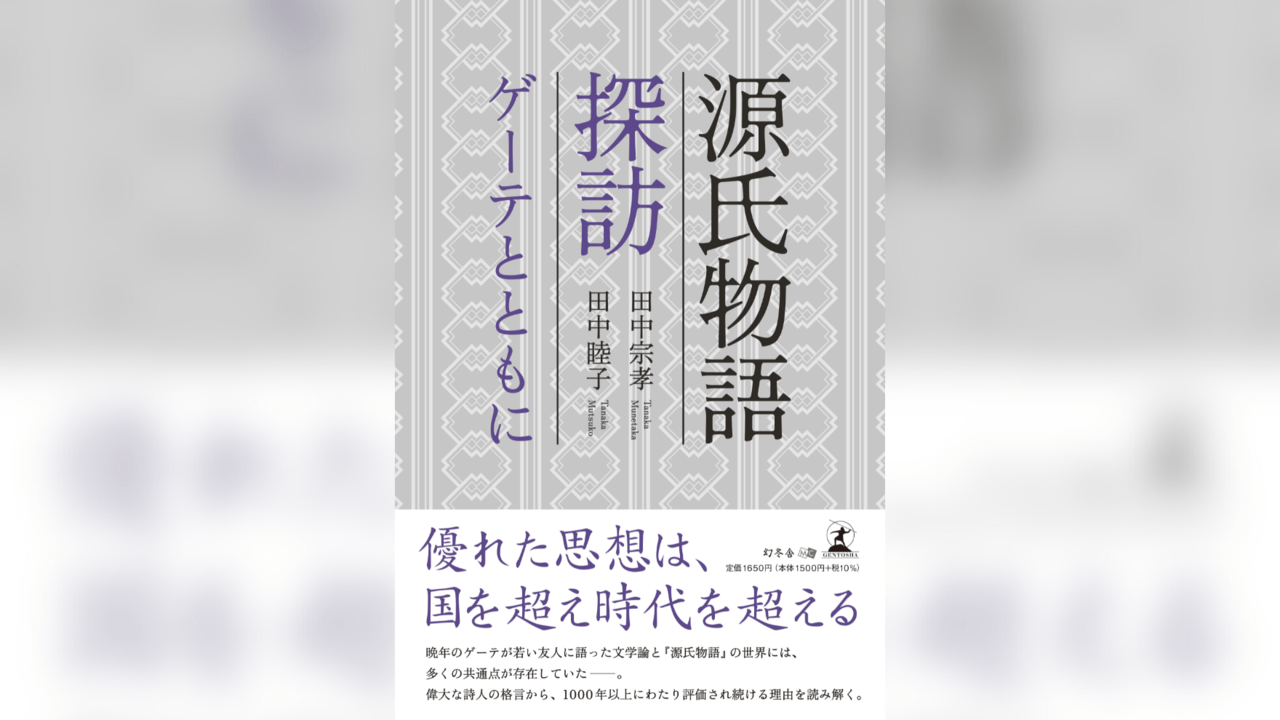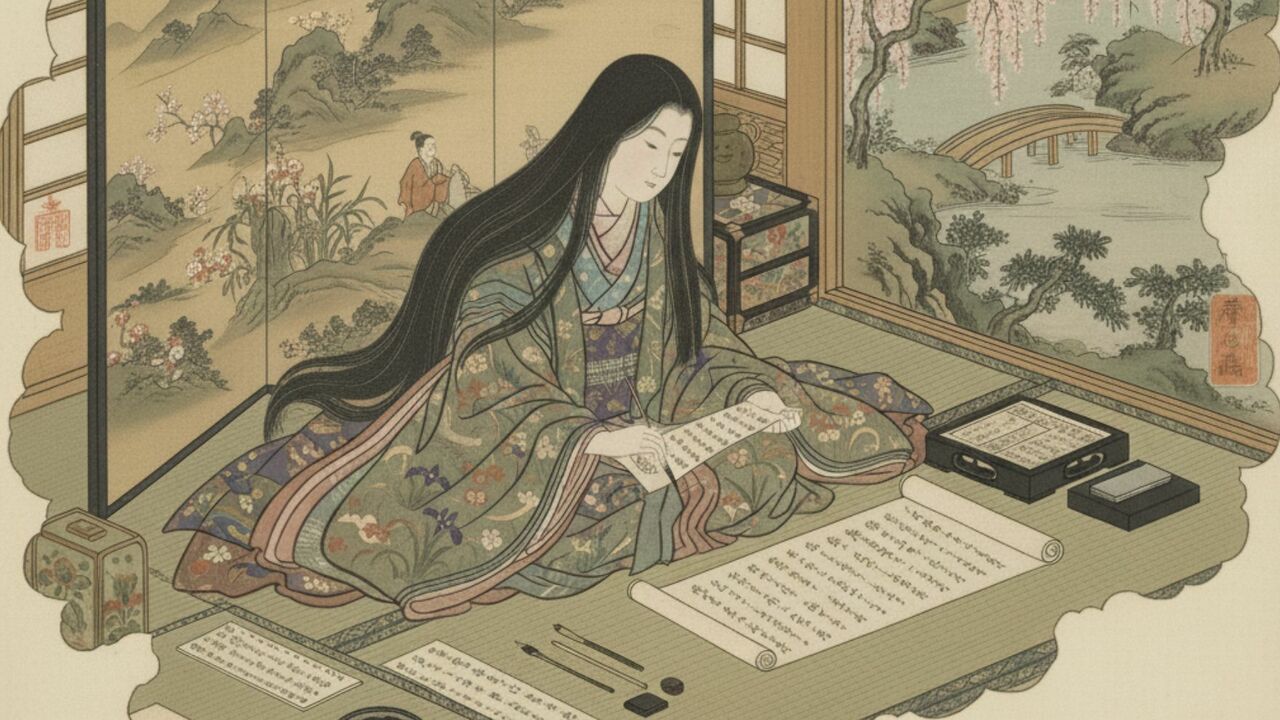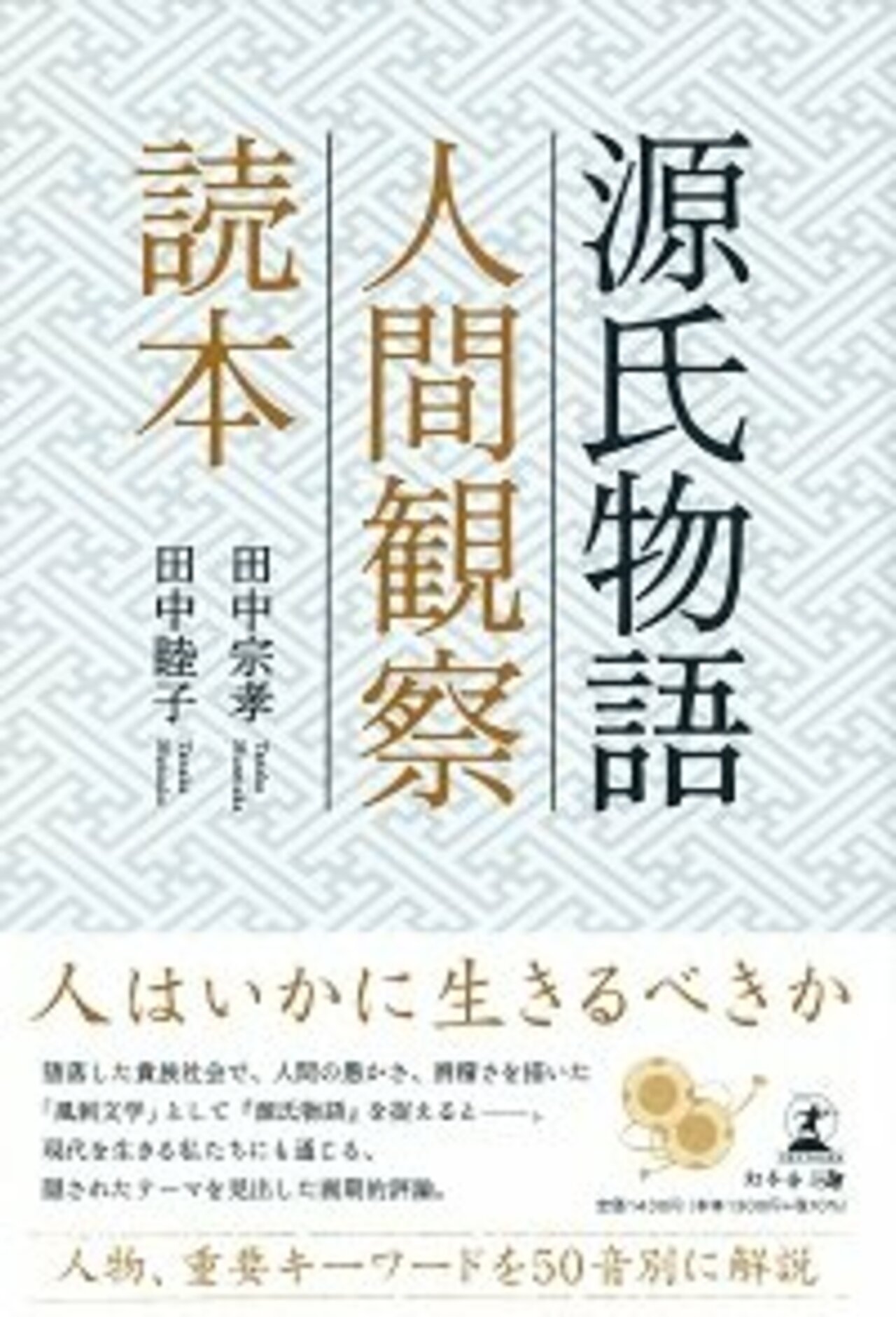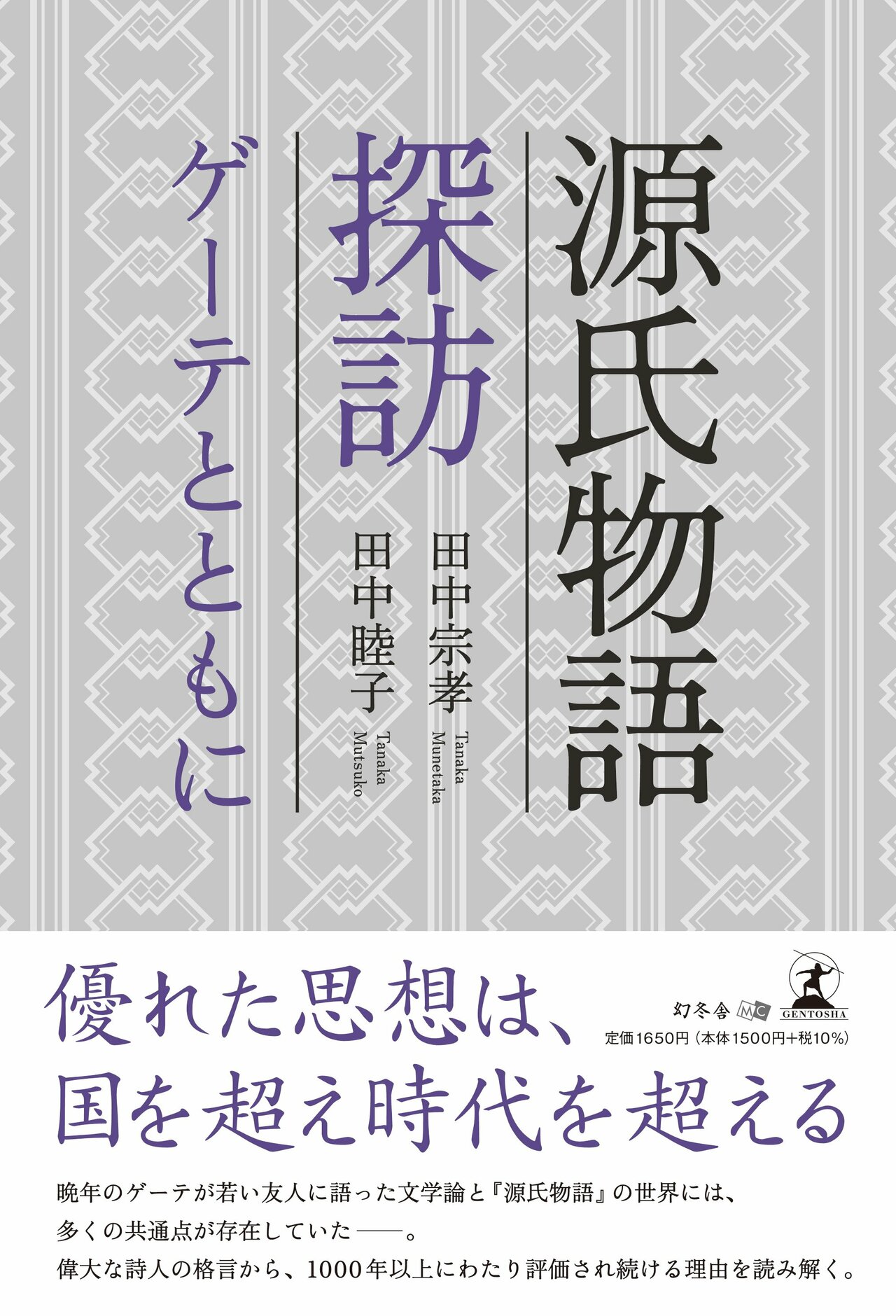【前回記事を読む】禁断の恋の真相――光源氏と藤壺の不倫は桐壺帝の思惑だったのか?
一 『ゲーテとの対話』(上)を読みながら考える
機会の詩
ゲーテ「詩はすべて機会の詩(ゲレーゲンハイツゲディヒテ)でなければならない。つまり、現実が詩作のための動機と素材をあたえるのでなければいけない。ある特殊な場合が、まさに詩人の手にかかってこそ、普遍的な、詩的なものとなるのだ。私の詩はすべて機会の詩だ。すべて現実によって刺戟(しげき)され、現実に根拠と基盤をもつ。根も葉もないつくりものの詩を私は尊重しないのだ。」(上六九頁)
『源氏物語』に、次のような一節がある。
「ごほごほと鳴神(なるかみ)よりもおどろおどろしく、踏みとどろかす唐臼(からうす)の音も枕上(まくらがみ)とおぼゆる、あな耳かしがましとこれにぞ思さるる。」(源氏物語①一五六頁)
(ごろごろと、雷よりも恐ろしく、足を踏み鳴らすような唐臼の音が、〔実際は隣家から聞こえてくるのだが〕枕元で鳴り響いているように思われる。ああなんと騒々しいことかと〔光源氏は〕閉口する。)
光源氏が、夕顔の宿で一夜を過ごした際の情景である。紫式部は、唐臼の音を耳の近くで聞いたことがあったのだろう。唐臼の音は、それ自体が詩的であるわけではない。しかし、それが物語の場面に取り入れられ、登場人物や前後の事情と一体化されたとき、詩的な存在として輝いてくる。これを、ゲーテは、「機会の詩」とする。
別の例である。
「いと古めきたる御けはひ、咳(しはぶき)がちにおはす。このかみにおはすれど、故大殿(おほとの)の宮はあらまほしく古(ふ)りがたき御ありさまなるを、もて離れ、声ふつつかにこちごちしくおぼえたまへるもさる方(かた)なり。」(源氏物語②四六九〜四七〇頁)
(〔女五の宮は〕非常にお年を召したというご様子で、しきりに咳(せき)をしておられる。故左大臣の北の方は、〔女五の宮の〕姉宮でおられるが、いつまでも若々しくて、ぜひこうありたいと思うほどのご様子であるのに対して、〔女五の宮は〕姉宮と違って、声も太くて無骨な感じである。それもそれぞれの境涯による。)
光源氏が女五の宮を訪れた際の宮の様子を描いた箇所である。紫式部は、老人の老いた様子も人それぞれであることを、自身の見聞によって知っていたのだろう。『源氏物語』は、全編、機会の詩である。