武家の都「鎌倉」を自らのステージとして生きた者を「鎌倉人」と呼ぶならば、私もその一人だ。私のように今に生きる者もいれば、歴史の中でこの町が最も輝きを放った中世に生き、その名を今に遺す者も数多くいる。ここではその中から何人かの「鎌倉人」を選んでその足跡をたどる。また、この本は「人」だけではなく「場所」にもスポットをあてている。歴史に名を遺す「鎌倉人」には寺社をはじめとするゆかりの場所が必ずあるから…
歴史・地理
ジャンル「歴史・地理」の中で、絞り込み検索が行なえます。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
-
『鎌倉人を訪ねて』【新連載】松本 彰

【桓武天皇】全員は養えない…70歳までに26人の妻をもち、35人の子どもを授かったものの……。
-
『九頭龍王 オホト』【第8回】森長 美紀

倭海を行き交う船のほとんどが越の船!? 航行技術の高さから、朝鮮出兵の折に水先案内をするのは越人エビスと決まっていた
-
『我が陣営にあるべし』【第8回】林口 宏

16歳で戦場に立ち、敵の首を取った少年武将——桶狭間の戦いに名を刻んだ水野太郎作清久と、丸根砦で散った片山勝高の真実
-
『紫式部日記を読む』【第8回】神明 敬子

【紫式部日記】書くことがなかった正月のはずが...寛弘六年・七年正月の日記は、後に加筆修正されている
-
『カイト地名と縄文遺跡 謎の関係』【第8回】井藤 一樹

突然「君の奥さんは霞のような人だね」と言われたが、意味がよくわからなかった…驚いて理由を聞くのを忘れてしまった
-
『プリマドンナ・デル・モンド』【第8回】稲邊 富実代

「本当に死んでしまうわ」何日も図書館に来ない彼を待ち続けた結果、熱を出してしまい……
-
『ぼくとマンゴとエルマーノ』【第8回】マイク 峯

スペイン語上達のためダハボンへ。30分ほどバスに揺られていると、鉄砲を持った迷彩服の兵士がずかずかと入ってきて...
-
『菟狭津彦が見た倭国の歴史』【第4回】宇佐津彦 清智

日本書紀と三国史記の記述差から読み解く、継体天皇暗殺説と倭国・伽耶・新羅をめぐる6世紀東アジア政変の真相とは
-
『楽ではない お金もかかる 大変なだけ それなのになぜ行った!?』【第4回】本間 照雄

【四国お遍路】「気持ちの維持」が難しい“焼山寺のあと”——多くは、志半ばで帰路につき「挫折」と表現されるが…
-
『JANOBO 幻想のジパング』【第4回】田中 恒行

「時給300円の労働者」外国人研修制度では、“労働法”による保護が適用されず——
-
『巡礼の道・フランチジェナ街道』【第9回】廣田 司

「羊飼いは狼より泥棒を恐れている」ほど物騒だった14世紀――現在はあちこちで"にゃんこ"がみられる街・カプラーニカ
-
『“魔法の国”日本 ~駐日アメリカ大使夫人が見た明治・大正の日本~』【第5回】中村 信弘

壊れた帽子を被っていると罰を受ける!? 数世紀前の韓国は皇帝の命令で、男性は〇〇を被らなければならなかった
-
『喰道楽』【第5回】大藤 崇

夜の店の“営業の型”は、100年前からあった?…嬢のサンタコスと同様、大正時代の女給達はひな祭りにコスプレをしていた。
-
『惰走は駛走に変わる』【第5回】大森 是政

知らせを受けてすぐに遺体を引き取りに行くと、「衛生上の都合で既に火葬した」…納得できない。見せられない理由があったはず。
-
『卑弥呼と古事記と日本書紀』【第5回】吉木 正實

どうして、何のために? 彼らが間違うはずがない。百済王の即位と薨去年から見える「神功皇后紀」の意図的な120年のずれ
-
『続・ながれ星 冬星』【第5回】石田 義一郎

「まさか飛び込むとは……。いい度胸をしているが、命はあるまい」。しかし時が経ち、彼は息を吹き返した——
-
『晋作に銭を持たすな』【第5回】原 雄治
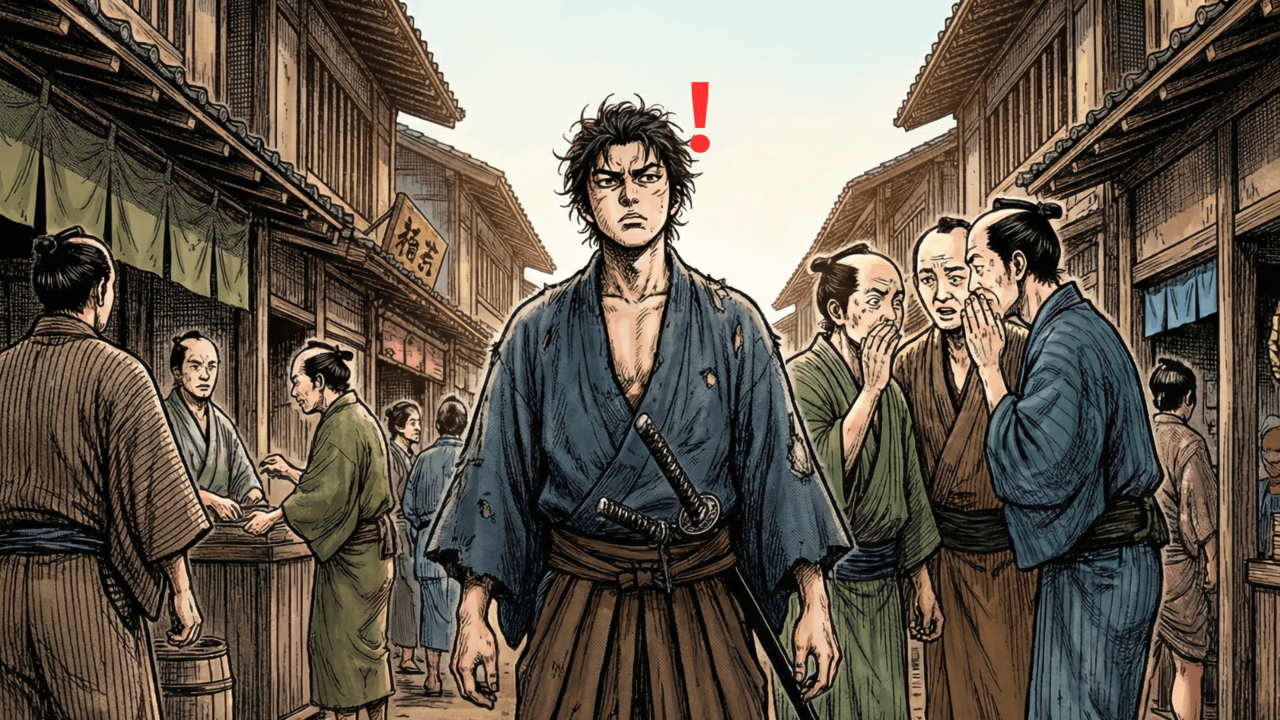
この世は戦場だ。世に生きるとは完勝すること――「異端児」は大罪人となった男の生き方に惹かれ...
-
『テーバイの将軍エパミノンダスとペロピダス』【第5回】竹中 愛語

まずい。もしや、同志たちの脱出を知らせてきたのでは――宴の席での策略の最中、アテネの急使が手紙を差し出して...
-
『振袖の謎森』【第5回】ホシヤマ 昭一

招待客リストに入っていない、招かれざる客を見つけた。…振り袖姿のその女性は、新郎の過去のお見合い相手で…
-
『桶狭間の戦いは迂回奇襲説、長篠の戦いは鉄炮三段撃』【第5回】坂田 尚哉

今川本軍の進軍経路は「織田方」に遺された史料で判断できるのか。鳴海方面説に残る論拠の欠如







