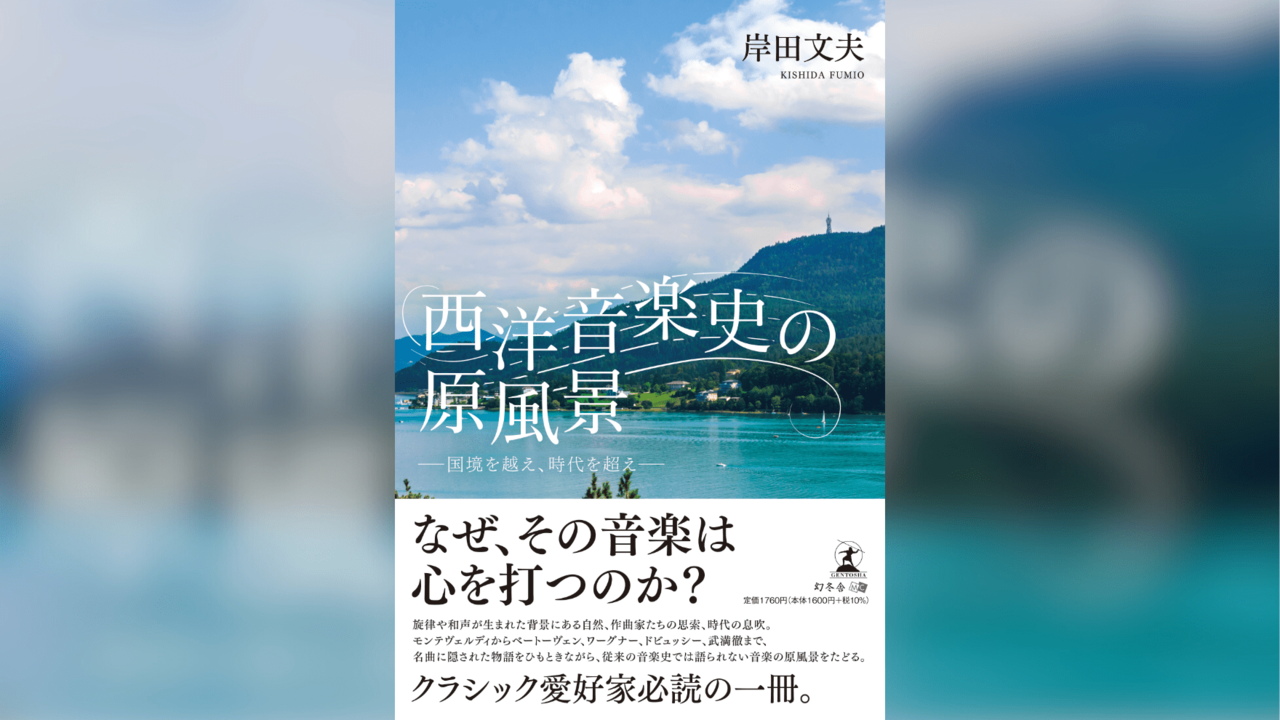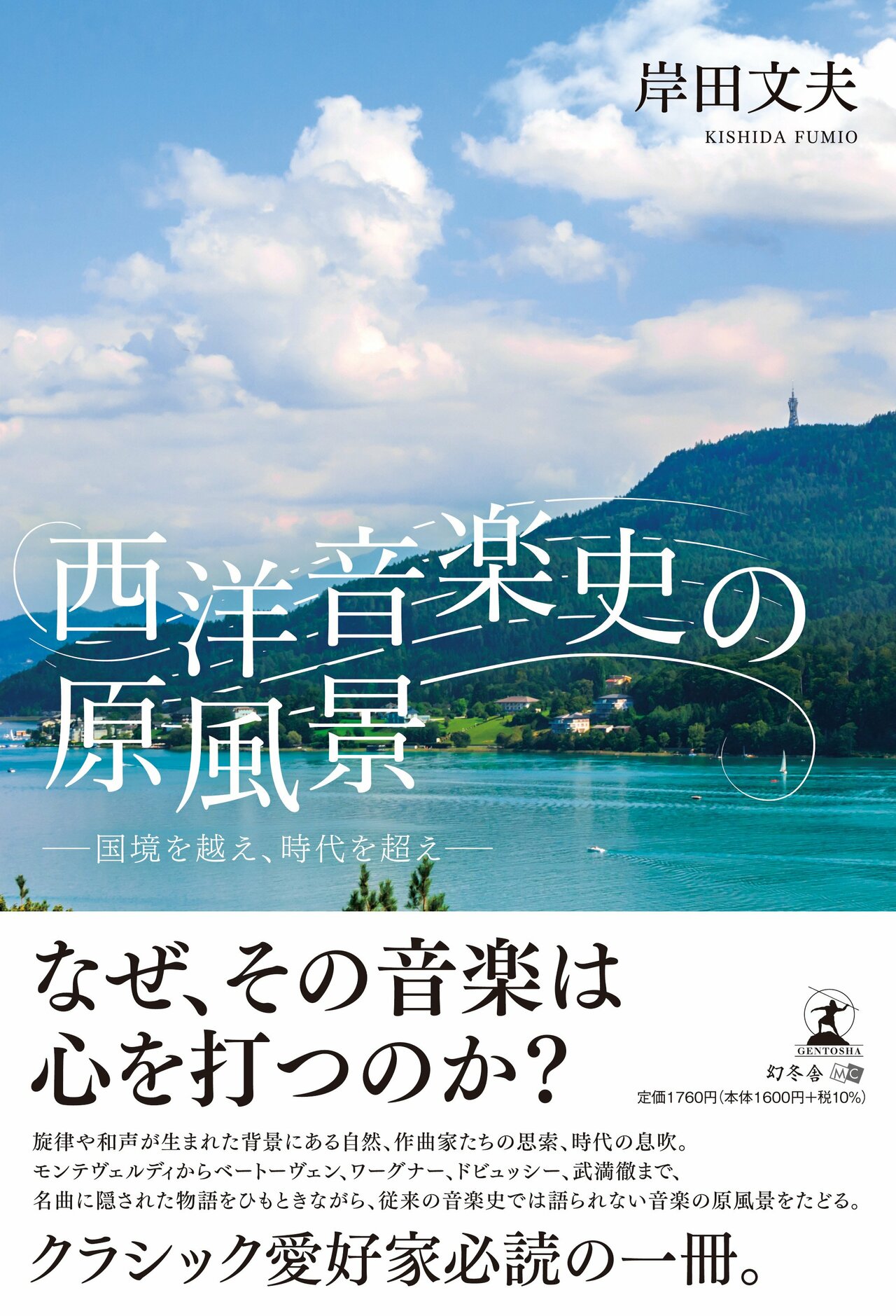はじめに
私がはじめてクラシック音楽に興味を持ったのは、中学校一年生の時、学校が音楽教育の一環として、当時の大阪放送管弦楽団のメンバーによるアンサンブルを招いてくれて、その最初の曲、シューベルトの『軍隊行進曲』のコントラバスが支える重厚な響きに身が浮き立つような驚きを感じた時だった。
ただその時宿題になっていた感想文にはそれをうまく書けなかったように思う。それが、「あっ、これだったのか。」と思い知ったのは、それから二〇年ほど後になって、ハンス・クナッパーツブッシュの指揮するレコードでこの曲を聴いた時である。
この曲は六小節の序奏の後、主題に入って、旋律は円滑に流れつつもその主題の六小節目に和声がニ長調のトニカから、ホ短調の属七という縁の遠い和音に転調するので、音の響きはガラッと変わる。クナッパーツブッシュは、その属七の根音Bをコントラバスで、ここぞとばかり強調する。
「単純な曲だとなめるでないぞ。シューベルトはわずか十二、三小節のうちに、かくも巨大な響きの伽藍を作っているのだぞ。よく聴けい!」といわんばかりの指揮ぶりである。並みの子供にとって、教育効果というものはそれくらいの時間をかけて現れるもののようだ。教育は、子供のうちに、いいものを詰め込んで、気長に待つべきものかと感得した。
特別な音楽教育は受けていないが、学校や職場の合唱団で歌ったり、コンサートやオペラ鑑賞に通ったり、レコード、CDを買い込んだりする、私はそういうクラシック音楽を愛好する元サラリーマンである。音楽書をかじったり、同好の士と一杯飲んで音楽談義を楽しんだりもする。
ただ、いつのころからか、音楽を聴いた感動や、その感動をもたらす源や背景について思うところを日記のように書き綴る習慣が身についた。仕事から半ば引退した七〇代後半になったころから、たまった文章を整理し、調べているうちに、長年聴き続けてきたことの意味のようなものに感じ入ることがあった。
長年聴いてきた中でも、感動的だった演奏の一つはカラヤン指揮のベルリン・フィルハーモニーの初来日(一九五七年)だ。
当時私は二〇歳だったから、あれを一緒に聴いた人達のかなり多くはもうおられないのではないか。そのころのベルリン・フィルハーモニーの音がどんなものであったかをつたない筆ででも若いファンに伝えておきたいという気持ちがよぎる。