【前回の記事を読む】『古事記』が全く触れていない、意外な偉人…日本の歴史において、“都合が悪かった?”その人物とは…そして、神功皇后と卑弥呼の関係である。『日本書紀』が神功皇后を卑弥呼に擬したのはなぜか。『日本書紀』や「神功皇后紀」の紀年に基準年を確保するために、神功皇后と卑弥呼を重ね合わせたというだけのことなのか。だが歴史書としての『日本書紀』に、そんな手前勝手な手法は通用しないに違いない。い…
古事記の記事一覧
タグ「古事記」の中で、絞り込み検索が行なえます。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
-
歴史・地理『卑弥呼と古事記と日本書紀』【第5回】吉木 正實

どうして、何のために? 彼らが間違うはずがない。百済王の即位と薨去年から見える「神功皇后紀」の意図的な120年のずれ
-
小説『新事記』【第6回】吉開 輝隆

「天上界の人間は、地上界の人間と同じようにみえたかもしれませんが、肉体のない、霊体だけの人間です。いや、神なのです。」
-
歴史・地理『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』【最終回】田中 善積
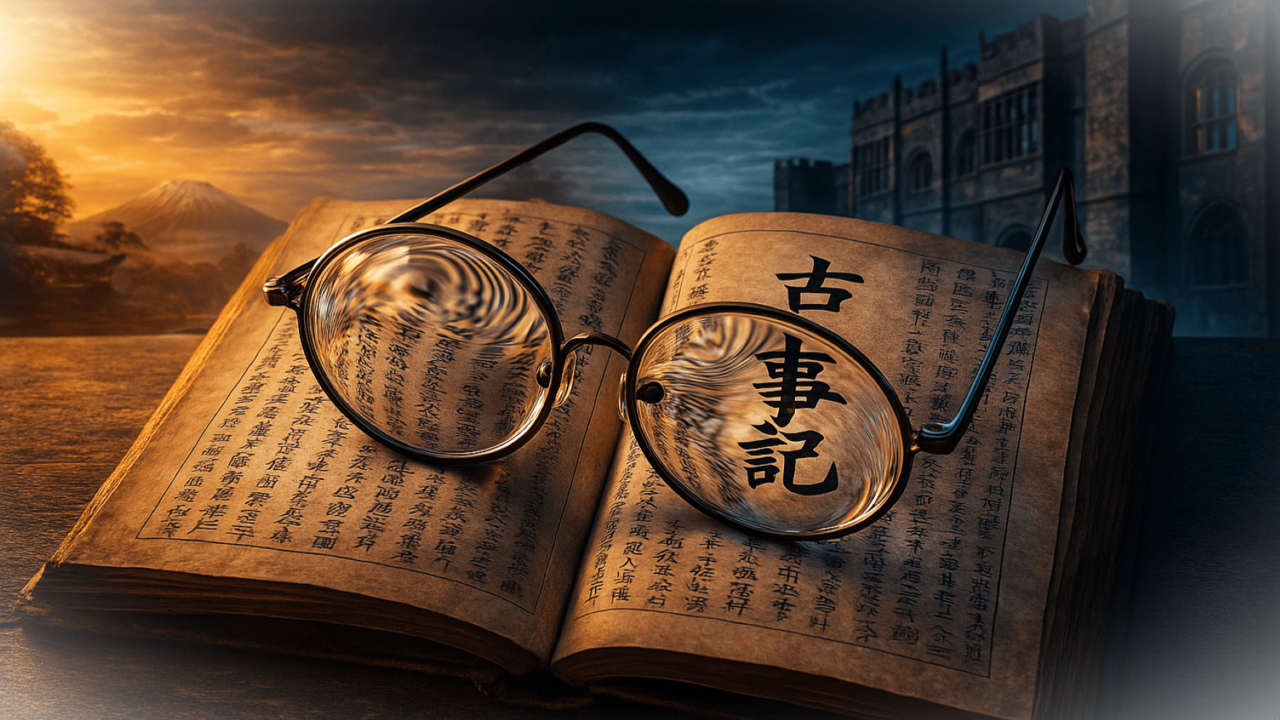
なぜ『古事記は天皇家支配の正当化するための道具』と信じられたのか――欧州国家観が生んだ日本史最大の誤読
-
歴史・地理『卑弥呼と古事記と日本書紀』【第4回】吉木 正實

『古事記』が全く触れていない、意外な偉人…日本の歴史において、“都合が悪かった?”その人物とは…
-
小説『新事記』【第5回】吉開 輝隆

天地創造と神々の誕生をめぐる神秘の旅へ――双つ神と独り神、それぞれの役割と神代の物語を辿る壮大な神話的対話
-
歴史・地理『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』【第11回】田中 善積

「国家安泰」、「民の幸福」そして、「永遠の日本」——苦難を越え、天武天皇が渇望した理念は『古事記』に刻まれた
-
歴史・地理『日本神話における「高天原」とは何か!?』【最終回】松浦 明博

神の住む天上国? それとも為政者による虚像? 「高天原」に宿る信仰と創造の原点
-
歴史・地理『卑弥呼と古事記と日本書紀』【第3回】吉木 正實

『日本書紀』のからくり──史実改ざんの疑いと2つの奇怪な記事を紹介
-
小説『新事記』【第4回】吉開 輝隆

「天上界は神の国、すなわち、真実の国…真実のもとには、真実の慈悲があります。」
-
歴史・地理『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』【第10回】田中 善積

血で血を洗う争いを終わらせるために…天武天皇が考えた“権力トーナメント”の仕組みとは
-
歴史・地理『日本神話における「高天原」とは何か!?』【第11回】松浦 明博

なぜ『高天原』の読み方は分かれたのか――『たかまのはら・たかあまはら』の背景
-
歴史・地理『卑弥呼と古事記と日本書紀』【第2回】吉木 正實

根底に流れる思想が「天皇統治の正当性の主張」である以上、『日本書紀』は、『古事記』によって枷をはめられている
-
小説『新事記』【第3回】吉開 輝隆
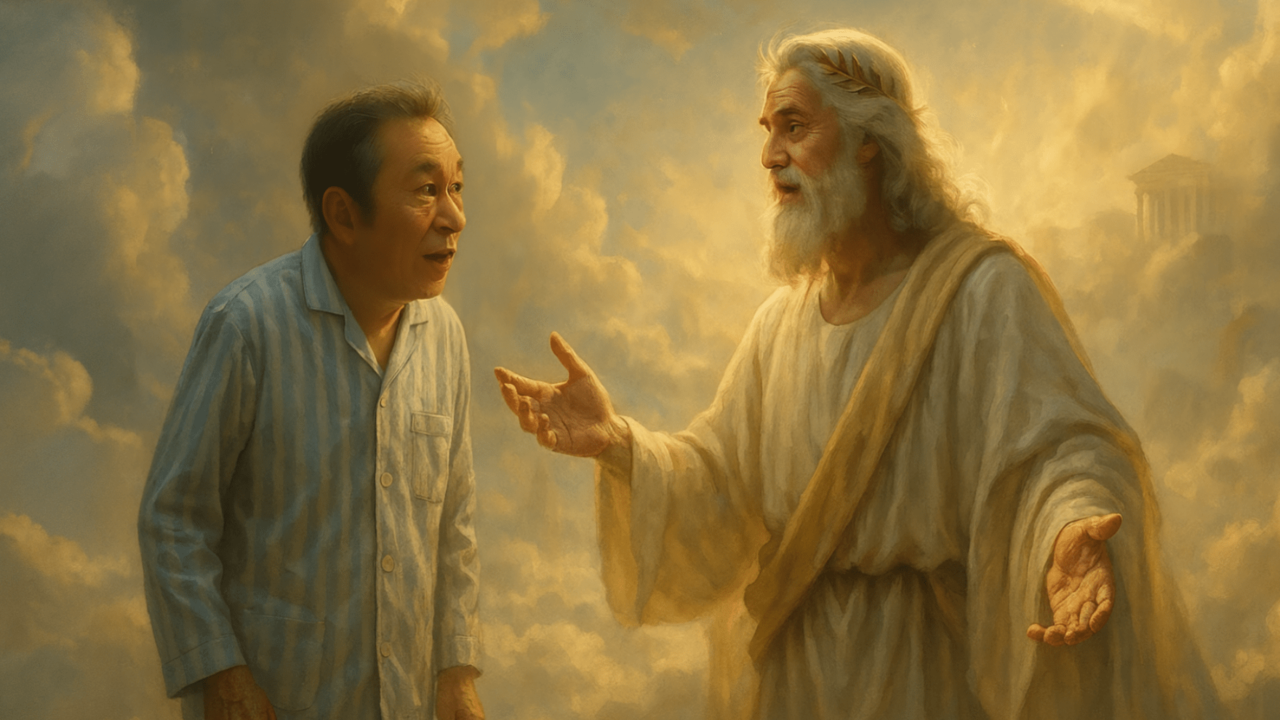
えっ、私が神に!? 我の神(あれの命)が案内する、"神になる方法"と天上界へのスピリチュアルな旅がはじまる
-
歴史・地理『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』【第9回】田中 善積

どうすれば日本は安定的かつ永遠に存続するであろうか――そのカギとなるのは、国家の中心となるべき天皇のあり方であった
-
歴史・地理『日本神話における「高天原」とは何か!?』【第10回】松浦 明博

聖なる世界としての高天原は「たかあまはら」、あるいは「たかあまのはら」と読むのが自然である
-
歴史・地理『卑弥呼と古事記と日本書紀』【新連載】吉木 正實

歴史書に存在しない女王・卑弥呼。当然、その存在は何らかの形で記されているだろうと思うが...
-
小説『新事記』【第2回】吉開 輝隆

午前4時24分、大音声を残して消えた老人。その夜、その老人が家を訪ねてきたので挨拶をして下げた頭を上げると…
-
歴史・地理『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』【第8回】田中 善積

天武天皇の治世下、『日本』の国号は定められた。日の昇る国家――その名には中国の冊封体制からの独立の意志が込められていた
-
歴史・地理『日本神話における「高天原」とは何か!?』【第9回】松浦 明博
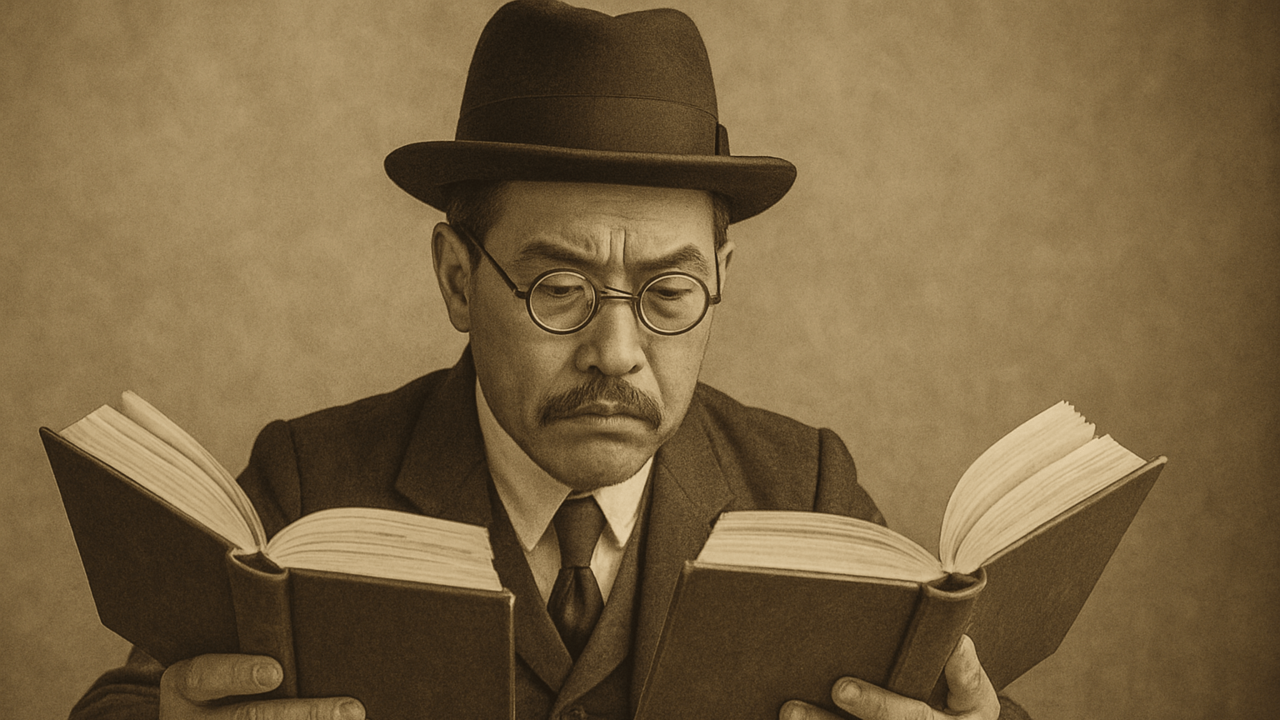
「長雨」は、「ながあめ」とも「ながめ」とも読む。「あ」が消える法則を辿ると、見えてくるのは......
-
小説『新事記』【新連載】吉開 輝隆

朝、痛みと共に目を覚ますと老人がいるではないか。老人は唐突に「われは、伊弉諾(いざなぎ)の尊(みこと)であるぞ」と大声で言いだし......







