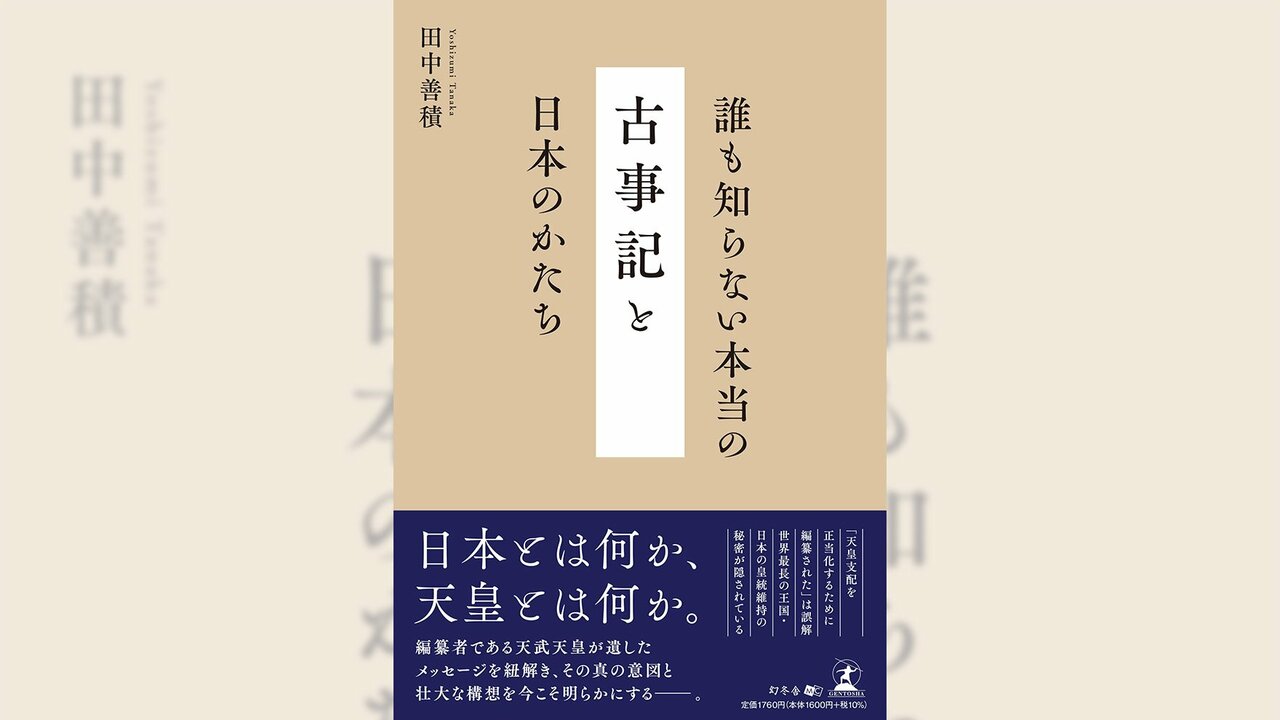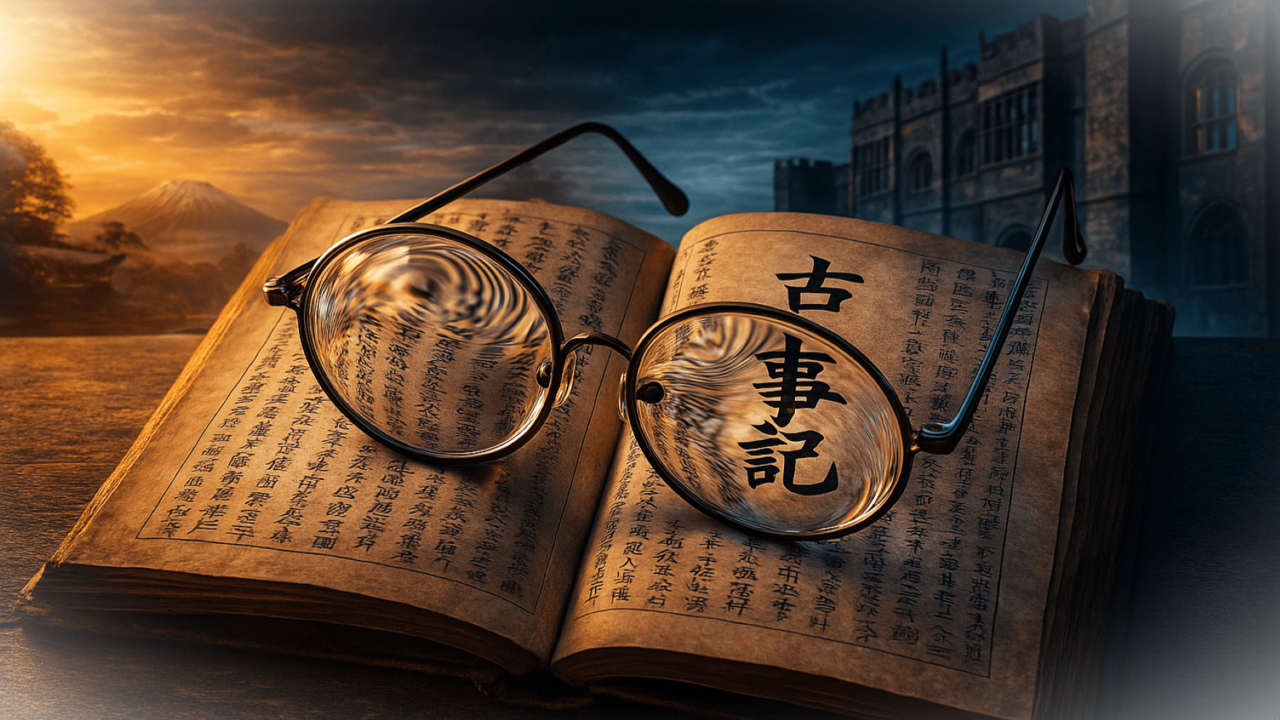【前回の記事を読む】どうすれば日本は安定的かつ永遠に存続するであろうか――そのカギとなるのは、国家の中心となるべき天皇のあり方であった
第一章 『古事記』の時代背景を探る
「権力トーナメント」の主宰者になる
このままだと、この血生臭いトーナメントが延々と続くことになる。これでは、大陸や半島の国と同じである。場合によっては、このヤマト政権も滅ぼされるかもしれない。
それを防ぐためには「権力トーナメント」の主宰者になり、その時代のトーナメント勝者をチャンピオンとして認定し、その者と主宰者が共同でこの国を治めるという方法があることを思い付く。
共同なので、時の権力者によって葬り去られることもない。そんなことをすれば、自分自身の権力を否定することになるからだ。先に挙げた五つのことが、守られる見通しがついたことになる。
そしてトーナメントは、その歴史が長くなれば成るほど、大会と主宰者の権威は高まることになり、民もトーナメントが発展する方向で応援・協力してくれるだろう。そうなれば、大会そのものを破壊するとか、主宰者を亡き者にするなどと考える人間は出てこなくなる。そして、主宰者であれば人格的に優れていなくても大丈夫である。こんなことを考えたのであるまいか。
作家の司馬遼太郎氏が天皇家は常に強い者に味方をするということを何かの本に書いていたが、まさに核心を突いた言葉である。強い者を引き入れるシステムを作ったのである。その究極の目的は戦乱なき世である。権力者との二人三脚の共同事業であれば、それは可能と考えたのである。
そしてその次に考えたのが、主宰者の“資格”である。「権力トーナメント」の主宰者が次から次に現れないようにしなければいけない。もしそうなれば、権力闘争の時代に戻ることになる。国内のトーナメントを一つに限定する必要がある。
そこで思い付いたのが、祭祀の権威者として君臨することであった。ただ、急に都合よく何かの宗教や教えが天から降ってくる訳ではない。どうすれば良いのか。無ければ、神様にまつわる物語を作り、神様と主宰者である皇室を繋げ、社殿もつくることにする。
ただ、建物はやがて朽ちてしまう。その建物と共に物語がなくなってしまえば、祭祀の権威者としての地位もなくなり、単なる普通の民となってしまう。それを避けるために、式年遷宮を思い付く。内宮と外宮を作り、二十年ごとに神殿を移す。建築技術も受け継がれるので、社殿は永久に建っているはず。内宮と外宮、二つを対にして考えるのは、陰陽の原理にも適っている。
人は現実社会を超越した存在に対して畏敬の念を持つものである。そして、現実の価値観に対して、見向きもしないような人間を尊敬する傾向がある。
確かに、世界の四大聖人と言われる人は、目先の価値観に見向きもしなかった。
現実の価値観を超えた存在として振る舞う、つまり権力欲を一切捨ててしまう、そしてなお且つ国の祖神のために祈り続ける存在であるならば、多くの人の気持ちは尊敬に変わり、民の心を結集し協力を得ることができるのではないか、それはちょうど台風の中心が何もないのに、周りからそこに向かって強い風が吹き込むようなものではないかと考えるようになったのである。
権威者としての天皇のあり方を陰陽など様々な原理の中で説きつつ皇統を定着させるための秘蔵書、『古事記』編纂のアイディアが天武の頭に浮かんだ瞬間だったのである。