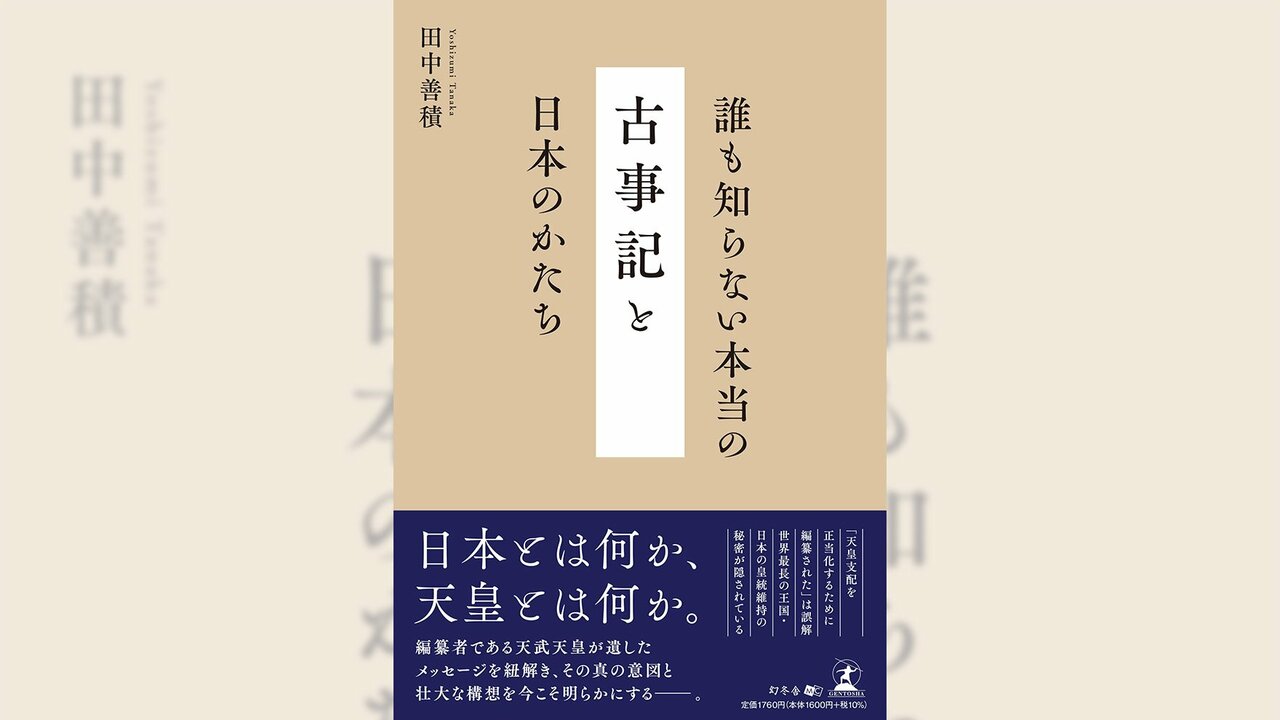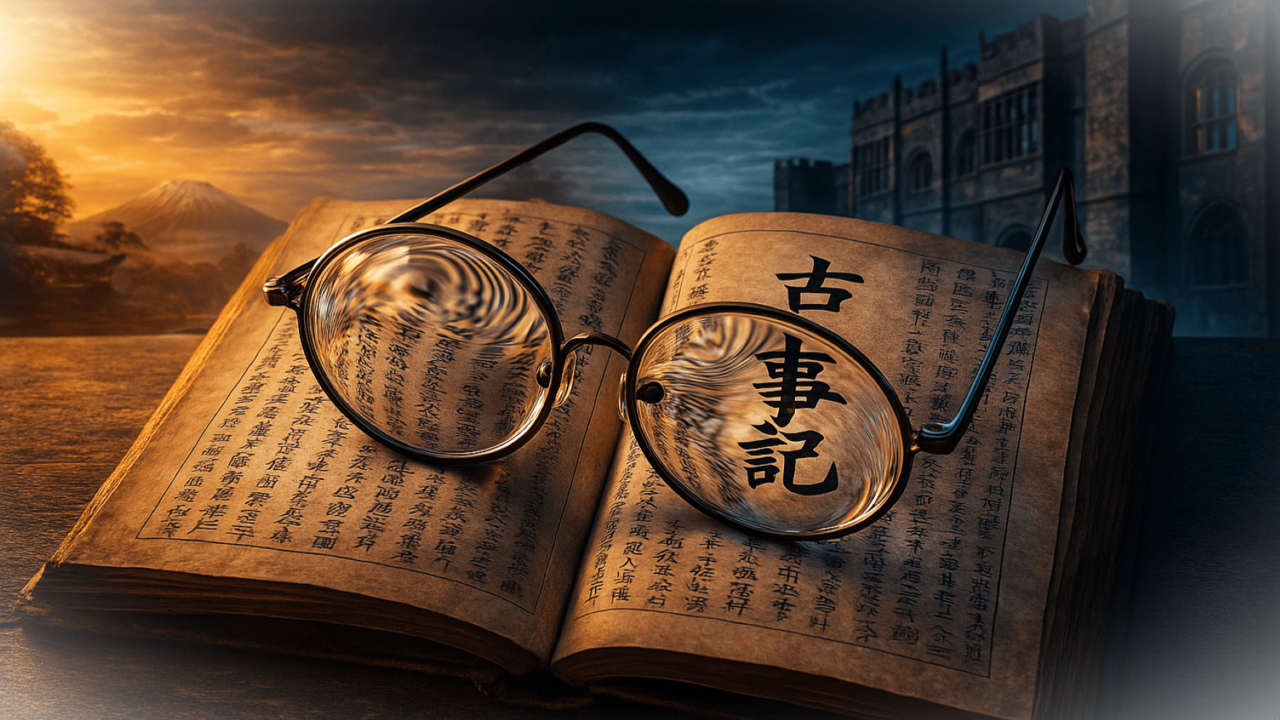【前回の記事を読む】天武天皇の治世下、『日本』の国号は定められた。日の昇る国家――その名には中国の冊封体制からの独立の意志が込められていた
第一章 『古事記』の時代背景を探る
天武天皇の深遠な問題意識
そして全国の民には仏壇を置いて仏像を拝むように命じている。日本は神仏習合の国であるが、その基礎固めを行ったのである。
家の中に仏壇と神棚の両方がある光景は外国の人には奇異に映るらしいが、近くの先祖に対して仏壇で祈り、遠くの先祖に対しては神棚で拝むということである。そして先祖はやがて神となって故郷の野山に還っていく。その祖先神を祀る神社を各地域に建てた。
警察も刑務所もない時代。とにかく、民が目に見えない大きな力を畏れ信じて生活することが、国家安泰の基本条件と考えたのである。
権力者ではない天皇を模索
天武は以上、五つのことに問題意識を持って国や民の生活に関する指針を定めたのであるが、この中に私的利益を追究したものは一つもない。すべて日本の国のことを考えての施策である。それが先に「深遠」と記した理由である。
天武が次に考えたことは、前項で示した五つのことが守られてさえいれば、日本は安定的かつ永遠に存続するであろうかということである。
大陸の様々な王朝の興亡の記録が、日本にもたらされていた。隋という大帝国が三十年足らずで滅亡し、唐が興る。親交があった百済は結局滅亡した。高句麗も滅亡した。新羅が半島を統一した。短期間でこれだけ多くの国家の興亡が間近で起きることは稀であろう。否が応でも、国家について考えさせられる状況だったと思われる。
なぜ、国は滅びるのか。大国でも滅びるということは、規模は関係ないということである。では、どのような原理がそこに働いているのだろうか。
日本もやがてはそのような運命を辿るのだろうか。中国の律令制度は有効に作用するのだろうか。中国に対抗できるような強い国にする必要があるのに、中国の制度を使うのは良くないのではないか、そもそも強い国とは一体何なのか。仮に、それが分かったとしても実行できるのか。どのような制度を導入すれは永続的な国となるのか。
そんな自問自答を繰り返す日々であったと思われる。