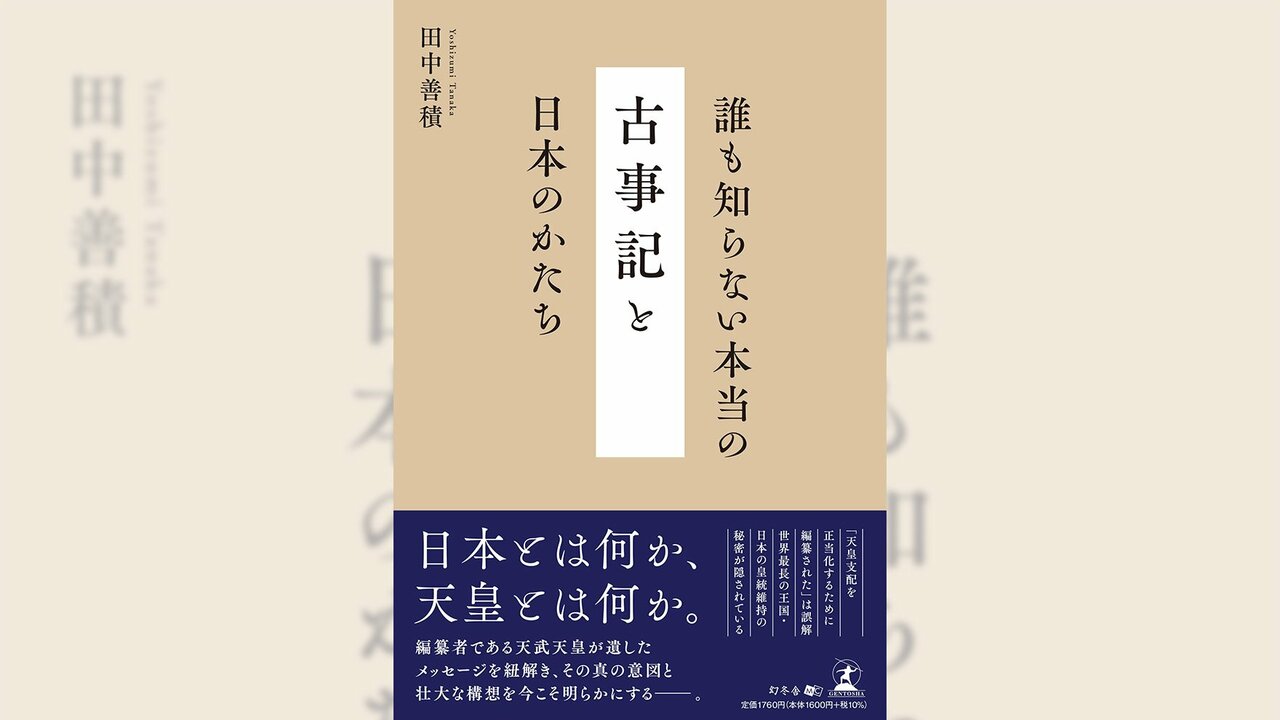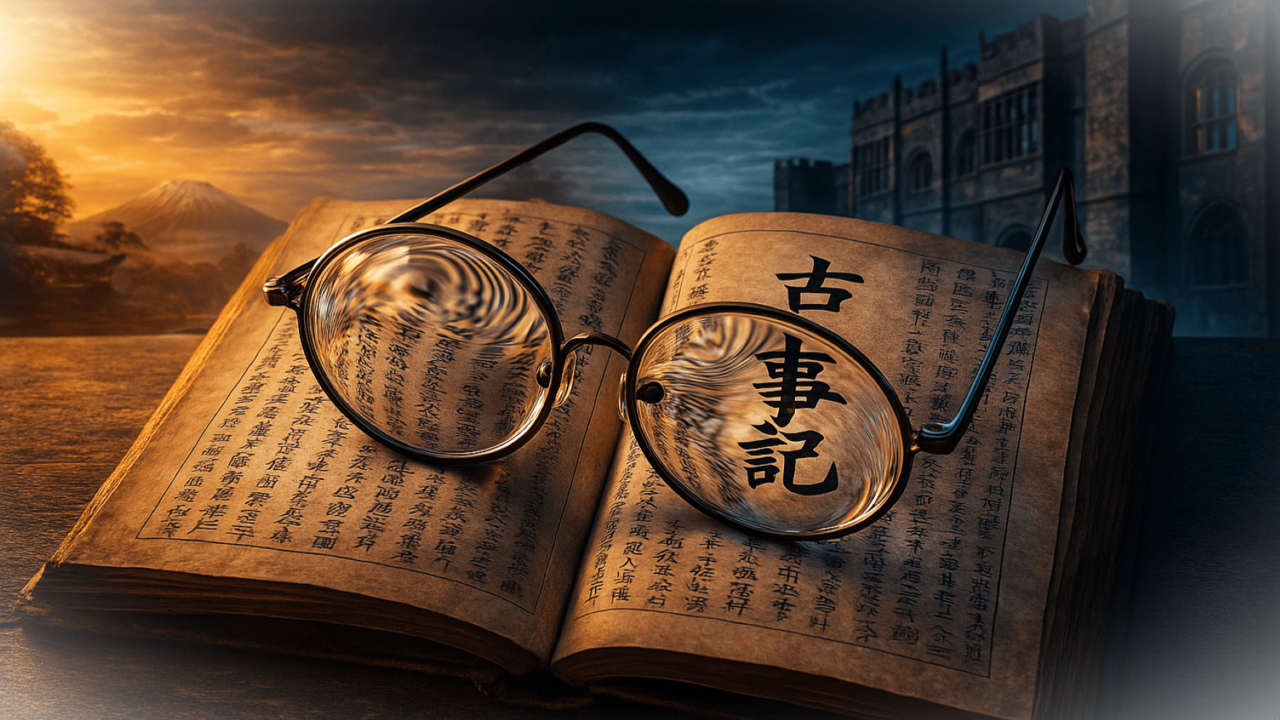【前回の記事を読む】「天皇には権力がなかった」――653年、孝徳天皇は中大兄による遷都に反対し、旧都に残った。この行動は…
第一章 『古事記』の時代背景を探る
天武天皇の深遠な問題意識
大友側についた中央の有力豪族は没落し、天皇に対抗する有力豪族がいなくなる。そんなこともあり、天武の「治世の十数年間、一人の大臣もおかず、皇族以外の豪族が重要な国政に参与した形跡はほとんどみられない」(吉田孝 前掲書)。
誰にも邪魔されることなく、思った通りの政策を実行することが出来たということであろう。そして、実はこういう時の政策を分析することによって、その人間のスケールや大局観のあるなしが分かる。
まず一番目は外交問題、特に中国との関係構築に努めた。中国の華夷体制に組み込まれないために、「『天皇』と並んで『日本』の国号も天武朝に定められた可能性が強い」(吉田孝『体系日本の歴史③』小学館、一九九二年)。
従来の大王(おおきみ)であれば、中国の冊封体制に入ることを意味する。単なる名称変更ではなく、そこには独立した国家として、独自の考え方でこれからは歩んでいくという考えが込められている。
『日本書紀』の中に史実を編年体で書き込み、歴代天皇の事績を正式な漢文で書き記すことによって、中国に国名と共に日本という国を理解してもらおうと考えたのである。
『旧唐書』の中に、「倭国伝」と「日本伝」の二項目がある。少なくとも唐が国名を認めたことが分かる。
戦火を交えたが、六八〇年頃には外交関係は修復に向かって動き始め、対等な関係による遣唐使船の派遣が八世紀から行われるようになる。天武は中国に対して、天皇と日本の名称を『日本書紀』によってアピールしようと考えたのである。
二番目は、律令制の導入である。飛鳥浄御原令は「わが国で初の体系的な成文法典」(『日本生活文化史 2』河出書房新社、一九八〇年)として評価されている。
令は現代で言えば、行政法、組織法を意味する。『古事記』に書き込んだ原理は、制度や組織を通して現実社会の中に反映されていく。原理・理念と制度は二つで一セットと考える必要がある。
そんなことから、天武は令の中身に問題意識を持ったのである。具体的には、「太政官 神祇官」の二官体制の中で、権限を太政官の大臣に委ねつつ、権威者として君臨するポジションを取ったのである。そして、かたちだけ唐の律令制度にならったが、そこには新羅対策の意味があった。それについては、後述する。