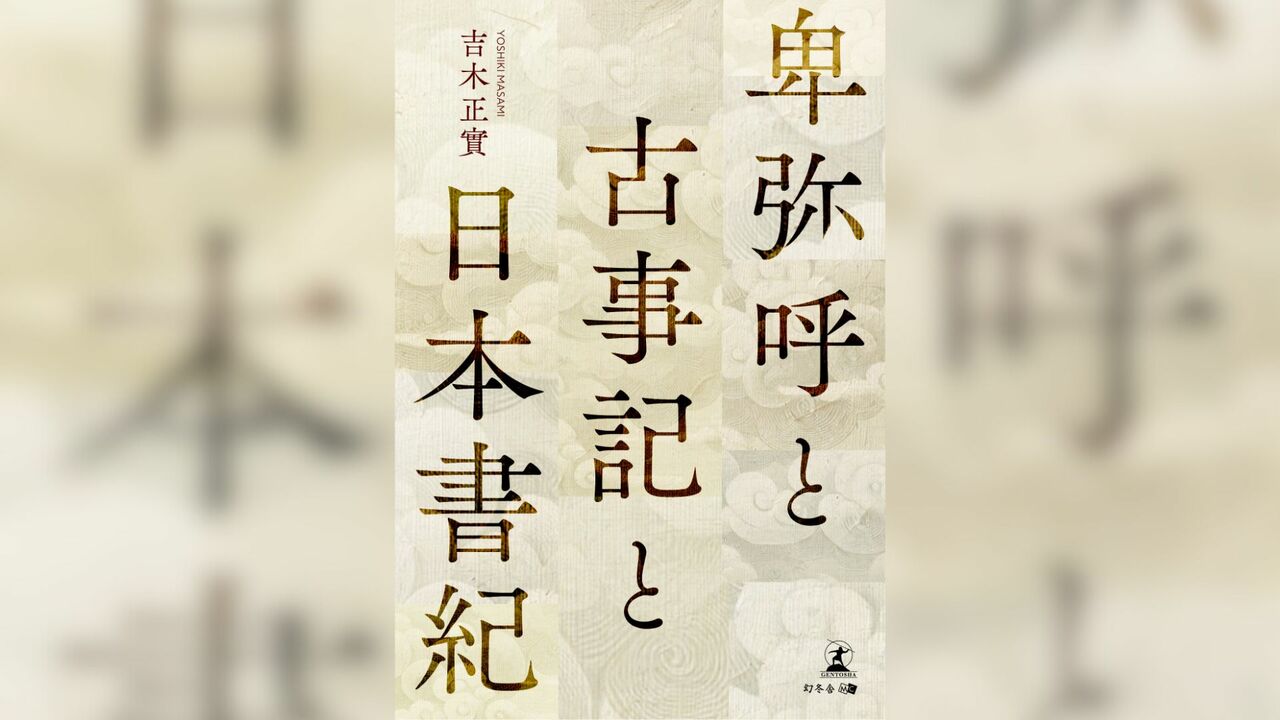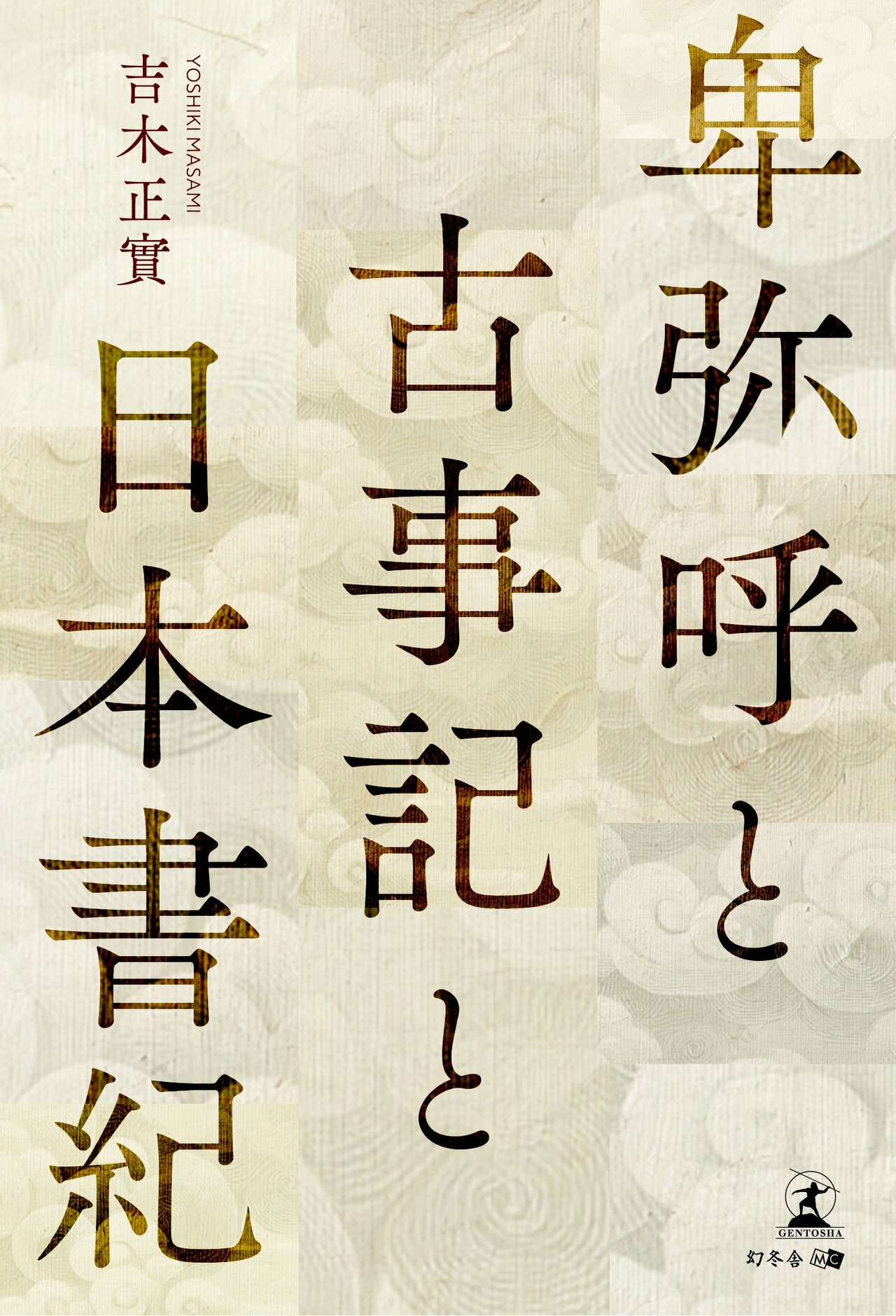【前回の記事を読む】歴史書に存在しない女王・卑弥呼。当然、その存在は何らかの形で記されているだろうと思うが...
はじめに 偽装の『古事記』とからくりの『日本書紀』
「古事記神話」で枷をはめられた『日本書紀』
そして『日本書紀』である。
『日本書紀』も『古事記』と同様に発案は天武天皇だと言われる。『古事記』が漢文体を基調としながらも、漢字の音訓を利用した日本語を併用しているのに対して、『日本書紀』はすべて漢文体である。そして干支を用いて年次を明確にしながら、その時々の出来事を詳細に記録している。
『古事記』が国内向けの天皇家の物語だとするならば、『日本書紀』は中国の歴代王朝を意識した我が国の歴史書としての体裁を強くもっているわけである。
だが残念なことにこの歴史書としての『日本書紀』には、少なからぬ疑惑が付き纏っている。それは『日本書紀』もまた、『古事記』同様に、「正實に違い、多く虚偽を加」えている可能性が否定できないからである。そしてそれは前述した「古事記神話」によって、枷をはめられた結果ではないかと推測されるのだ。
例えば『日本書紀』「神代紀」は、「天地が初めて判れたときに生じた神」について多くの神の名を紹介しているが、「高天原とそこに生まれた神の名」について記述しているのは一書(第四)だけなのである。ところが天照大神(アマテラスオオミカミ)が誕生し高天原に送られた後には、その後の天上界の記事は高天原世界一色に染まってくるのである。
またアマテラスオオミカミの神名である。同じく「神代紀」第五段では、「伊奘諾尊(いざなきのみこと)・伊奘冉尊(いざなみのみこと)、共(とも)に議(はか)りて曰(のたま)はく、」として「是(ここ)に、共に日の神(かみ)を生みまつります。大日孁貴(おほひるめのむち)と号(まう)す。」と記している。
ところがその直後に分注で、「一書に云はく、天照大神(あまてらすおほみかみ)といふ。一書に云はく、天照大日孁尊(あまてらすおほひるめのみこと)といふ。」と追記しているのである。
なぜなのであろうか。高天原主体、アマテラスオオミカミ中心の『古事記』「高天原神話」と比較すれば、明らかに印象の異なるこれらの記述は一体どこからきたものであろうか…。