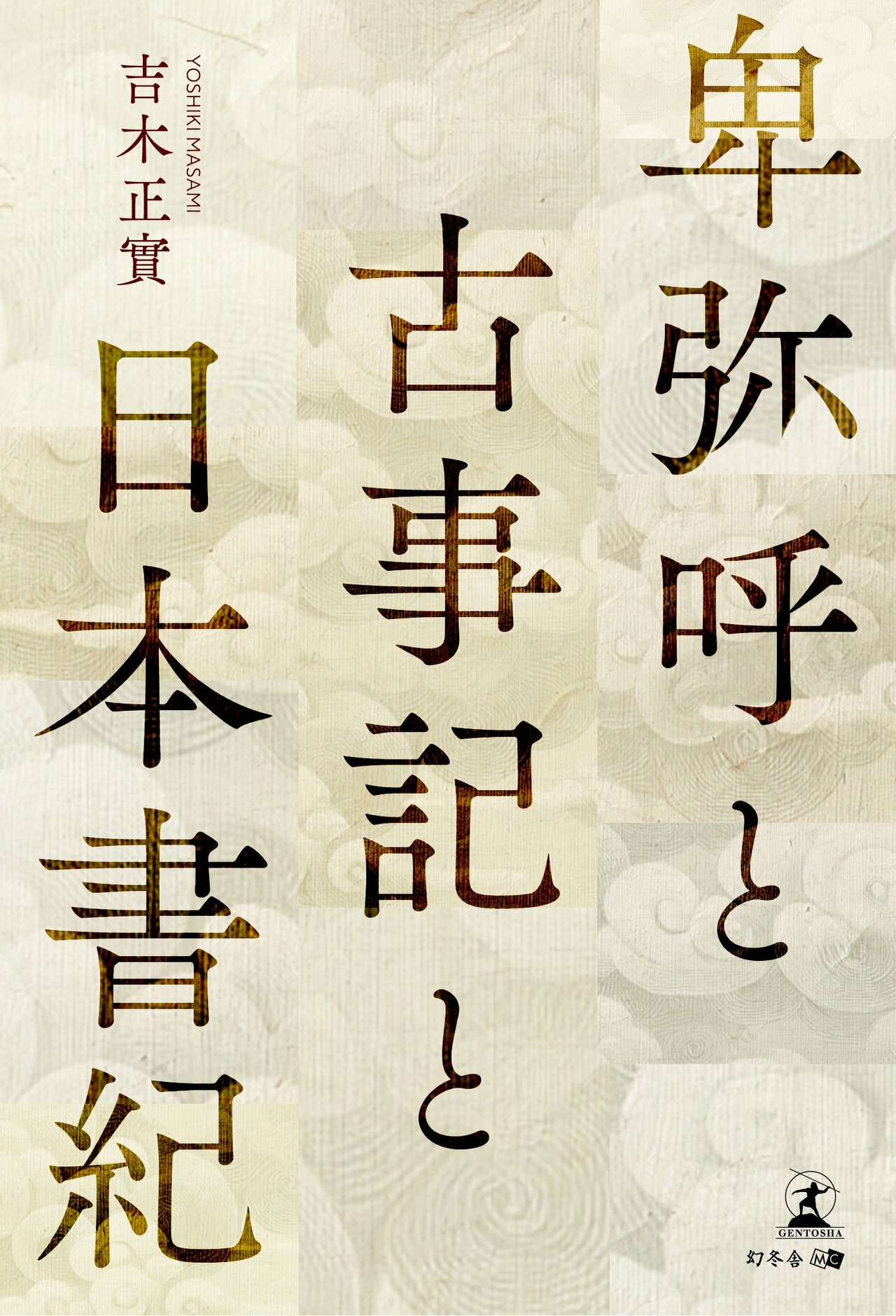からくりの『日本書紀』
こうして『古事記』と『日本書紀』は、自らのその骨格の中に一連の神話を取り込んできた。今日「記紀神話」と呼ばれているものがそれである。天武天皇の目的は、『古事記』・『日本書紀』の成立によって、その死後にようやく達成されたわけである。泉下の天武天皇もほくそ笑んだに違いない。
しかし『古事記』はまだしも、『日本書紀』の編纂に携わった者たちは、その編纂作業の過程で、ある重苦しい問題と向き合ったはずである。
その問題とは、一つは権力による歴史改ざんの圧力であり、今一つはその圧力に対して編纂者としてどう向き合うのかという自らの内面における葛藤である。編纂者たちは両立することのないこれらの問題の狭間で悩み続けてきたのではないか。そしてそれは歴史書の体裁を持つ『日本書紀』において、より深刻であったに違いない。
本来、歴史を編纂するということは、史実に対して忠実を貫く覚悟がなくては為し得ない作業である。一つの事例(『司馬遷・史記1・覇者の条件』「解題」市川宏+杉本達夫[訳]徳間文庫)を紹介してみよう。
斉(せい)の大夫崔杼(さいちょ)が、君主の荘(そう)公を殺し、その弟の景(けい)公を立てて大臣となった。すると斉の太史が「崔杼、その君を弑(しい)す」と記録した。崔杼が激怒してこれを殺すと、その弟が太史の職をつぎ、同じことを記録してまた殺された。だが、もうひとりの弟が、三度同じことを記すに及んで、さすがの崔杼も記録の抹殺を断念した。
この間、地方にいた他の史官は、太史がつぎつぎに殺されたと聞くや、記録板を携えて国都に駆けつけ、記録が守られたことを知ってはじめて帰ったのであった。(『左伝』)
太史(史官)たちは命懸けで史実を記録したわけである。
【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…
【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった