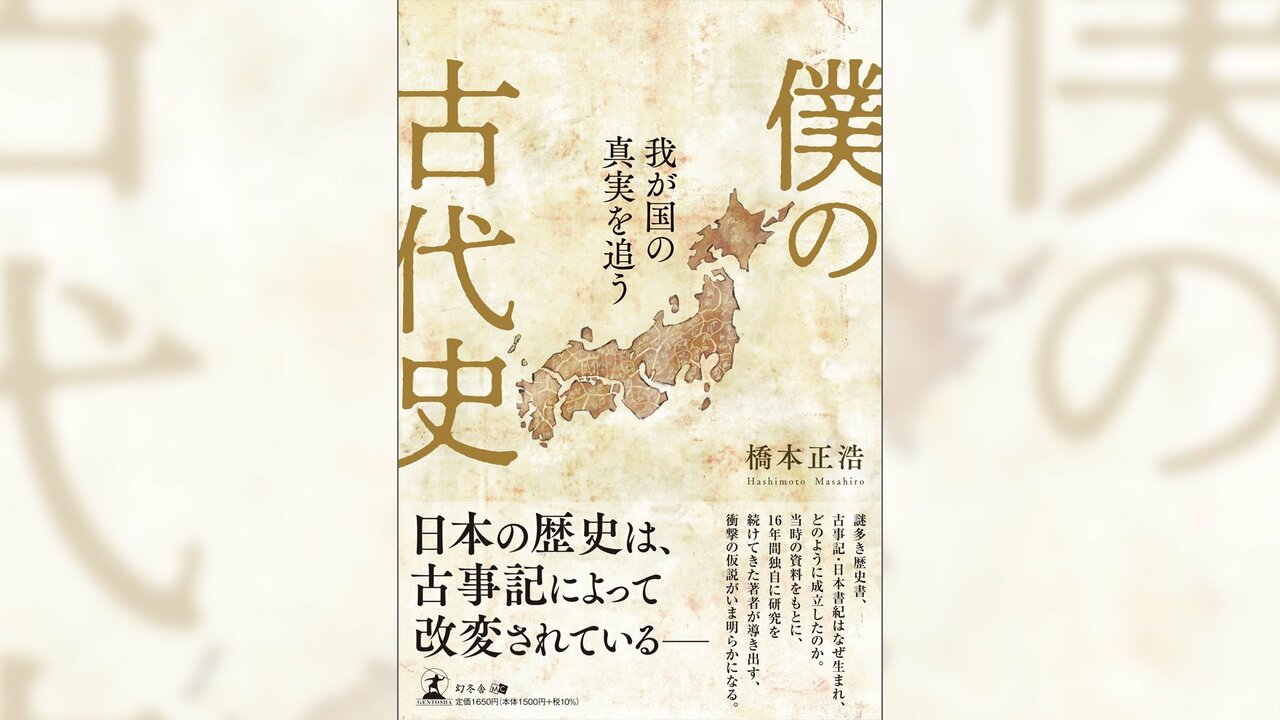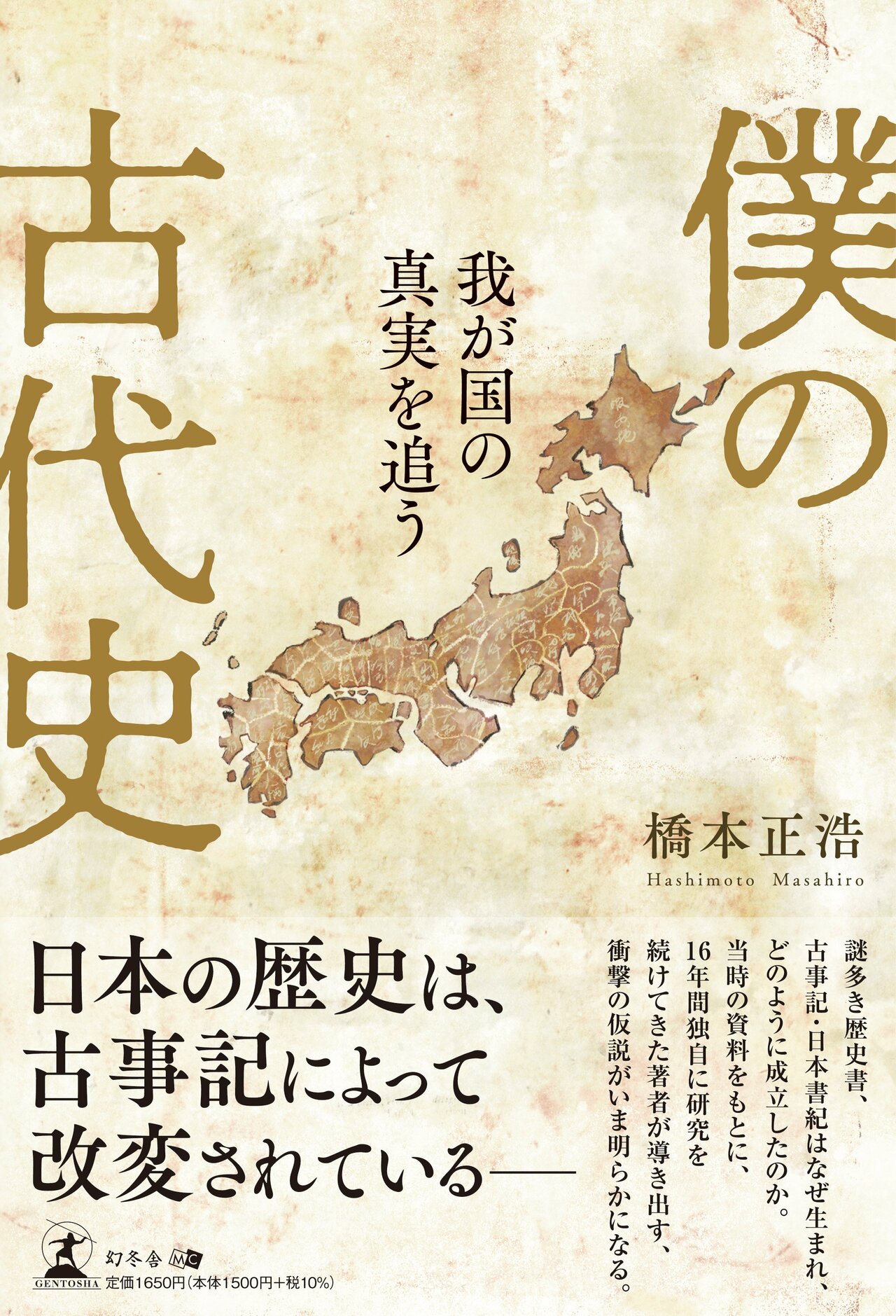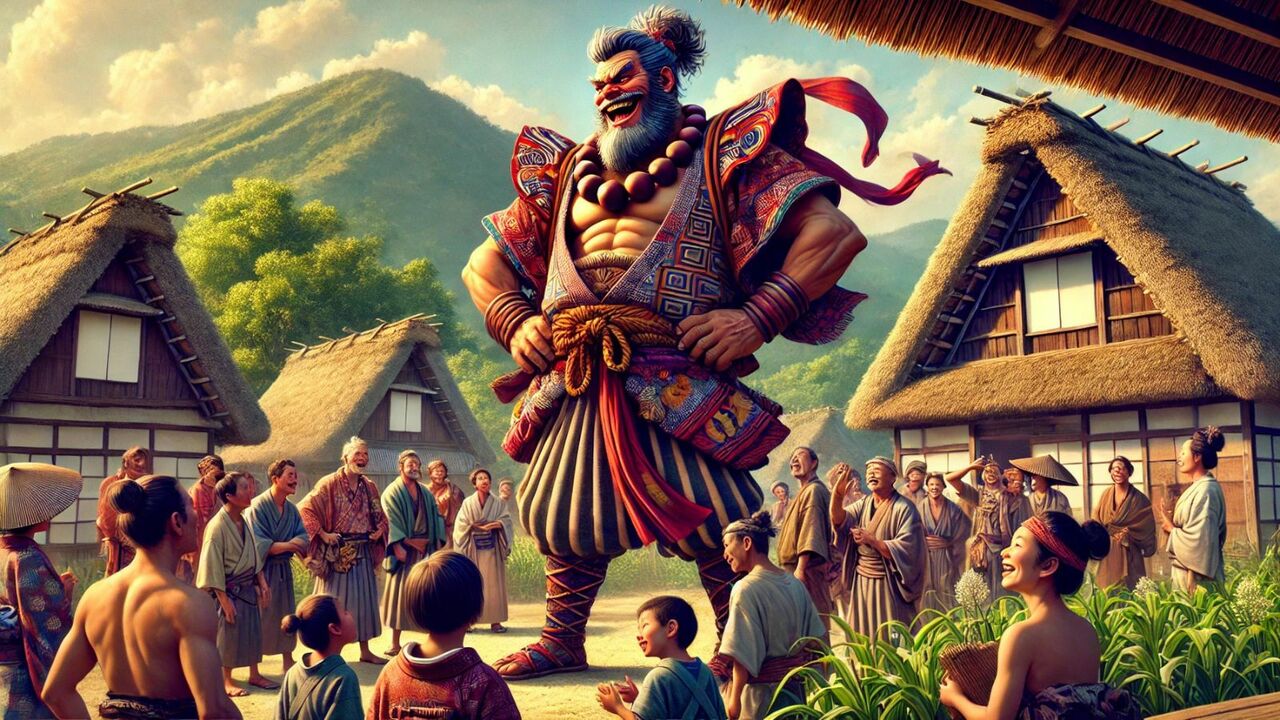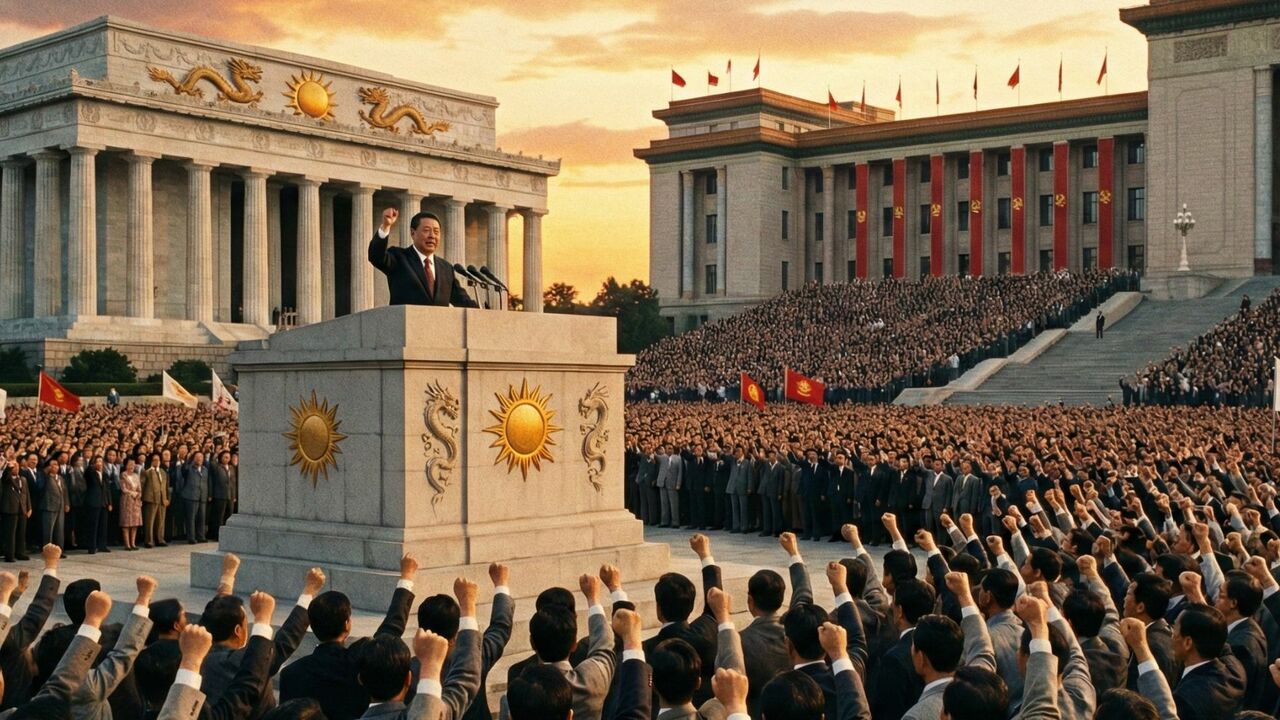【前回の記事を読む】「日出ずる処の国の天子が書を日没する処の天子に致す......」鮮卑族の王朝に対して、変わらぬ姿勢で対等交流。
第一章 地方分権国家としての隆盛
六.前方後円墳を考える 前方後円墳の築造について
前方後円墳という特異な形の墳墓はどのようにして生まれたのでしょうか。AD4~6世紀にかけての古墳時代といわれる、前方後円墳という特異な古墳の時代は、この「倭国」と自称した「倭の五王」の時代と見事に重なっているのです。
私は従来から、古墳の中でも特に、世界にあまり例のない「前方後円墳」に興味を感じていました。
そんな中で、二〇一九年に大山古墳が世界遺産に登録されたというニュースを聞き、改めて前方後円墳に対する関心が高まり、我が国の古代史に照らして、純粋に古代遺跡として自慢できるものなのかどうかという、疑う気持ちを持ち始めました。
それは森浩一氏が、江戸時代から明治・大正にかけて、多くの古墳が「整備」の名の下に「改築」されていた、とその著書(『巨大古墳』・講談社学術文庫)で述べているのを知ったからです。
世界遺産に登録されてしまった大山古墳を含む、我が国の前方後円墳の実情を暴くことには、いささか気が引ける面もありますが、「真実の追究」の結果としてご容赦ください。
今回ネット上に情報のある全国約6377基以上の墳丘を持つ古墳の中から前方後円墳を中心に約1500基の古墳情報を整理してみた結果(そのうち前方後円墳は1189基)、
近畿を含め全国の巨大古墳(森浩一氏が言う墳長160m以上)は、竪穴による埋葬で、墳丘そのものを造るための築成によらない、自然丘陵を利用している可能性が大きいことが確認できたのです。
即ち、それほど多くの人力によらなくても巨大古墳が作れたということです。本になる丘陵が大きければ巨大古墳になり、小さい丘を選べば小さな古墳になるということです。それはとりもなおさず、巨大古墳だからといって、それを大王(天皇)の古墳と見ることはできないということを示唆しています。
このことは、東京古田会会員の平松幸一氏の情報から、かつて、地質学者梅田甲子郎氏が「応神天皇陵付近の地質と地形について(書陵部)」で主張されていたことを知っておりましたが、私はその「埋葬施設(前方後円墳)の造り方」の考察を通して同じ結論を得ました。
大きな丘陵を選んだ場合、確かに整形に要する版築などは人手と時間はかかりますが巨大古墳を一から土を盛って造り出すことに比べれば比較にならないほど簡単であったと思われるからです。