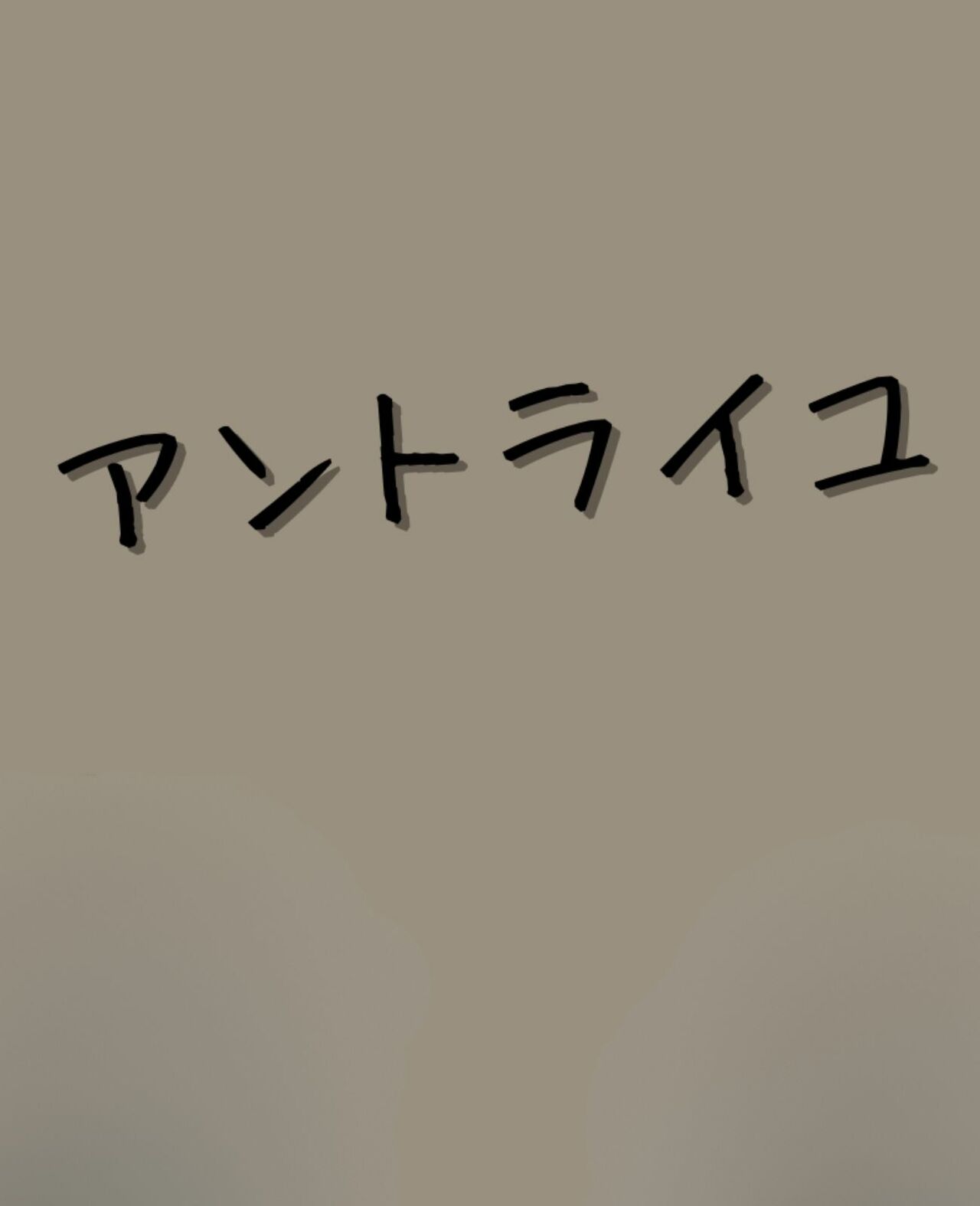【前回の記事を読む】彼にピアスが増えたら、私は自分の耳にも印をつけて、ニードルを取り出す…「痛い痛い!」それでも彼とお揃いがよかった
アントライユ
1
私たちは新潟県の外れにある小さな町で育った。
私は、ボロボロのアパートで生まれた。母親の稼ぎが少なく、泣く泣く住んでいた。幼少期に千春がそのアパートの隣の部屋に引っ越してきたのだ。千春の母親の後ろに隠れる彼の光る涙は私の心を潤した。今でも鮮明に思い出せる。
彼の目は女の子のようにパッチリしていて、よく同級生の男の子から揶揄われていた。彼は気弱な性格であったから、抵抗できずよく泣き寝入りしていた。母親に慰められている姿を嫌という程見た。私も何度も千春に絡んで頭を撫でた。その時は、同情していたからだと思う。
千春の母親というと、彼のことを心から愛していた。息子の事を宝のように愛でる母親の鏡だった。それは確かだった。
一方、私の母親はいつも私を怒鳴ったり家の外に放置したりした。凍ってしまいそうな寒い冬の夜に家から投げ出されるのは地獄だ。そうすると、千春の母親がいつも彼女らの部屋に入れてくれて、温かいご飯を分けてくれた。冷たい体にじわりと涙が滲んで凍った心が解けていくのを覚えている。
千春も、私の事を抱きしめてくれた。彼らの温情はどんなに優秀なエアコンよりも、ストーブよりも温かいものだった。
千春の父親は、救いようの無い最低な人間だった。千春と彼の母親をゴミのように扱った。いや、ゴミだって肥料になる。多分、それ以下にしか見ていなかった。服の裾から垣間見えた母親の腕には、アザがあった。
私は何も出来なかった。殴られている所を目撃したことがあるが、怖くて足がすくんで、動けなかった。今私が彼と居るのは、そんな罪悪感を、機嫌を取ることで払拭したいからなのだろう。決して、浮ついたことなど言えない。
私の父親は私が生まれた後、亡くなった。だから、記憶が無い。母親も父親の事は話さないから、私の中で消えつつある存在だった。
そんな環境が十二歳になってもまだ続いた。周りは全員私たちの事を白い目でみるばかりで、助ける、なんて思考は全く無かったのだろう。どんなにアザを作ろうが、体調を崩そうが、誰も手を差し伸べてはくれなかった。