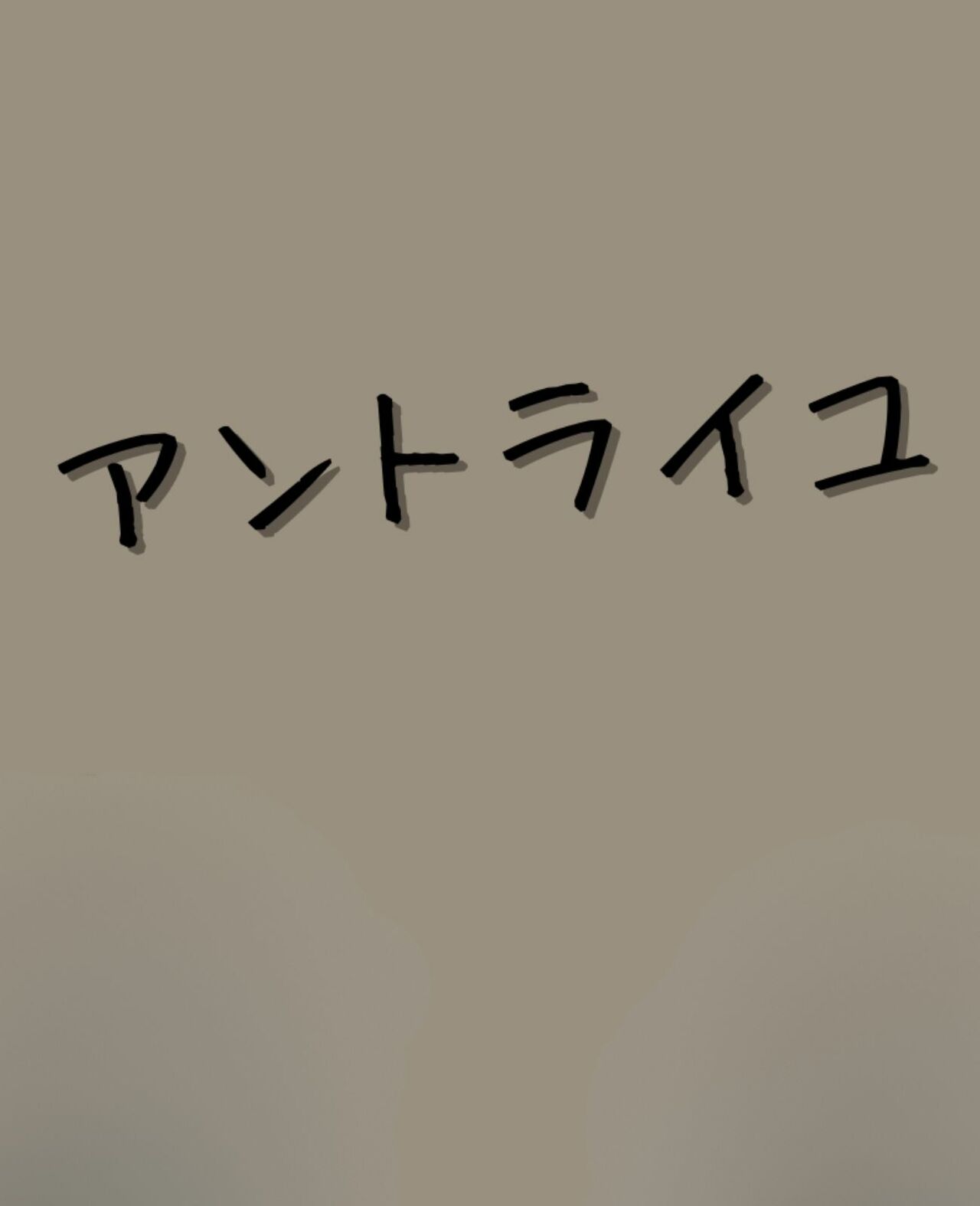【前回の記事を読む】たしか、彼が冷たくなったのは四年くらい前から――都合の良いセフレだと思っているのだろうか…
アントライユ
1
恋は盲目と言うけれど、実際は恋をしている側の欲目に過ぎないのかもしれない。愛及屋烏(あいきゅうおくう)とは言っても、嫌いなものは嫌いなままだろう。こんな可愛げの無い脳みそになったのは、きっと目の前の男のせいである。
一方、彼も愛だの恋だの言うタイプではない。彼が恋愛を語った時は、神様がひっくり返って爆笑するだろう。
そんな私たちは家賃六万の小さなアパートに身を置いている。もちろん一人暮らし用。狭いけど、意外と住み心地が良くて契約し続けている。今、この小さな空間では張り詰めた空気が私たちを支配していた。
「千春、ピアス開けたとこ見せて」
千春は黙って髪を掻き上げた。以前はなかったホールが増えている。自分の耳を触って場所を確認する。
「ここに開けたんだ。印付けて」
千春は舌打ちをして私の髪を雑に耳にかけた。そして机に放置されたアイライナーで、私の耳に穴を開けやすいように印をつける。終わると、またスマホで猫の動画を流した。猫が好きという点は、数少ない共通点だ。
「ありがと。ニードル使って良い?」
私たちはニードルで開けている。皮膚科でも開けてもらえると言ったのだが金が勿体無いと言って、千春は安いニードルをネットで注文した。
千春は何も感じないって言うけど、明らかに感覚がおかしい。ツボが密集している場所に穴を開けるのだから少なくとも不思議な感覚がある筈。それ以上に痛みが勝つのが至極当然だ。実際、私は悶えるほど痛かった。
わざわざ痛い思いをしてでも彼とお揃いがいい。そんな私らしい理由に後押しされて、決心した。
「一気に刺す。一気に刺す」
何度か復唱した後、素早くニードルを耳の骨に沈める。無駄に力が入って体が小刻みに震える。
「痛い痛い痛いー!」
「すげぇ顔」
千春は私の顔を見て引いていた。
「ヤダ。見ないで」
ニードルが貫通したら、ピアスと入れ替えるだけ。この作業が難しい。十四ゲージ、たった一・六ミリの隙間なんて、気を抜けば塞がってしまう。本当に緊張するのはここからだ。