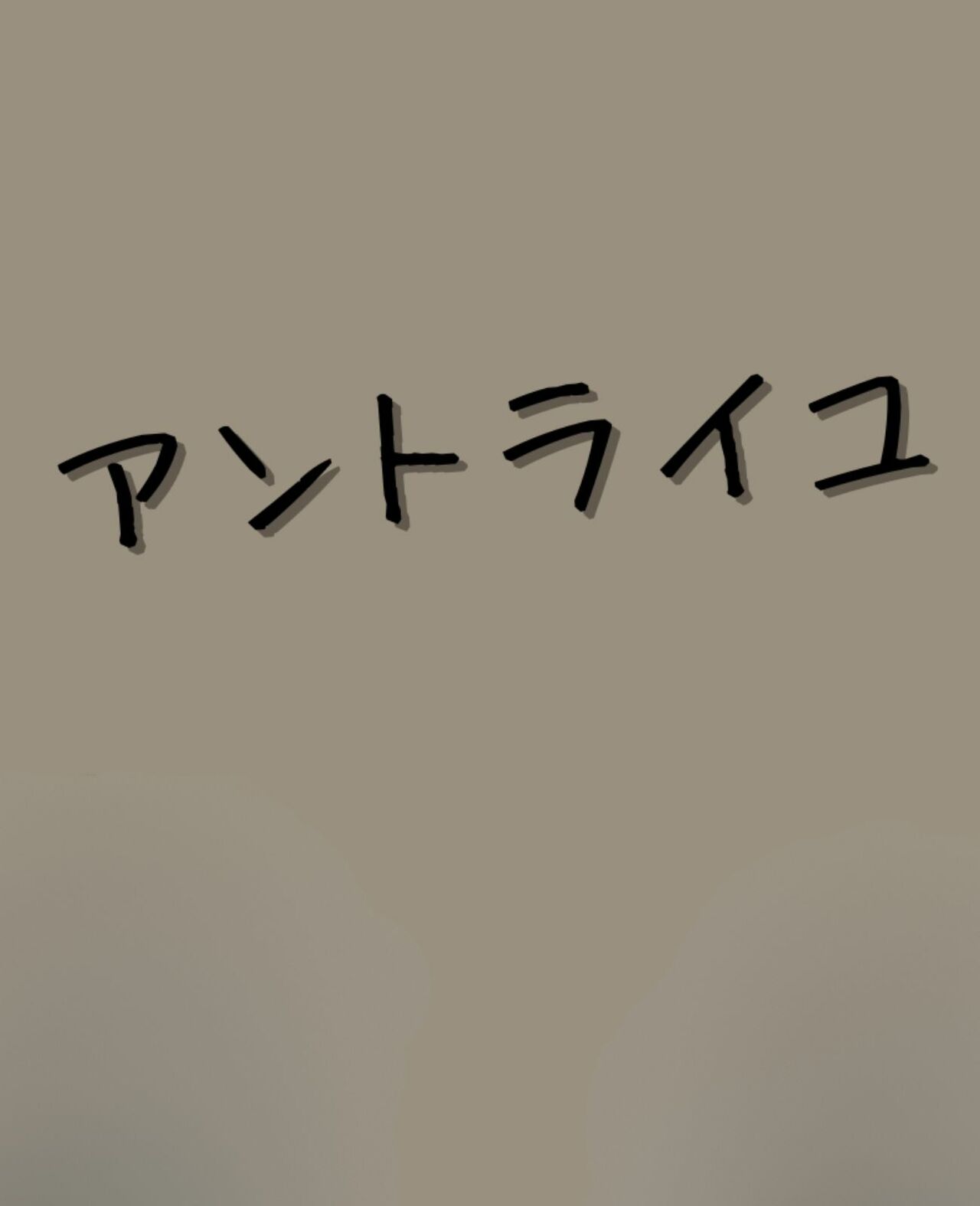千春に助言して貰いながら何とか接続に成功すると、力が一気に抜ける。鏡で見ると綺麗に開いていて、大満足だった。千春に追いつけたという達成感も同時に味わえた。
「軟膏ある?」
「そこの棚の右側」
千春が指差した棚を開けようと手を伸ばした。
「そっちじゃない」と、私の手を強く掴む。私が開けようとしていたのは、彼が絶対に開けるなと口酸っぱく言っていた方だった。私は『開かずの棚』と呼んでいる。
「ごめんなさい」
すぐ謝ったのだが、彼の逆鱗に触れたらしい。じっと睨み据えてベッドに腰掛けた。私はその形相に何も言えず縮こまった。これが最近の私たち。
「てかさ、何か香水くさいんだけど」
後藤さんだ。今日いつも以上に距離が近かったから。
「ごめん。バイトの先輩だと思う」
「風呂入ってきて」
千春の鋭い目を見た私は黙って脱衣所に向かった。