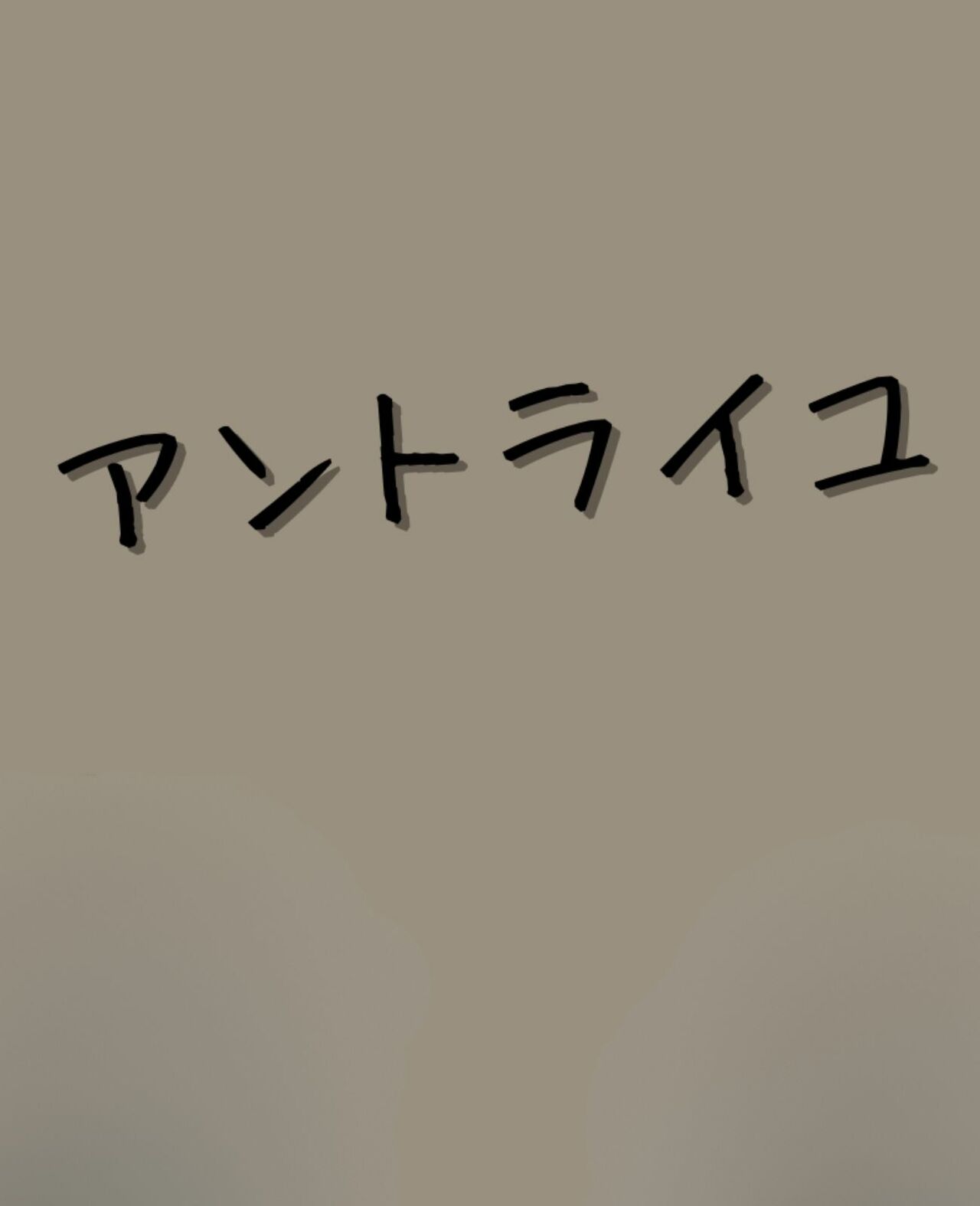アントライユ
1
アラームが鳴る前に目が覚めた。二人で寝ているベッドはどうしても冷たくて、思わず身が震える。
隣で寝ている千春は相変わらず背中を向けている。起こさないように、するりとベッドから抜け出す。
激安スーパーで手に入れた卵をフライパンの上に丁寧に二つ落とす。熱に晒された白身はパチパチと怒っている。
「千春みたい」
そう呟くと、彼が寝室から出てきた。男にしては少し長い襟足。彼の細くて青白い首を隠すように垂れている。ブリーチをして傷んだ毛先が跳ねていて可愛い。最近染めてないから、黒い部分が伸びてきている。彼はそこを雑に掻き毟り、冷蔵庫から水を出して飲み干した。
「今日は朝ご飯いる?」
「いらない」
即答されたが、今日は機嫌が良い。目が合う。その目は鋭く突いて私を刺激する。
千春はいつもご飯を食べない。本人は腹が空かないと言うのだが、中枢がやられてしまっているのだろうか。私の心配を尻目にスマホを弄りだす。
ソーセージをフライパンに滑らせ、水を少し入れた後、蓋を閉める。髪に染み込んだ油っぽい匂いに、換気扇を回さなかった事を後悔する。
「パン焼くけど?」
「⋯⋯食べる」
私は焼いた食パンと卵とソーセージを平皿に乗せ、ローテーブルに置く。我ながら上手く焼けたと思う。
千春はスマホから目を離し、食事の邪魔にならない様に髪を結ぶ。いつもは見えない頸にドキドキしてしまうということは、死んでも言えない。
「いった」
千春が耳を抑えた。ピアスが髪に引っかかったのだろう。私のメイク用の鏡を雑に掴んで覗き込む。
「また開けたの? 私にも開けて」
「やだ」
私は千春と同じところにピアスが開いている。正確には私が一方的に真似をしている。ロブが五個、ヘリックスが三個、ロックが一個、トラガスが一個。両耳合わせて十個。そして、新たにアンテナが一個。全部で十一個。
「じゃあ自分で開ける」
必死に追いつこうとする私の姿は千春からしたら滑稽に見えているのだろう。気持ち悪いって思っているかも。でも、一緒が良い。
「もう行くね」