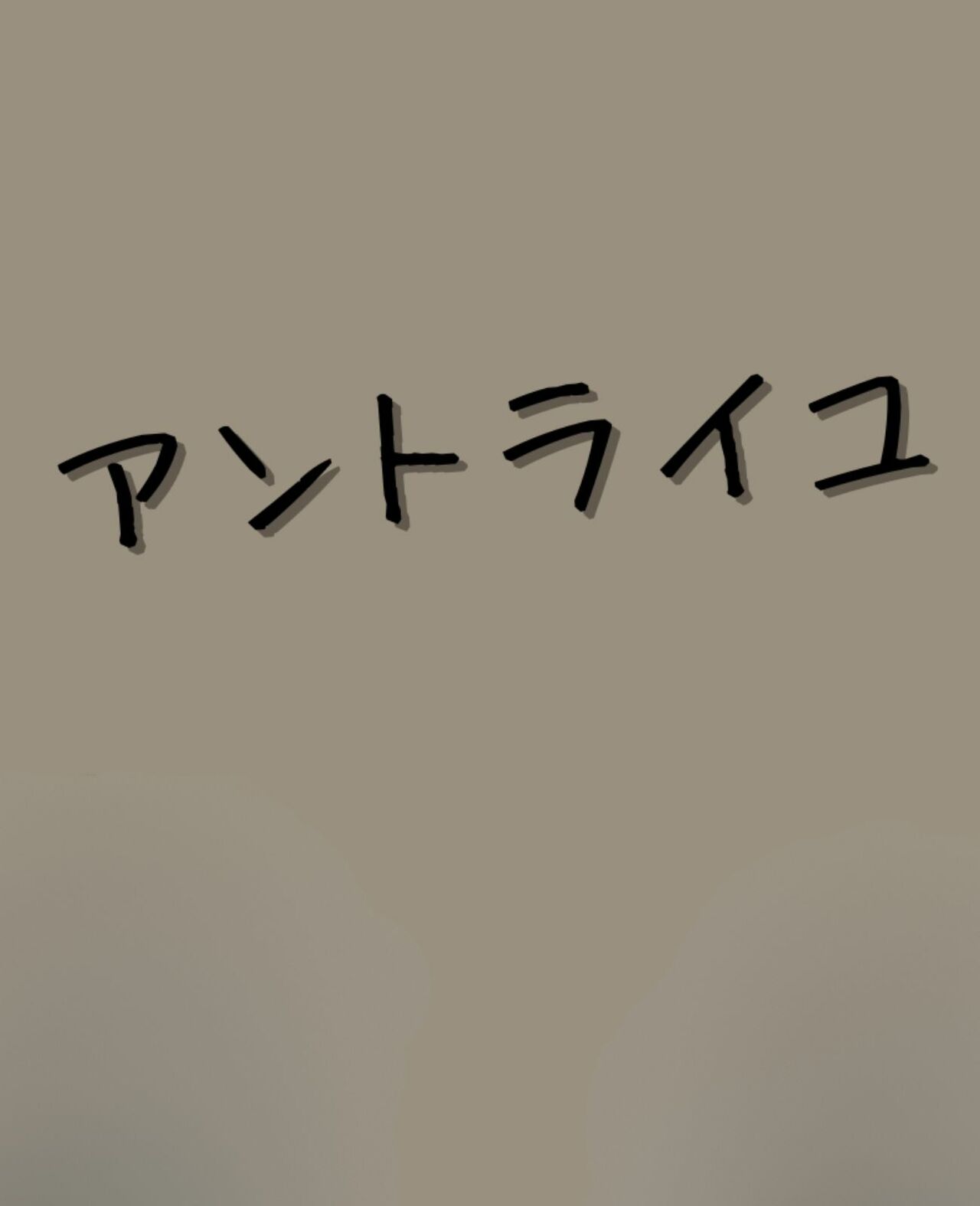はっきり言おう。この人の事が嫌いだ。
「話聞こうか?」
テンプレートの様な甘言すら苦く感じる。
「大丈夫です」
適当にあしらうと、後藤さんは何故か笑った。それを尻目に揚げたホットスナックをショーケースに並べた。
「どんな人なの? 同居人」
私は言葉に詰まった。千春のことを他人に説明したことが無いから。
「簡単に言うと、仏頂面で文句言ってくる人ですかね」
「え、なにそれ。モラハラじゃん」
改めて言われるとそうなのかもしれない。それが当たり前の時点で私たちの関係は可笑しいのだろう。でも、私は千春から離れられない。私には彼しか居ないから。
千春は私との関係をどう思っているのだろう。例えば、恋人だと思っていたとして、大切に思っていたとしたらあんな態度はとらない筈。やはり都合の良いセフレだと思っているのだろうか。そうすると一緒に住む理由が消滅してしまう。たしか、千春が冷たくなったのは四年くらい前。高校を卒業して二人で家を出た頃。特に何も無かったと思うけれど。私がムカつくことしかしないからかもしれない。
「おーい。雫ちゃん?」
後藤さんが私の視界に入り込んでいた。私は意識を体に戻し、揚げすぎたと思われる唐揚げを慌ててステンレストレーに移した。
後藤さんは私の肩を抱きながらケラケラ笑う。不快感に襲われたが、男の力に勝てる筈もなく、泣く泣く諦めた。
バイトが終わるまで、あと五時間。
次回更新は8月15日(金)、20時の予定です。
【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…
【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった