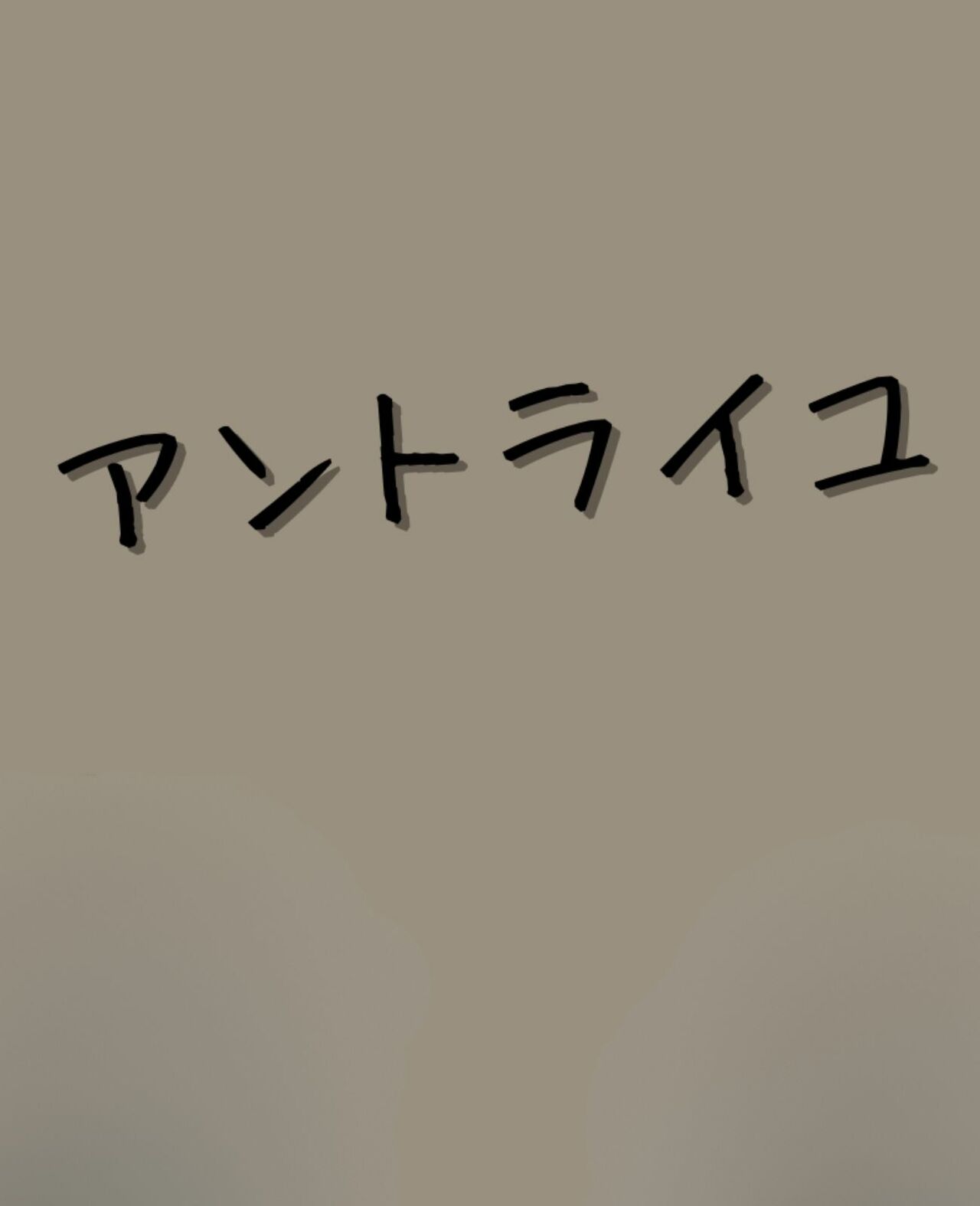雪国に居た私たちからしたら、東京の冬なんて甘ったるい。この前手に入れたオシャレだが極端に薄手の服を纏って鞄を拾う。ホルターネックのキャミソールの上にニットが合わさったトップス。所々にリボンがあしらわれていて、お気に入りだ。生活が苦しい中、労働のご褒美として買ったのだ。
「それでいくのかよ」
「だめ?」
「別に」
千春の鋭い視線は私の全身を刺した後、手元のスマホに戻った。肩と足を出しているのが気に食わないのだろう。私は黙ってジャージに着替えた。千春の態度は慣れている筈なのに、最近妙に刺さる。着慣れたジャージは冷えきっている私の心身を温めてくれるようだった。
バイト先は何処にでもあるコンビニ。店長もバイト仲間も全員優しい。何か企んでいるのではないかと疑ってしまう程だ。でも私からしたら酷く居心地が悪い。人の優しさなんて、疾うに忘れてしまった。
「雫ちゃん、お疲れ様」
「お疲れ様です」
私の肩を叩いたのは年が二つ上、二十六歳の後藤さん。私たちと違って大学を卒業している上に、家も裕福なのだとか。最近このコンビニに勤務することになった。気にかけてくれるのは大変ありがたいけど、かなりしつこい。
「元気ないね。何か悩んでる?」
「そうですか?」
最近の悩み。強いて言うなら千春が全然食事を摂らないこと。
「もしかして彼氏のこととか?」
「いえ。同居人です」
後藤さんは目を細めて「そう」と呟いた。