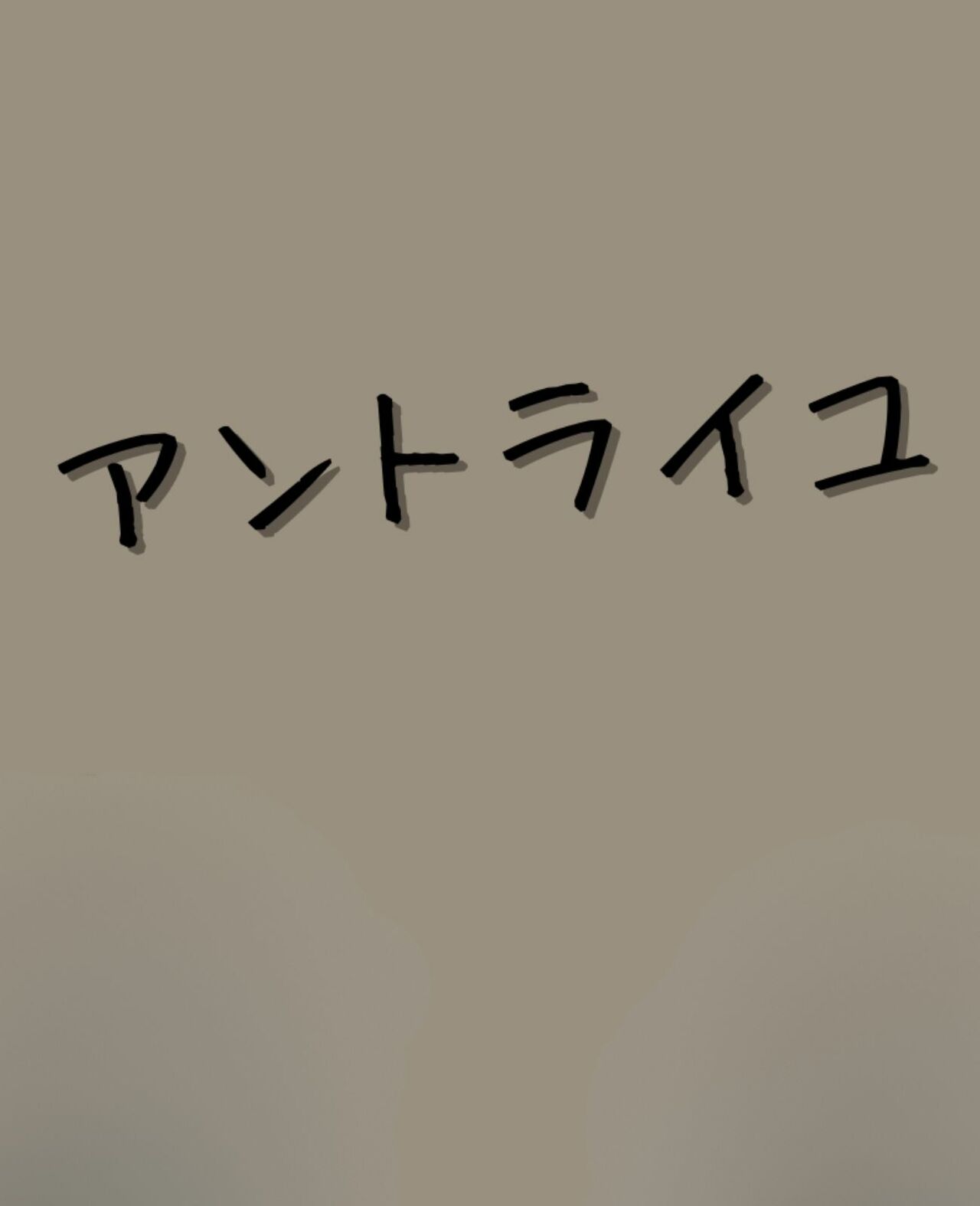【前回の記事を読む】私達の親が死んだ。二人の葬式は酷いものだった。帰り道嬉しくて咽び泣いているかのような雨にずぶ濡れの私と彼は…
アントライユ
5
「あー。またやっちゃった」
嫌な予想は的中して、もっと早く対策すれば良かったと後悔するのが毎月のお決まりになっている。
生理は重い方ではないが、気分の波に乗るのがどうしても苦手だ。アホなりに色々マイナスな事を考えてしまって、良くないと分かっていながら辞められない。この苦くて渋い思考を焼くための正解はどこにあるのか。
途端に、体の中に鉛を流したかの様に四肢重くなり、棒を宿した様に固まる。決して鮮やかとは言えない、形容しがたい色の血が勢いよく流れていく。流れが収まるのを待ち、便座の蓋を閉める。
千春はベッドに仰向けになり、天井をぼうっと見つめていた。手に握られたスマホからは微妙な音量で音楽が漏れている。
「ねぇ」
反応がない。
「ねぇ、千春」
「何?」
「そっち行っていい?」
「好きにすれば」
私はベッドに上がり、膝を抱えて座った。ベッドが軋んで一部が沈んでいる筈なのに、微動だにせず口を開けっぱなしの千春は間抜けな顔をしている。無理やり彼の視界に割って入った。
「してもいい? キス」
千春は目を見開いたが、黙って頷いた。千春の唇は薄くて、柔らかさは少なかったけど暖かい。彼は私の唇を素直に受け入れた。心も身体も満たされていくのを噛み締めて受け止める。
千春は私の両腕を強く掴んだ。視界が反転し、私は押し倒される形のまま彼を見つめた。彼の瞳は揺らいだ。親に恵まれず私と一緒に生きてきて、きっと幸せとは程遠いと呆れている。でもその瞳はまだ、理不尽で醜悪なこの世に未練があるように潤いながら光っている。
私を掴む腕は、私と変わらない程細かった。力も、私が全力で抵抗すれば勝てそうな程弱い。ゆっくりと視線を彼の体に動かす。こんなに広い世界の中、こんなにも小さな体(うつわ)の中で死が渦巻いていると思うと、心臓がチクチク痛む。
中から黒くて心地の悪い何かが溢れ出そうになって、全身の感覚が薄れていく。自分の重みを取り戻したくて、彼の首に腕を回した。彼は嫌そうな顔をしながらも私の腕を剥がそうとはしなかった。