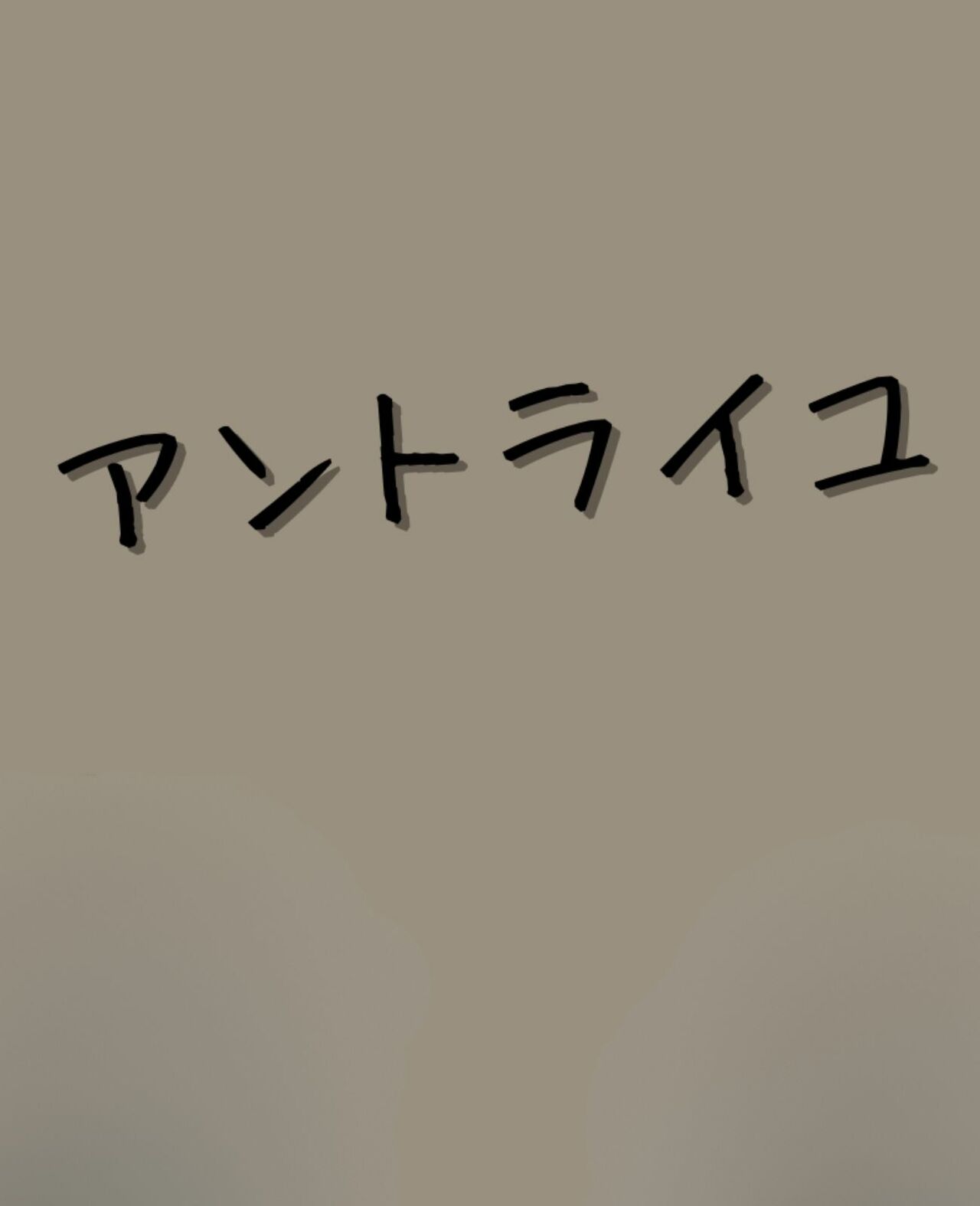看護師は若い女性だった。眉を下げて、千春を見る。
「一度だけお母様がお見えになったのですけど、何も言わずに帰ってしまって」
千春の母親が来たのだ。家を出て行ってから十年以上経っている筈。親子関係は切れているけど、きっと連絡が入ったのだろう。千春はどう思ったのか。それは、近くに居た筈の私が想像しても何も得られない、彼だけの感情だ。
初夏の暑さには有難い冷たい風が吹く、木陰のベンチに座った。千春は私を見ようとせず、呆然と一点を見つめた。
「猫、見に行きたいね」
ゆらゆら揺れる葉は千春を撫でているようだった。
「そう言えば、また本読み始めたんだ。最近のオススメはね、これ。好きな作家さんだから、買っちゃった」
くたびれたトートバッグから、下ろし立ての綺麗な本を取り出す。自慢しようと思って本を顔に近づける。図書館から借りることが多いから、新品の匂いは慣れなくて、眉を顰めてしまった。
「千春?」
千春は黙ったままだった。彼の目を見ると、長くて綺麗だった睫毛は一本もない。私は目を瞑った。
「疲れたよね、もう部屋戻ろっか」
立ち上がった私の服の裾を掴んだ。弱々しく、固く。千春が潤いのない唇で渇いた声を発した。
「帰ったら、俺の棚の中、見て」
か細く、闇に消え入りそうな声。開けるなと強く言っていたあの棚。
「わかった。絶対見る。その代わり、絶対治して」
千春は私に向かって笑って見せた。
私は悟った。
もしかして、もう――
次回更新は8月24日(日)、20時の予定です。
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...