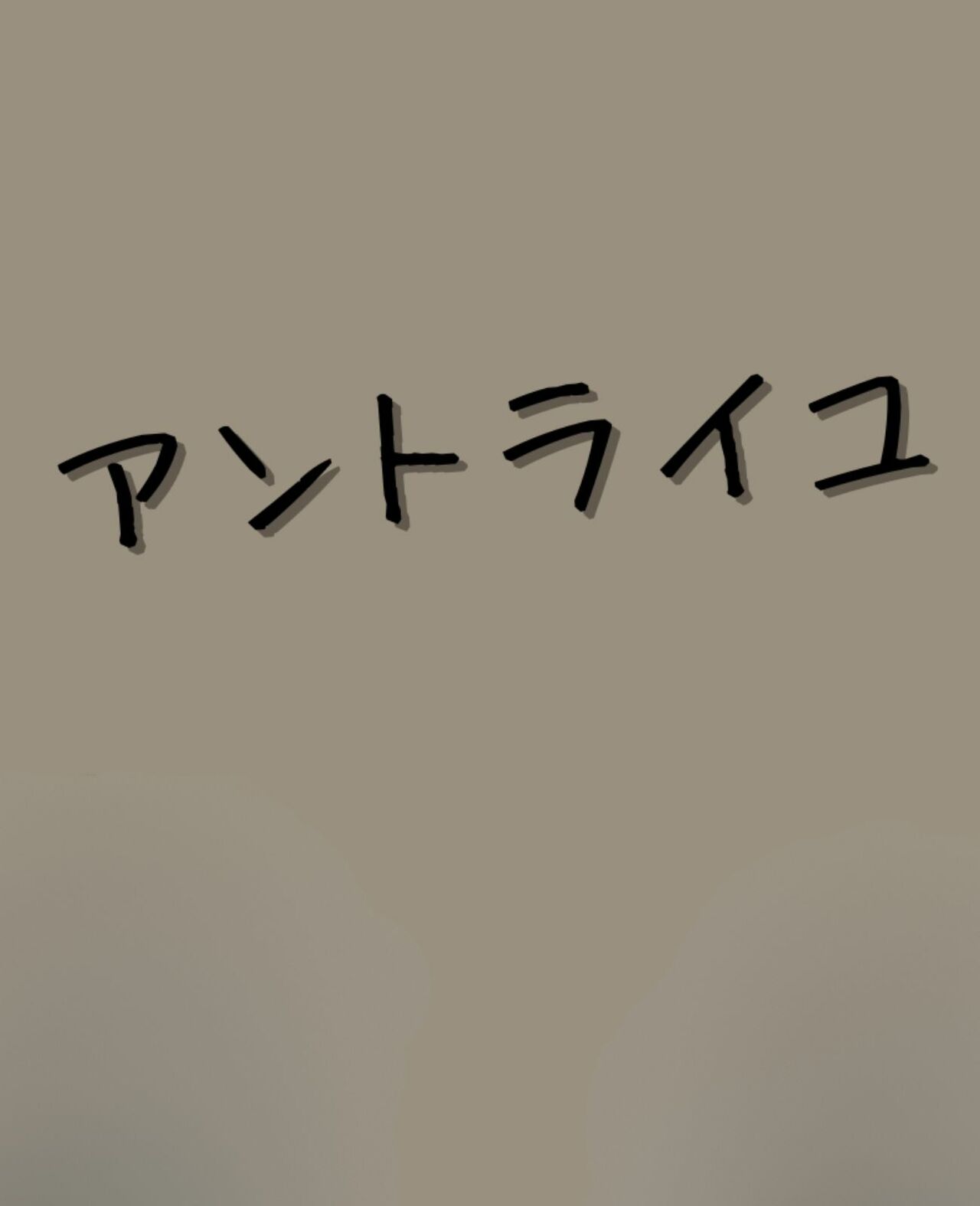「暑い」
「ちょっとこのままが良い」
観念した千春と横に寝転ぶと、彼は私の髪を弄りだした。少し機嫌が良い時にする、可愛い癖。
私は彼の胸に顔を埋めた。
「ねぇ、千春。猫飼いたい」
「良いよ。飼おう」
「青目の子、探そう。白い毛の青い目の子がいい」
「うん」
「今度ペットショップ行こう」
「うん」
千春の素直さに懐かしさと嬉しさが沸き立ってどうにかなってしまいそうだった。
「昔さ、私よく抱きついてたよね。あの時の千春、顔赤くして恥ずかしそうにしてた」
「めっちゃ鬱陶しかった」
流石、千春。思わず多弁になっていた私を黙らせるのが上手い。
「嘘」
千春はそう言って私の髪を指で軽く梳かし、口付けをする。沈黙が憚る部屋の中では、いつも通り千春が優勢で。頭の中も心臓も今は黙ってくれなくて、大きく視界を揺らす。血が沸くような高揚感に身を任せる。
私を真っ直ぐ見つめる千春の目は、死を恐れているものではなかった。
6
全国的に異常な暑さが観測された五月の中旬。私たちには関係ないゴールデンウィークはあっという間に過ぎ去って、世間はもう夏に向かって走っていた。
千春の限界は、疾うに越えていた。
「千春!」
周りの音が消えた。
千春の瞳は虚ろで、頬がこけている。変わり果てたその姿は目を背けたくなる程だ。でも、紛れもなく千春だ。
拙い簡易車椅子で押される彼は、俯いて、私を見ようとしなかった。尿が通る管と溜める袋が車椅子から出ている。そこには赤い液体が詰まっていた。私の心が崩れる音がした。