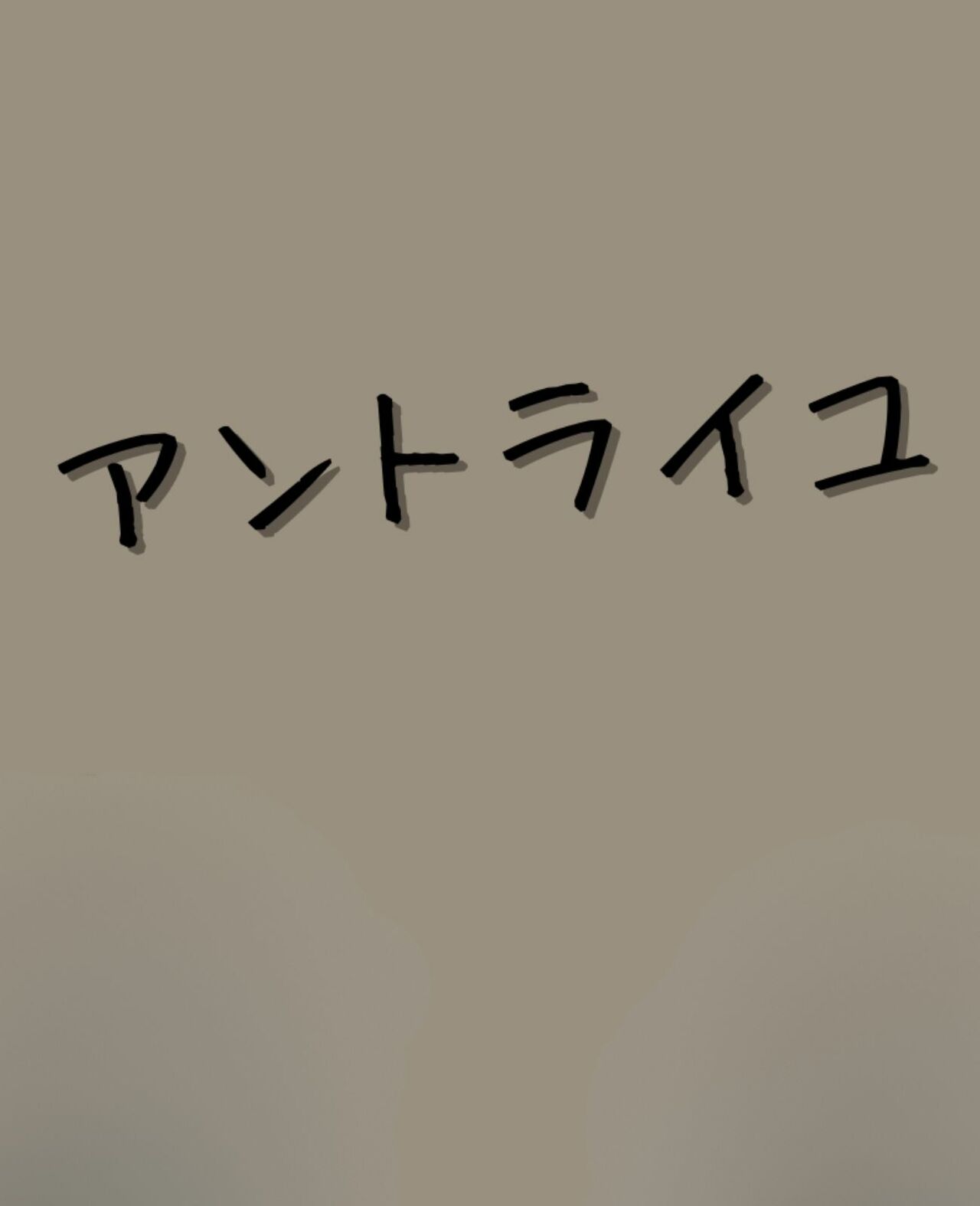突如、千春は何も言わず、私の太ももを強く掴んだ。痛みを感じる前に、千春の心の内を察した。これが合図。何に興奮したのかは全く分からないが、いつもの通りに身を委ねることにした。
キスなんてしない。キスをすると脳が刺激されて痛みが和らぐ、なんて聞いたことがあるけど、私の中では眉唾物同然だ。痛いと感じることはしない所は、彼の悪人になりきれない優しさが滲み出ていると思う。
私は自分でブラウスのリボンを解いた。目を逸らしたくなる程貧相な体。自分の体を目にすると偶に思い出す、千春の父親のこと。ゆっくり撫で上げられる気持ち悪い手つき。その感触が忘れられない。熱さは全く喉元を過ぎず、今も閊えている。私の体は、急に言うことを聞かなくなった。
「何」
「ごめん、思い出しちゃって」
千春は頭を掻きながら深く溜息を吐いた。
「あっそ」
「すぐ忘れるから待って」
私は必死に頭を空っぽにしようとした。でも人間とは不自由なもので、忘れようとすればする程、濃い霧のように纏わりつく。冷や汗が止まらず、瞬きも忘れてしまった。もたもたと服をたくし上げる。
「あー、俺も思い出してきた。もう良いわ」
千春はスウェットを拾って、袖を通した。そして雑にロンTを掴み、私に投げた。
「飯食いに行く。来んの?」
「行く」
私は慌てて服を纏い、髪を整えた。アパートの鍵を握り締めて転びそうになりながら駆け出す。
色違いのサンダルを履く私たちは、他人からはどう見えているのだろうか。
次回更新は8月17日(日)、20時の予定です。
【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…
【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった