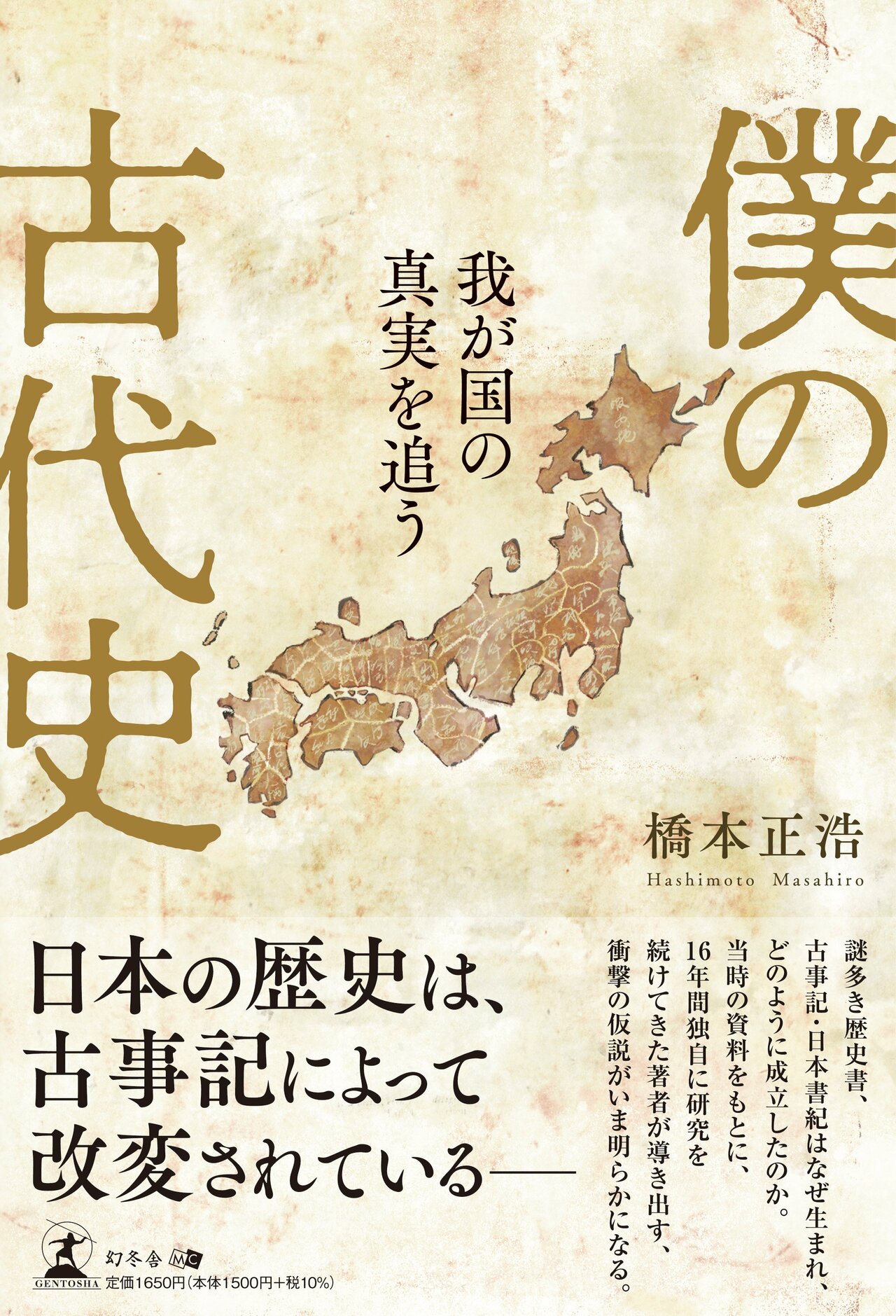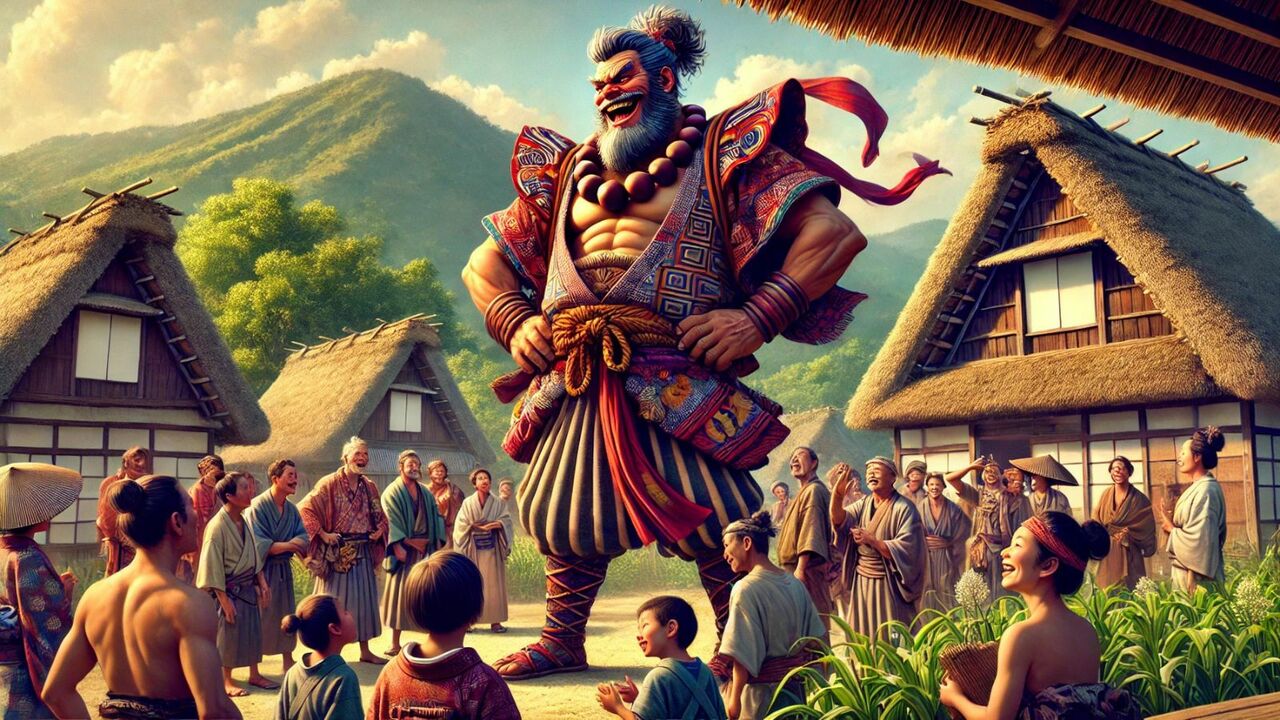埋葬形式の違いにより築造方式が異なる
さて、前方後円墳などの墳丘を持つお墓の「埋葬の形」は大きく分けて「墳頂」に埋葬する「竪穴」タイプと、羨道を設けて埋葬する「横穴式石室」タイプに二分されます。
通常、「竪穴」の場合、墳頂を平らにして、四角い穴を掘り開けて棺を安置しますが、AD5~6世紀頃から横穴式石室風のものを墳頂近くに造る場合があります。竪穴式石室に斜めに羨道と入り口を付けたものです(これを初期の、或いは九州系の横穴式石室とも言います)。
一方、「横穴式石室」タイプの主流は、墳丘の築成過程で羨道並びに玄室を造り、その上に墳丘を造っていくもので、古墳全体を、土を盛って造っていきます。即ち、竪穴式の場合は先ず墳丘を築成して、その墳頂に棺等を埋めていきます。
一方、横穴式石室の場合は横穴式石室を造りながら同時に墳丘全体を築成していくのです。その造り方は全く異なっているのです。
竪穴式であるということは、自然丘陵を利用したと思われる場合、先ず、墳頂を円形に平らにし、その後、墳頂の円形に添って順次周りの斜面を円形に斜めに削りとって
整形(中には葺き石を埋め込んだりしています)しながら何段かテラス(段)を作り出して墳丘の裾までを整形すれば、土を盛って墳丘を造る必要はなく、後円部を形成することができるのです。
墳頂の円形にならって整形することで裾まで円形を保つことができます。自然丘陵が円形でなくても円形に仕上げることができたようです。
本連載は今回で最終回です。
【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…
【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...