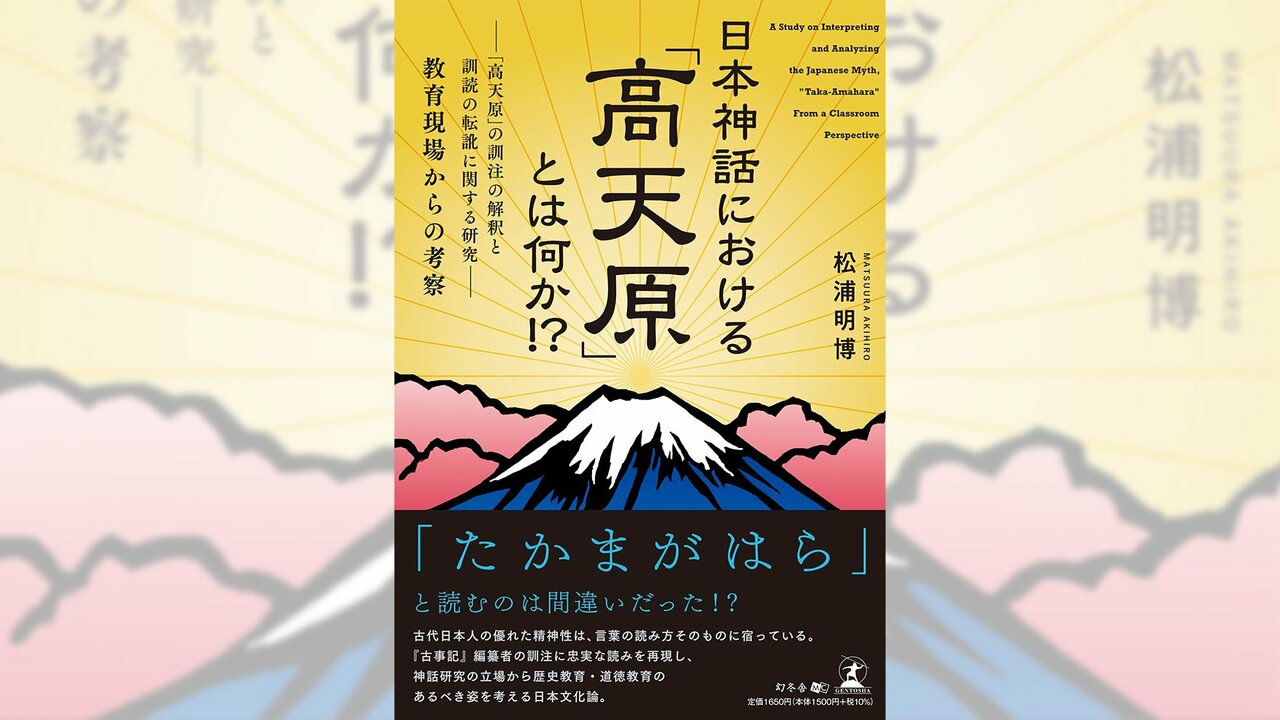【前回の記事を読む】「長雨」は、「ながあめ」とも「ながめ」とも読む。「あ」が消える法則を辿ると、見えてくるのは......
第一章 「高天原」訓読の研究成果と考察─その今日的意義
5. 度会延佳(わたらいのぶよし)の注釈と本居宣長(もとおりのりなが)の評価
宣長は、延佳本を手始めに、『古事記』の校合を以下の4回にわたり行っている(『古事記伝』奥書による)。
第1回 宝暦14年1月12日、度会延佳本。
「宝暦十四年甲申正月十二日以度会延佳校本校合終業、神風伊勢意須比飯高 舜庵本居宣長(花押)」。
第2回 延佳本校合済の信慶本で、安永9年5月25日(中巻)、同月26日(下巻)。
第3回 村井敬義所蔵古写本で、天明3年2月13日(全巻)。
第4回 真福寺本の転写本で、天明7年4月14日(全巻)。
ところが、宣長は『古事記伝』で、延佳を次のように批判している。
「今一つは、其の後に伊勢の神宮なる、度会延佳てふ人の、古本など校へて改め正して彫らせたるなり。此はかの脱ちたる字をも誤れるをも、大かた直して、訓もことわり聞ゆるさまに附けたり。
されど又まれには、己がさかしらをも加へて、字をも改めつと見えて、中々なることもあり。此の人すべて古語をしらず、ただ事の趣をのみ、一わたり思ひて訓めれば、其の訓は、言も意も、いたく古にたがひて、後の世なると漢なるとのみなり。さらに用ふべきにあらず。云々」
宣長は、『玉勝間』(十一の巻、「古事記伝の六の巻に入るべき事」)でも、延佳の「過ち」をとり上げ、再び「さかしら」の言葉を使って批判している注1。
宣長がここまで延佳を酷評したのは、なぜであろう。同郷の先学である延佳に対して対抗意識を燃やしたのであろうか。それとも伊勢外宮の神官である延佳が、外宮を内宮同等、いや内宮以上に権威(霊威)あるものとしていたことへの批判からであろうか。あるいは、儒教倫理を入れて度会神道の哲理が構築されたからであろうか。
いずれにせよ、宣長の延佳批判は、宣長の内宮重視や、「漢意(からごころ)」を排する余りの勇み足ではなかろうか、と筆者は考える。