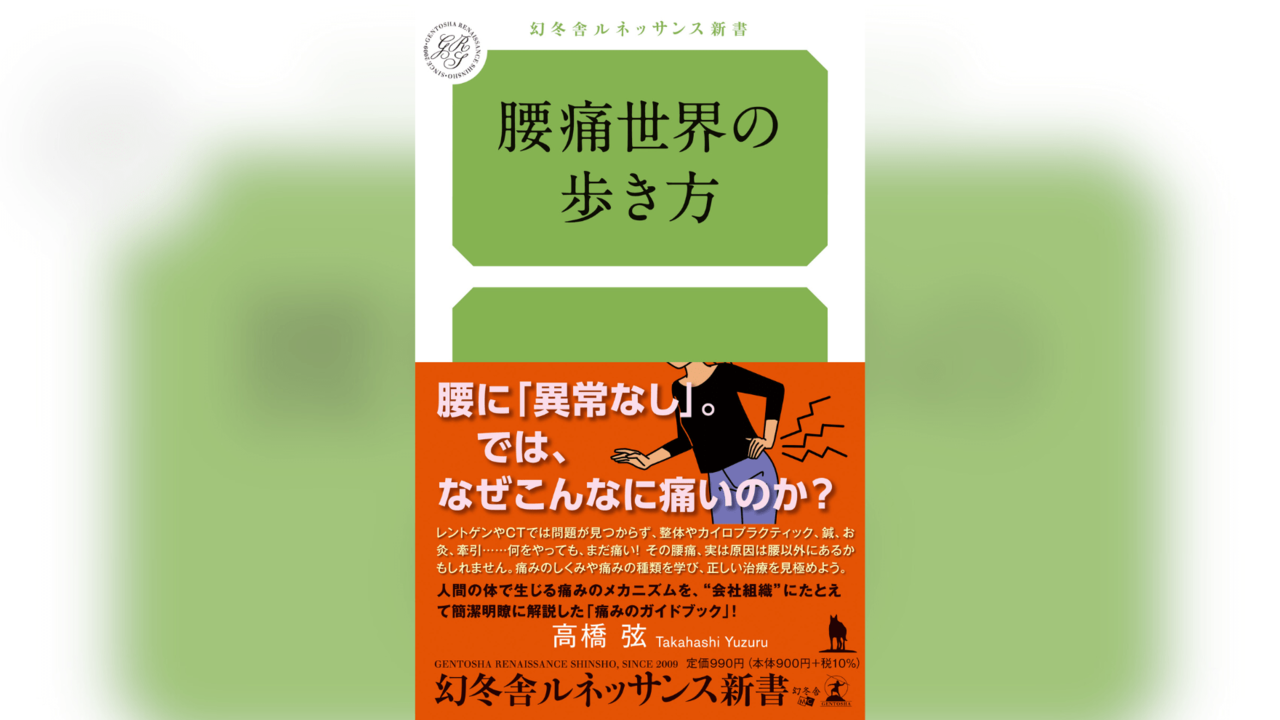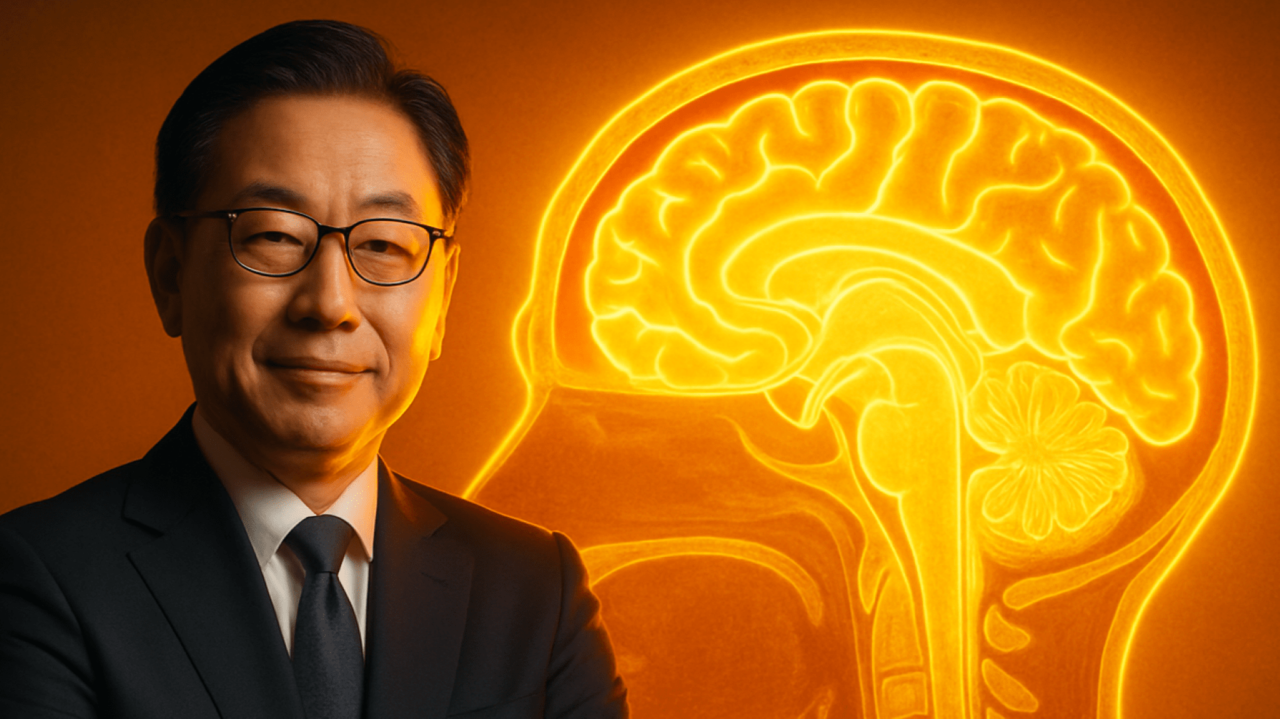【前回の記事を読む】もし脳に《社長室》があり、そこに《社長》がいて、外部や身体内部からの情報を見たり聞いたりしているならば《社長》の心は…?
第2章 心はどこに?〜意識の研究〜
痛みを「体験している」場所
つまり脳幹の神経活動は意識の必要条件です。ただし、脳幹は覚醒状態をつくるために必要な神経伝達物質をつくり大脳に送っていますが、それだけでは意識は生まれません。
一方、意識の主座と考えられてきた大脳皮質の神経活動も意識発生の必要条件ではないという説もあります(1)。神経学者のアントニオ・ダマシオは身体からの信号を受けた情動系の活動だけで「中核意識」が生まれると述べています(2)。
結局、痛みの場合は脳幹《総務部》により賦活されたペインマトリックスという《痛み担当部課》による《総合会議》そのものが「痛み体験」なのかもしれません1。
こう見てくると、脳には特別の《社長室》も《社長》も存在しないようです。でも、直感的には頭のなかには「心という“独裁者”の《社長》」が存在している感じがします。一方で、《担当者会議》の結果が《会社》の意識そのものであるという仮説は、リーダー不在で物事が決まるといわれる、われわれ日本人にとっては納得しやすい説明かもしれません。
神経活動がどうして意識を生み出すのか?
最後に残った超難問。それではいったいどのようにしてペインマトリックスの神経活動から「痛みという体験」が生まれるのか? 赤い色を見たときはなぜ「赤い感じ」を体験するのか? 針に刺された後の一連の神経活動がどのようにして「刺されたという不快な情動感覚」を体験するのか?
哲学者の鈴木貴之さんは、そのものずばり『ぼくらが原子の集まりなら、なぜ痛みや悲しみを感じるのだろう』(勁草書房)と題する本を書いています(3)。
脳神経細胞群の活動からなぜ、どのようにして、感覚質(クオリア(4))という主観的体験が生まれるのか。
オーストラリアの哲学者であるデイヴィッド・チャーマーズは心を生み出す神経機構の解明を「やさしい問題(イージー・プロブレム)」であり、そのような神経機構がどうして、どのようにして意識やクオリアを生み出すのかの解明を「難しい問題(ハード・プロブレム)」と二分し、「イージー・プロブレムは科学で解決できる可能性はあるが、ハード・プロブレムは既存の科学体系では解決できない」と言い切っています(5)。
さらにチャーマーズは、意識はあるレベル以上の複雑さをもった情報処理システム2に必然的に付随する「自然則3」だとも述べています。一種の二元論です。チャーマーズに同意しない科学者、哲学者も多いようですが、決定的な反論証拠は出ていません。脳の神経活動から心が生まれるしくみは「宇宙最大の謎!」なのです。
このように心に当たる「限られた」部分は脳には存在しないようです。しかし私たちには心も意識も厳然としてあります。その問題が痛みの医学で最も顕著に表れるのが、次の章で扱う主観と客観の問題なのです。