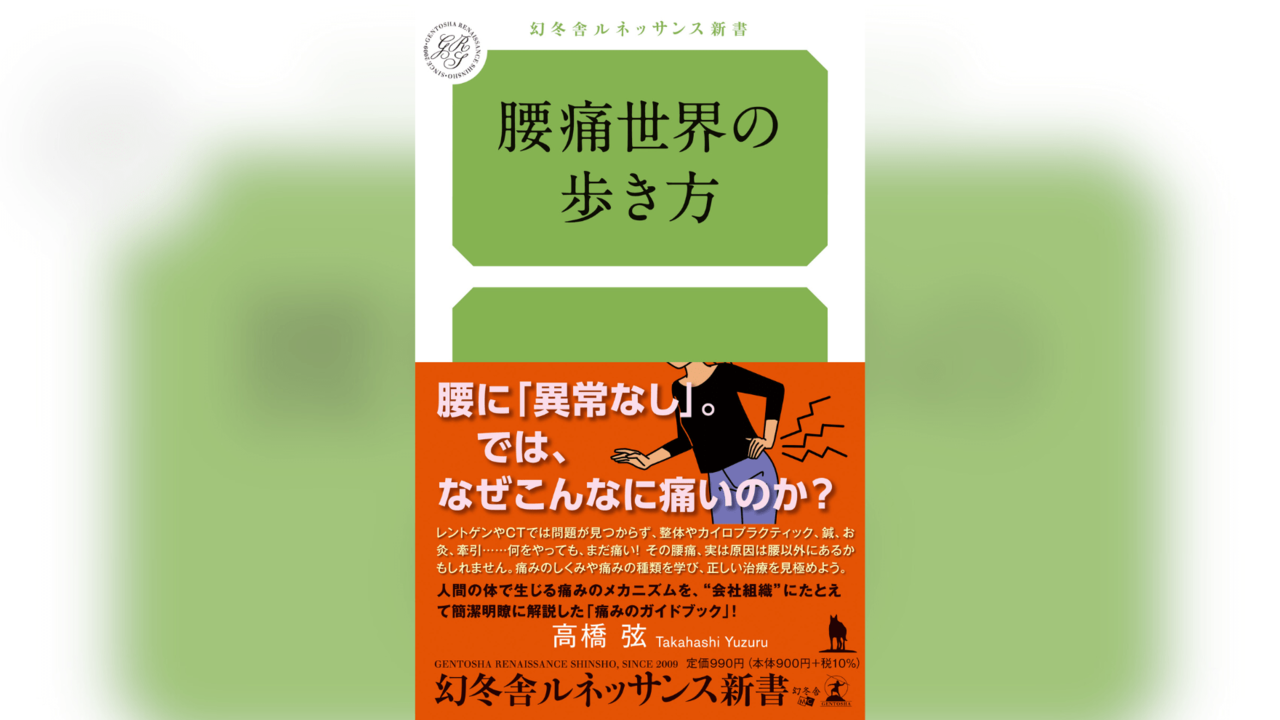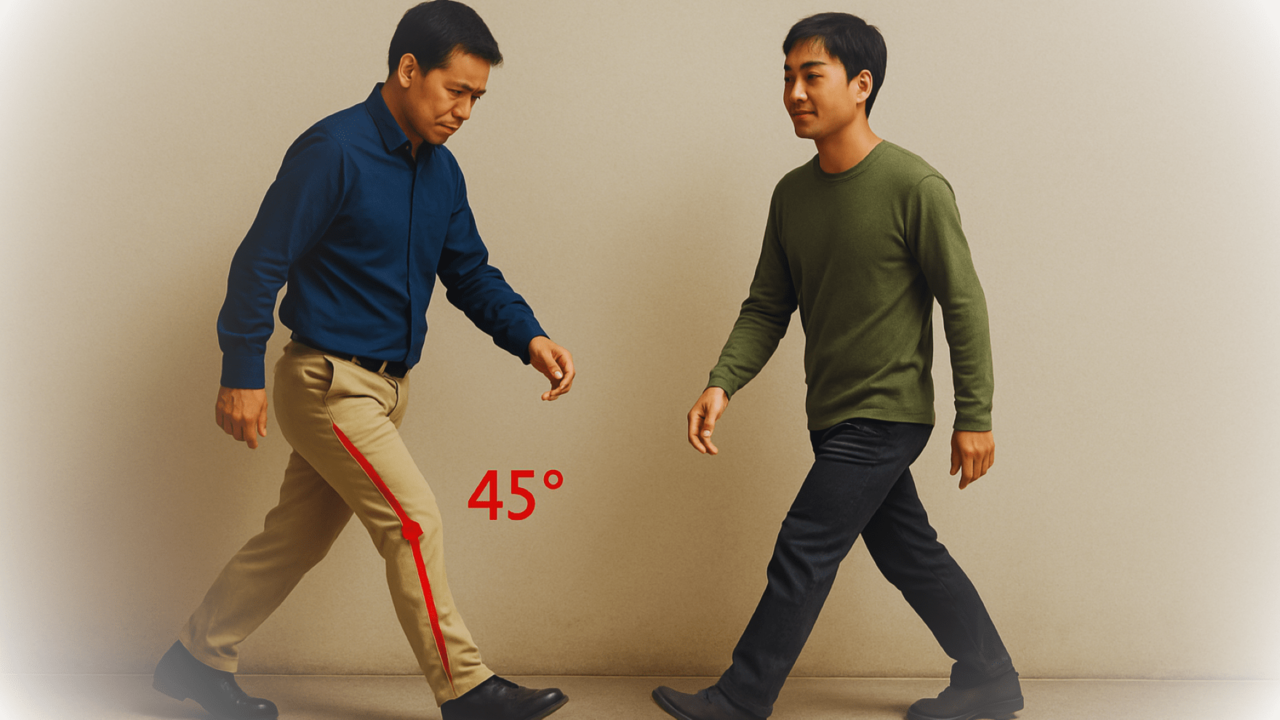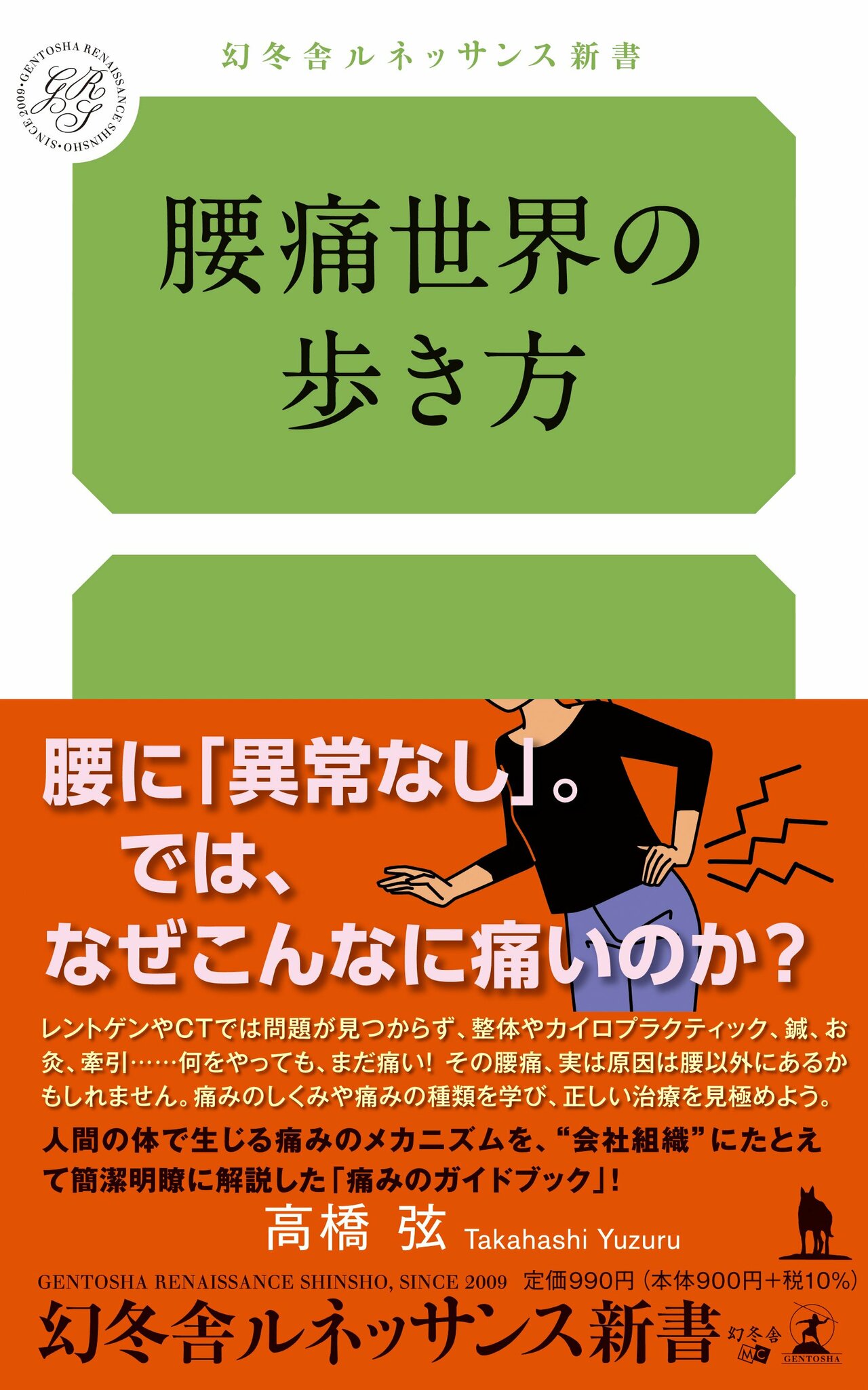【前回の記事を読む】脳の片隅に《社長室》があるわけでもなければ当然そこに《社長》もいるわけではない。あえて言えば、脳全体が《社長》と言える
第3章 主観と客観〜痛みの診療における観点〜
ここまで、痛みが起こるしくみと脳、心の関わりの問題についてさまざまに見てきました。本章では疼痛学の分野でもあまり議論されていない、実際の痛みの診療における「主観と客観の問題」を考えていきましょう。
身体外部に存在する事物は外感覚(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)によって知覚され、他の人と共有できるので客観的な存在です1。身体内部の構造も医学的検査により観察できるので、やはり客観的存在です。
それに対して、体組織内部の感覚(内感覚)は他人とは共有できず心のなかだけにあり、常に主観的です2。痛みもまた、主観的です。ベテランの医者でも患者さんの痛みを「ありのままに」追体験することはできません3。
痛みの診療では、「心が知覚している主観的な体の異常」と、心が知ることのできない「客観的な体の異常」というふたつの観点が必要です。
無意識のシステム 心が知らない体のこと
心《社長》は、どの程度自分の体《会社》のことを知っているのでしょうか? 答は「ほとんど何も知らない」です。私たちの体はそのほとんどが、心のあずかり知らぬところで自律的に機能しています4。
たとえば肝臓や腎臓からの感覚情報も脳には送られてすが、そのほぼすべてを心は把握していません。わたしたちが、われらが《社長》が、肝臓や腎臓などの《維持管理事業所》の存在を知っているのは、単に「学校で教わった」からです5。内臓や血管の感覚は平常時には意識されません。
例外は腸管、膀胱、心臓、肺などで、平常時でも「注意すれば」心は気づくことができます。この内臓や血管の感覚と運動を担当しているのが自律神経系です。異常をとらえたときだけ、心はそれを知るところとなり、心《社長》は「違和感」や「痛み」を感じ、そして不安になります。
それ以外の感覚について、皮膚感覚はほぼ意識されますが、運動器の場合は組織別、部位別に意識度にかなり差があります。骨の内部にある骨髄にも感覚神経がありますが、平常時には意識されません。骨髄内部に損傷、出血、膿ができたとき初めて痛みとして知覚されます。
私たちはまた、自分の姿や動きを関節の「屈曲の角度や速度の情報」として知ることができます。関節の角度の感覚を専門的には「固有感覚6」といいますが、固有感覚はじっとしていると弱くなり、やがて消えてしまって自分がどんな格好をしているかわからなくなります。
このように運動器《事業所》からの情報も多くは自動処理されており、心《社長》には必要最小限にしか届いておらず、注意を向けても知ることができる範囲は限られています。