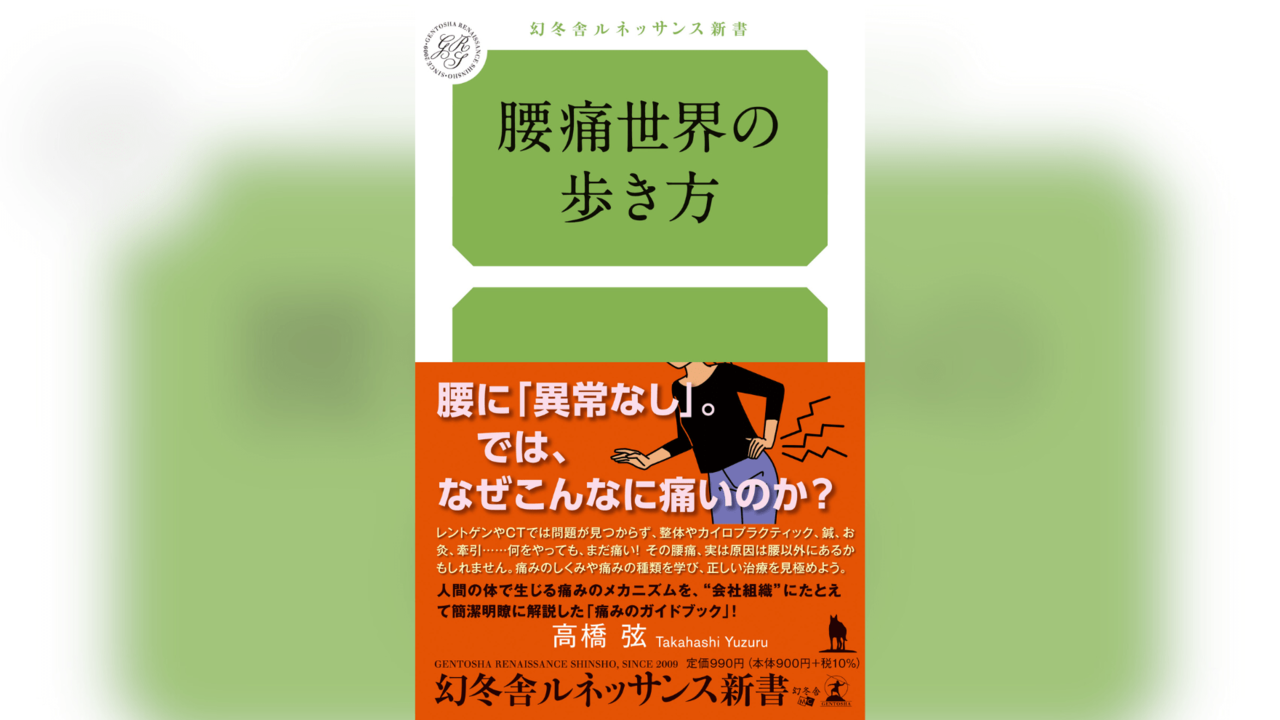【前回の記事を読む】「心頭滅却すれば火もまた涼し」とは言うが、どんな人も強い痛みを滅却することはできない。しかし弱い痛みならば――
第3章 主観と客観〜痛みの診療における観点〜
「主観的な体」と「客観的な体」
主観的身体
心が知っている自分の体を「主観的身体」と呼ぶことにします1。主観的身体は「生まれてから成長とともに経験的に知った自分の体の姿」です。体各部の名称や異常を感じたときの言い回しなどは、学校で教わらなくても自然に覚えていきます2。
本書では「主観的な身体の各部の名称」を「客観的な解剖用語」と区別するためにカタカナで表すことにします3。
患者さんが病院を訪れた初診時に「問診票」に記入をしてもらいますが、症状の場所や性質の表現にはかなりの個人差があります。以下、本書では患者さんが自分の言葉で表現する体各部の名称(主観的名称)をカタカナで、解剖学用語を漢字で書き表します。
頸から胸に移行する背中の部分は解剖学的には「項部(こうぶ、うなじ)」ですが、クビ、カタと言う人もいます。おしりをコシと呼ぶ人もいます。主観的身体の名称はどれが正しいということはなく、各自各様であってよいものです。
「体の異常感覚」と「異常を表現する言葉」は当然ながら主観的です。私たちは内感覚をお互いに共有することはできません。
イタイは誰もが使い、その感覚質を医者は共感できますが、ダルイ、ハバッタイ、コソバユイ、ムズムズ、ズキズキとなると、患者さんがどのような感覚質(クオリア)を体験しているのか、医者は自分の体験と照らし合わせて想像するしかありません。
シビレはイタミと同じくらい運動器の診療で頻繁に遭遇する訴えですが、患者さんがいかなる体験をしているのか、実際のところはわかりません4。
医者は患者さんの主観的訴えをしばしば軽視・無視して「客観的な異常」の発見に精力そそぎます。しかし医者が忘れてはいけないのは、患者さんの求めている第一目標はまさに「主観的な異常を消してほしい」ということなのです。
疼痛学では「体組織損傷の存在しない痛み」「体組織損傷は存在するがそれとは不釣り合いな痛み」であっても痛みそのものを「治療が必要な病気」と見なします。