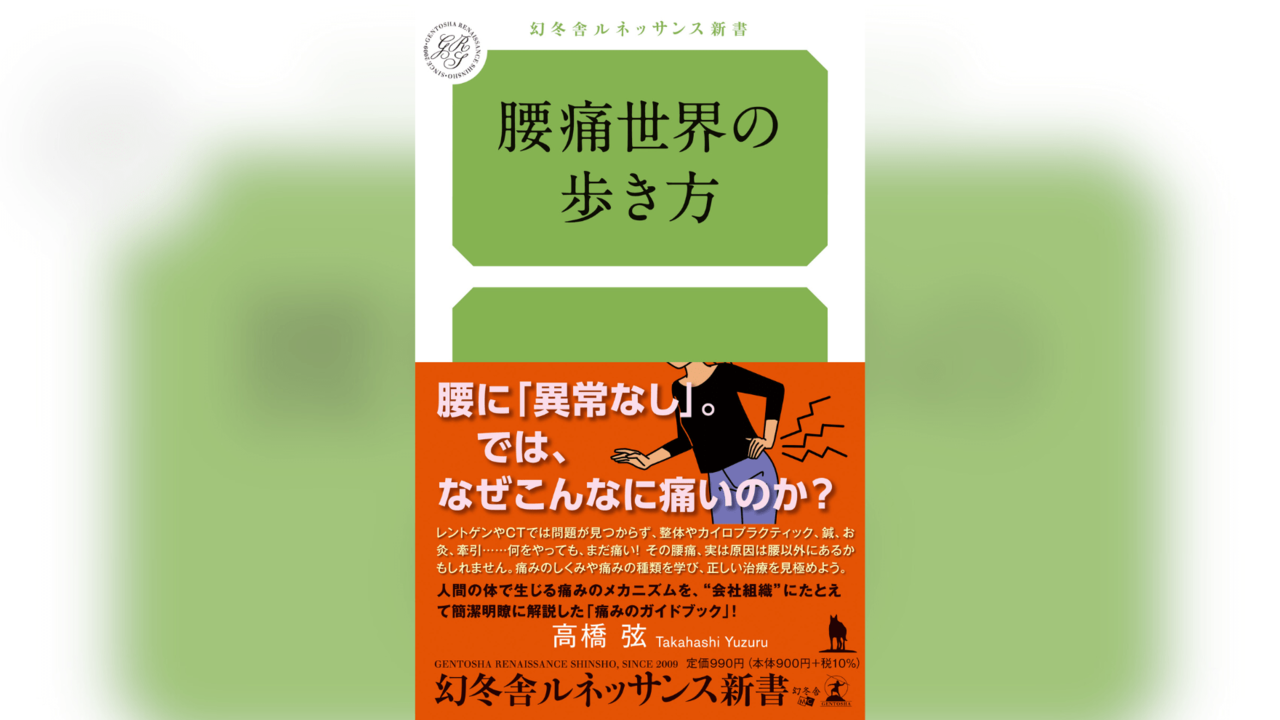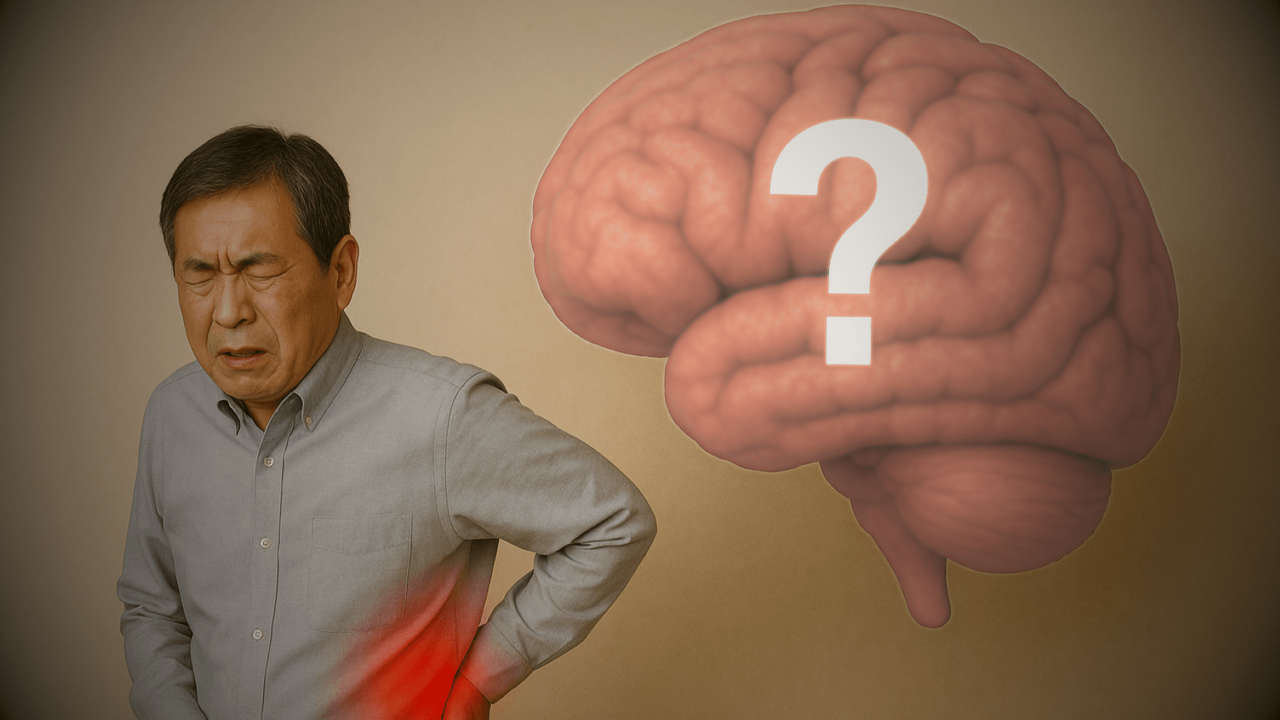【前回の記事を読む】前頭前野背外側部は痛みの認知や社会的意義の認識など、高度な処理が行われており、会社組織における《全体統括部長》のような存在
第1章 痛みのしくみ
大脳〜情動と感覚、そして認知〜
大脳皮質〜痛みの知覚の主体?〜
大脳皮質の神経活動は意識されることが多いため、大脳皮質こそが「意識」の主体と考えられてきました。しかし現在の疼痛科学、神経科学では大脳皮質の活動は意識の必要条件でも十分条件とはいえないようです。
さらに疼痛科学の研究により、大脳皮質からは逆に辺縁系と視床に向かって多数の神経線維が投射していることが明らかになりました。しかも数のうえではそちらの方が多いのです。
つまり大脳皮質《部長》だけで最終決定をするのではなく、扁桃体、海馬、視床など各《課》との活発な「情報交換」を行い、《部課長からなる全体連絡会議》で最終決定をしているようなのです。
ペインマトリックス
デカルトが脳こそが感覚を知覚する場所であると指摘して以来、科学者は知覚のしくみを研究してきました。
筆者が医学部で学んだ昭和時代は、脳を切るとどのような構造になっているのか(解剖学)、そして脳の切片を顕微鏡でのぞくとどのような神経細胞が並んでいるのか(組織学)については、ほぼ現代の水準に達していました。しかし観察された脳の各部と神経細胞の機能についてはまだ多くはわかっていませんでした。
脳の各部分がそれぞれ何らかの専門的な機能を果たしているという考え方を、脳の「機能局在論」といいます。
視覚では光の受容器が目であるとは誰でも知っています。では、目がとらえた光を知覚する細胞群はどこにあるのか。意外に思われるかもしれませんが、それは目と反対側にある「後頭葉」(後頭部の内側)なのです。後頭葉はそのほぼすべてが視覚処理にあてがわれています1。
皮膚触覚については、すでに書いたように頭頂葉の「体性感覚野」が担当しています。ペンフィールドのホムンクルスのいる場所です。痛みの感覚がどこに局在しているのか、正確にはまだよくわかっていません。腰痛については島皮質ではないかと考えられています。