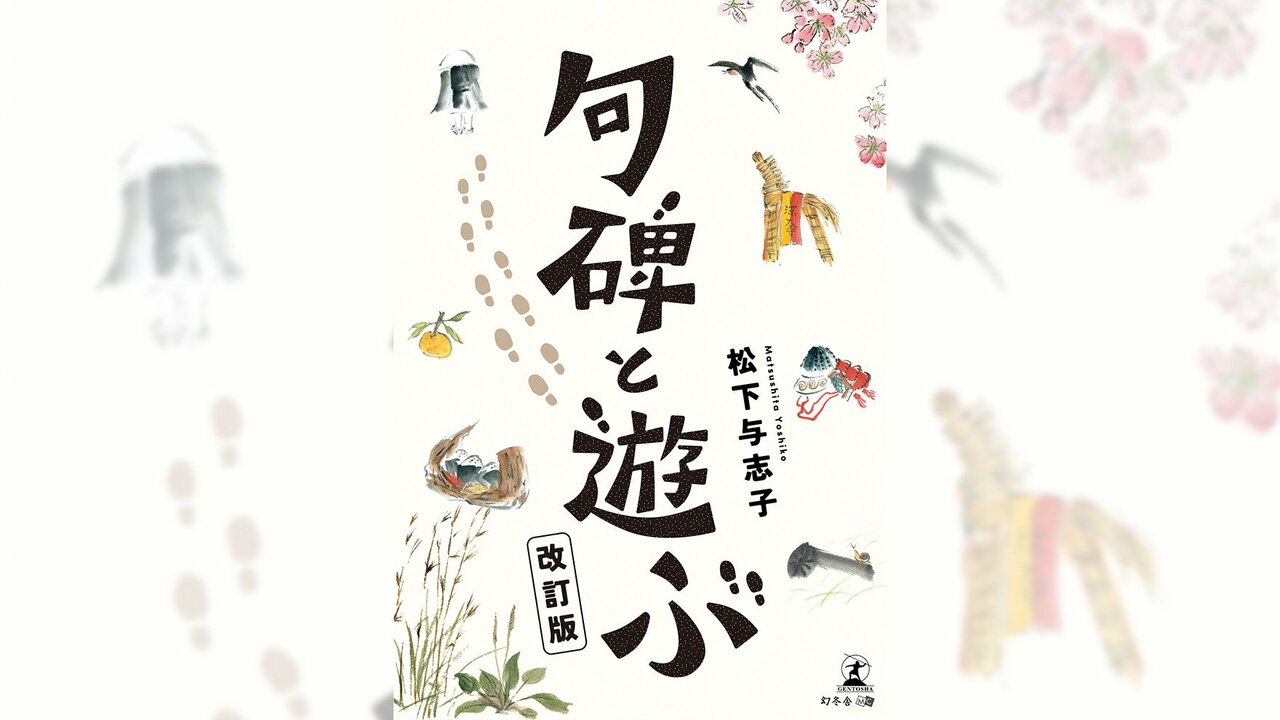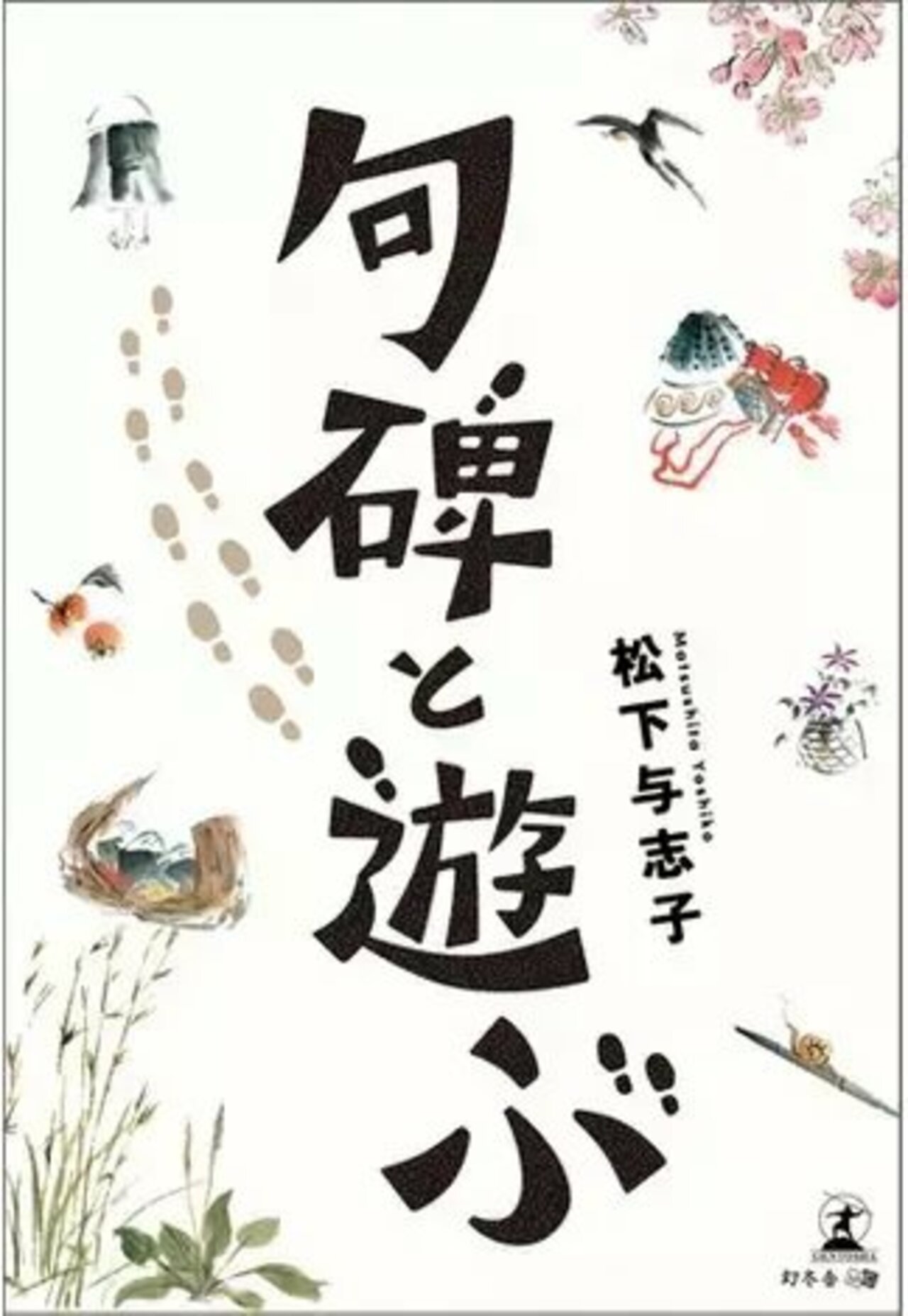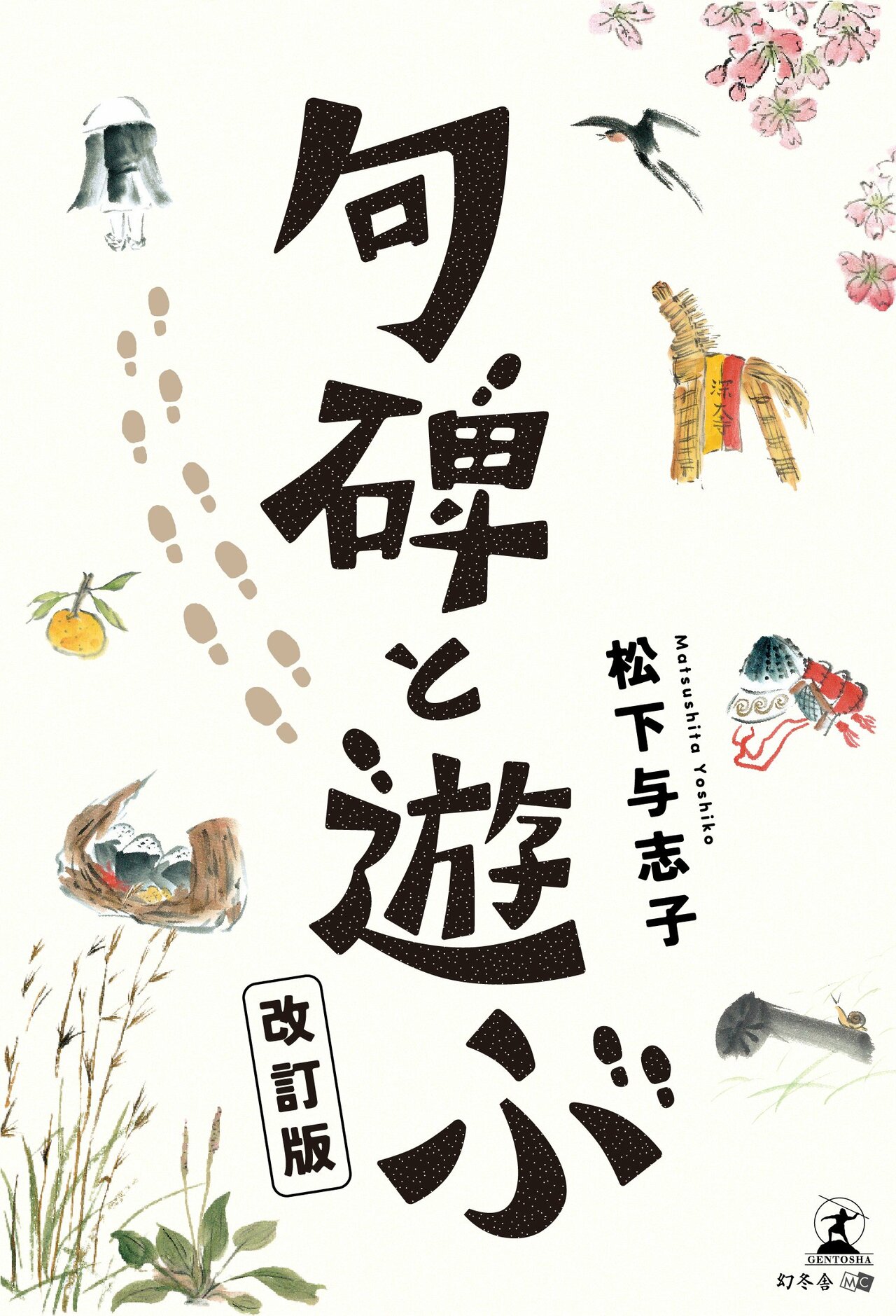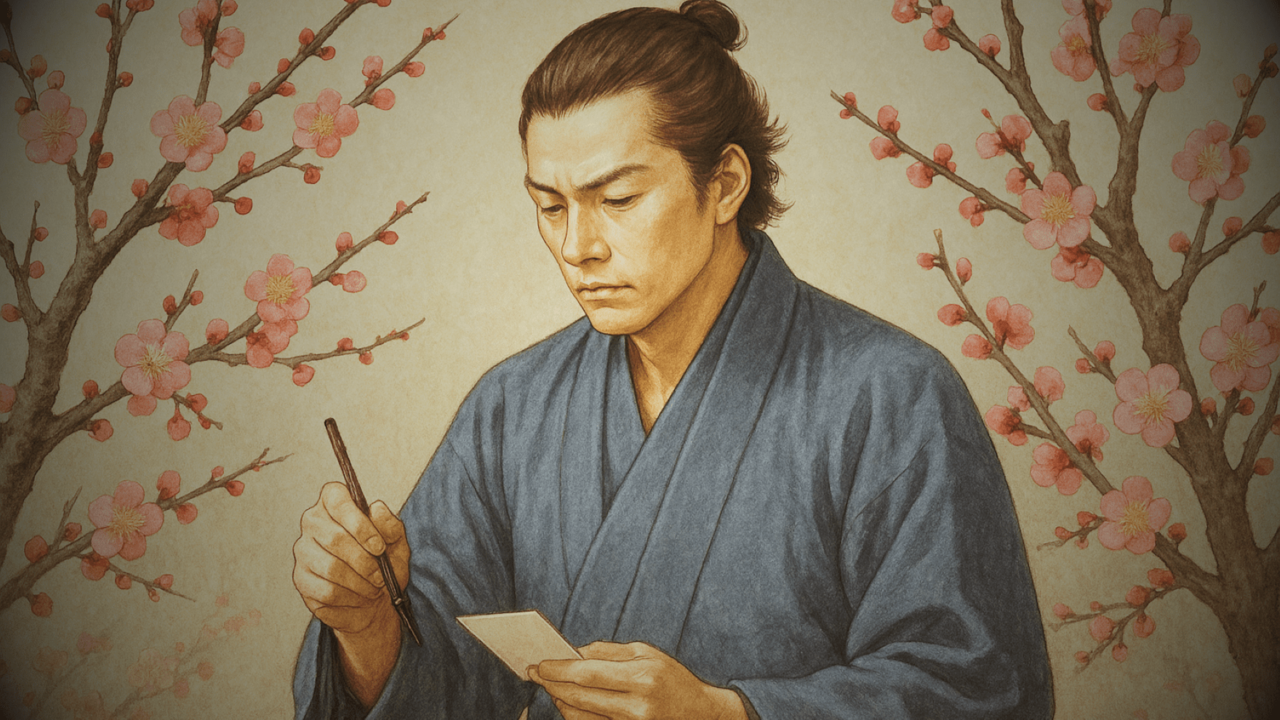【前回記事を読む】「道」とは面白いものだ。多摩丘陵に位置する小野路が長きにわたり運び続けた人々の心。
のらぼう菜
この周辺の話題ばかりで恐縮だが我が家の住所、仙谷という地名は家の裏手を7、80メートル上がった所にある仙谷山寿福寺という寺の名に由来している。
禅宗のこの寿福寺に、兄頼朝の加勢をする為にこの辺りで兵を整える用意をしていた源義経と弁慶が暫く逗留していたという。その際残したという馬の鎧と写経が寺宝としてこの寺に大切に保管されている。
その後この辺りでは度々の激戦があり、寿福寺まで上る坂は幽霊坂と呼ばれていたことがあると聞いた。戦で倒れた兵の多くの骸がこの寺に放り込まれその霊を怖れたことからそう呼ばれたらしい。
頼朝の命により殺された木曾義仲の息子義高と許嫁の大姫との悲恋のストーリーも大河ドラマにあって涙を誘ったが、この気の毒な木曾義高の居た地もさほど遠くない場所に木曽町という名を残している。
我が家から最寄駅まで歩く道の途中に多摩川の支流に架かる小さな橋があり、そこに「指月橋」と彫られた古い石碑が立っている。義経がここから見える月を愛でて指差したのが由来とある。
NHK大河ドラマに因んだ我が家周辺の観光案内のような文章になってしまったが、地元に残る数々の鎌倉時代がより身近なものになり興味が増した。きっと来春食べるのらぼう菜の味は一味違って感じられるかも知れない。
この際もう少し歴史探訪をしたくなり、久しぶりに鎌倉時代の本拠地、鶴岡八幡宮周辺を訪ね歩いてみた。
三代将軍実朝が最期を遂げた場所の有名な大銀杏の切り株は八幡宮の階の左に大事に保存されていた。八幡宮から若宮堂への歩道の傍に大きな句碑を見つけた。昭和14年に建てられた俳人裸馬と称した菅礼之助の実朝を偲ぶ句であった。
歌あはれその人あはれ実朝忌
肉親、友、味方までも抹殺しなければならなかった悲劇の連鎖の鎌倉時代は、或る歴史学者が、出来ればいちばん生まれ変わりたくない時代だと述べていた。句碑の「あはれ」の一語が胸に沁みた。