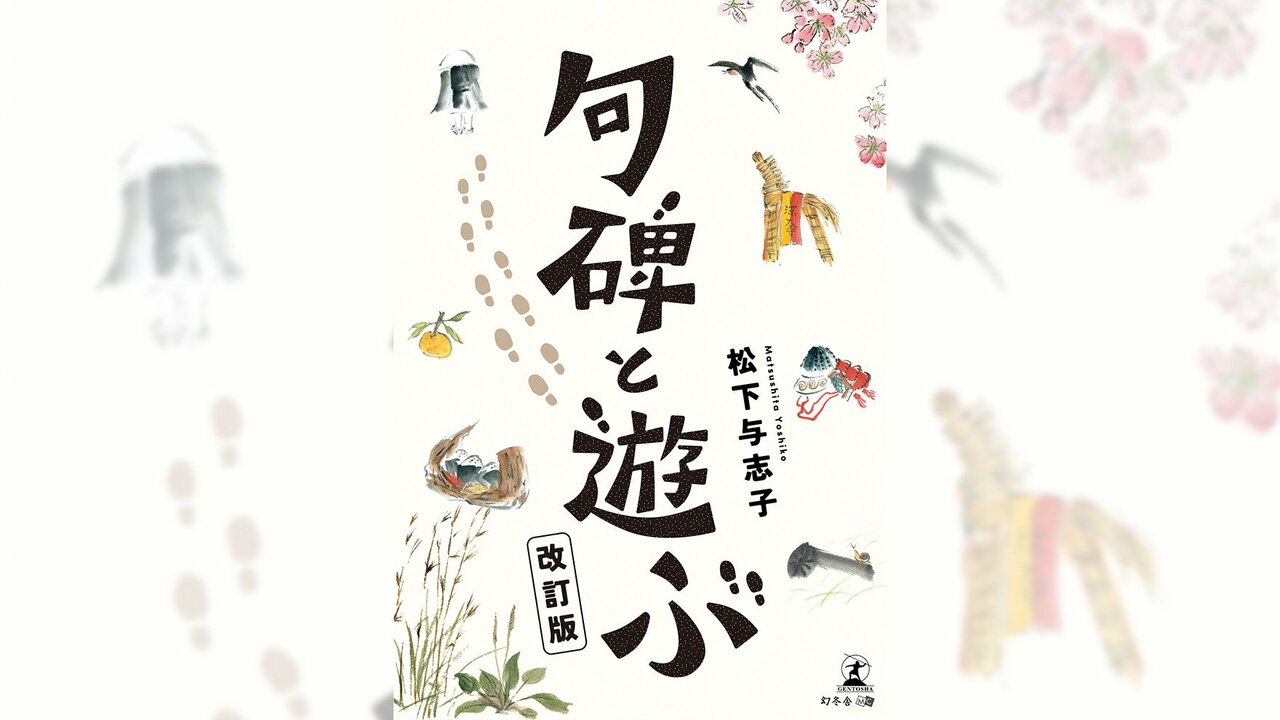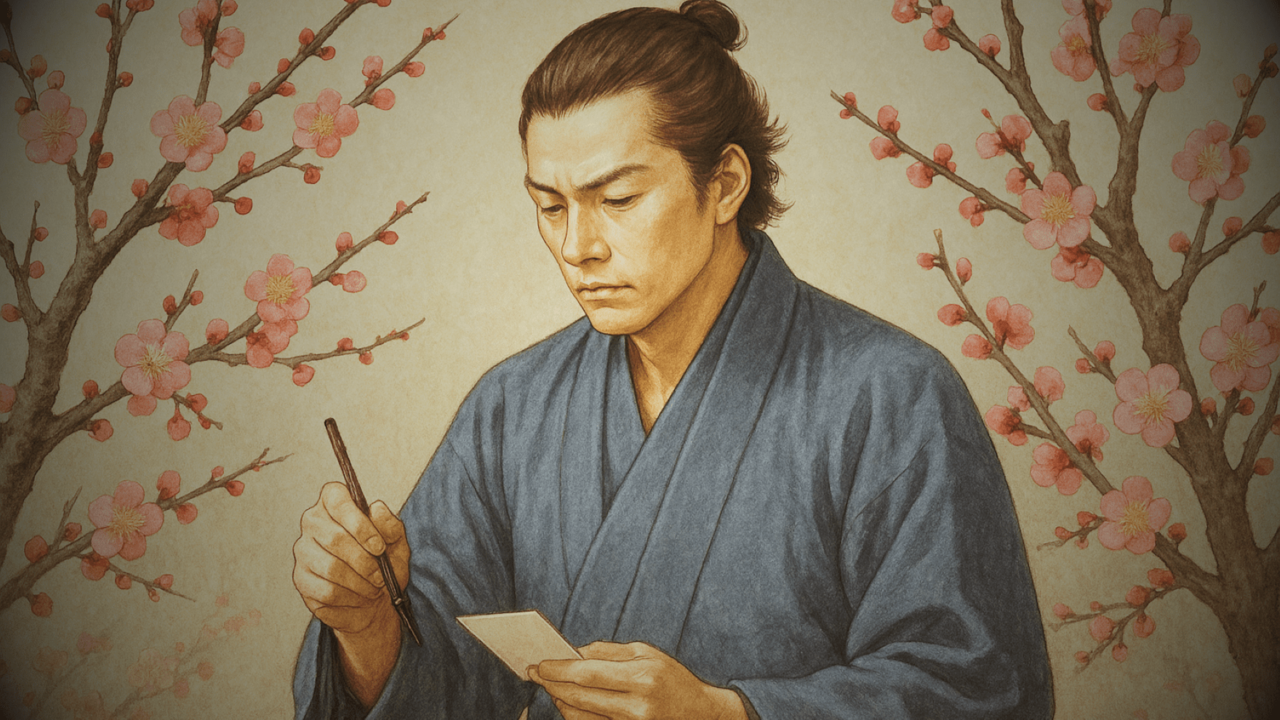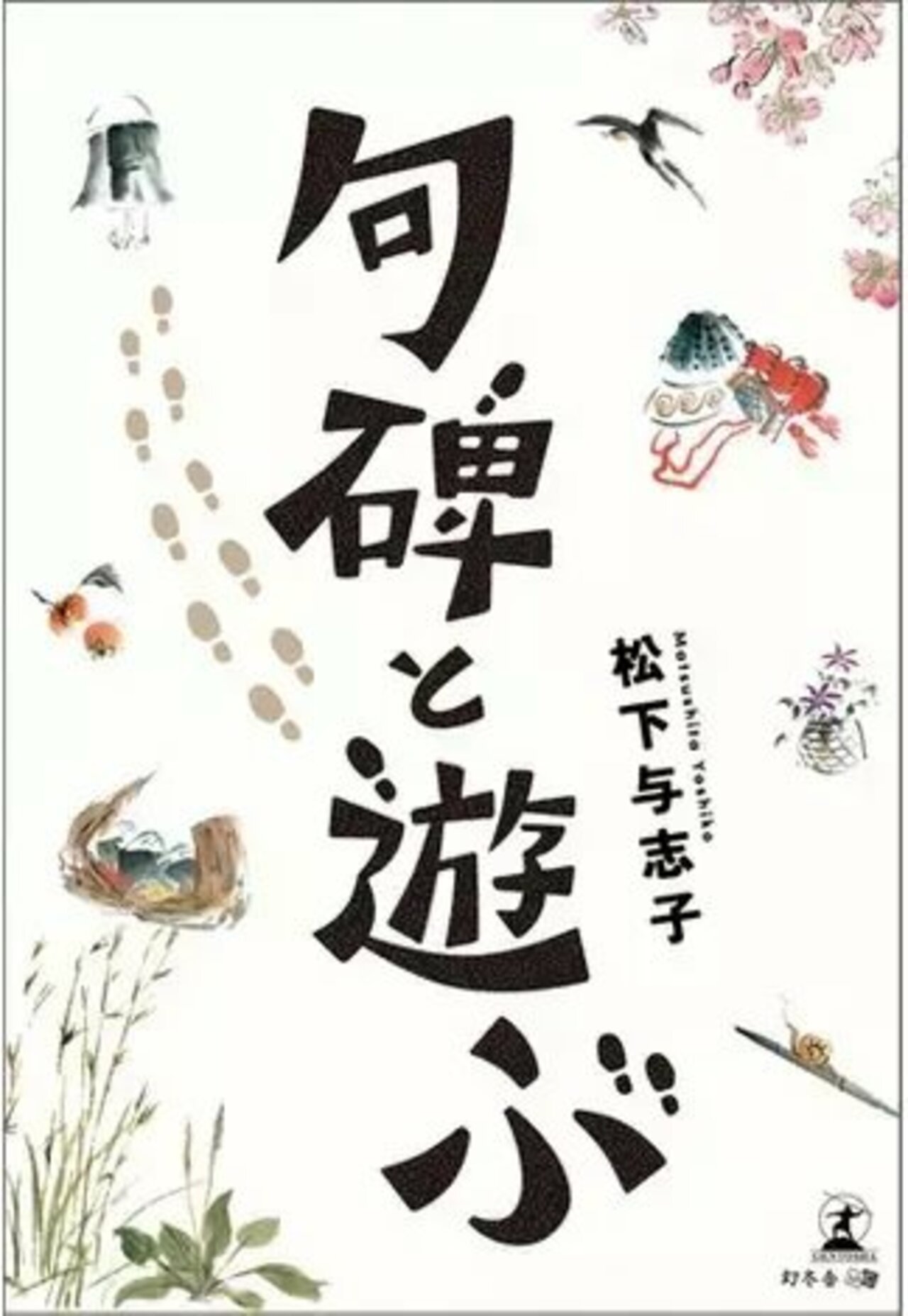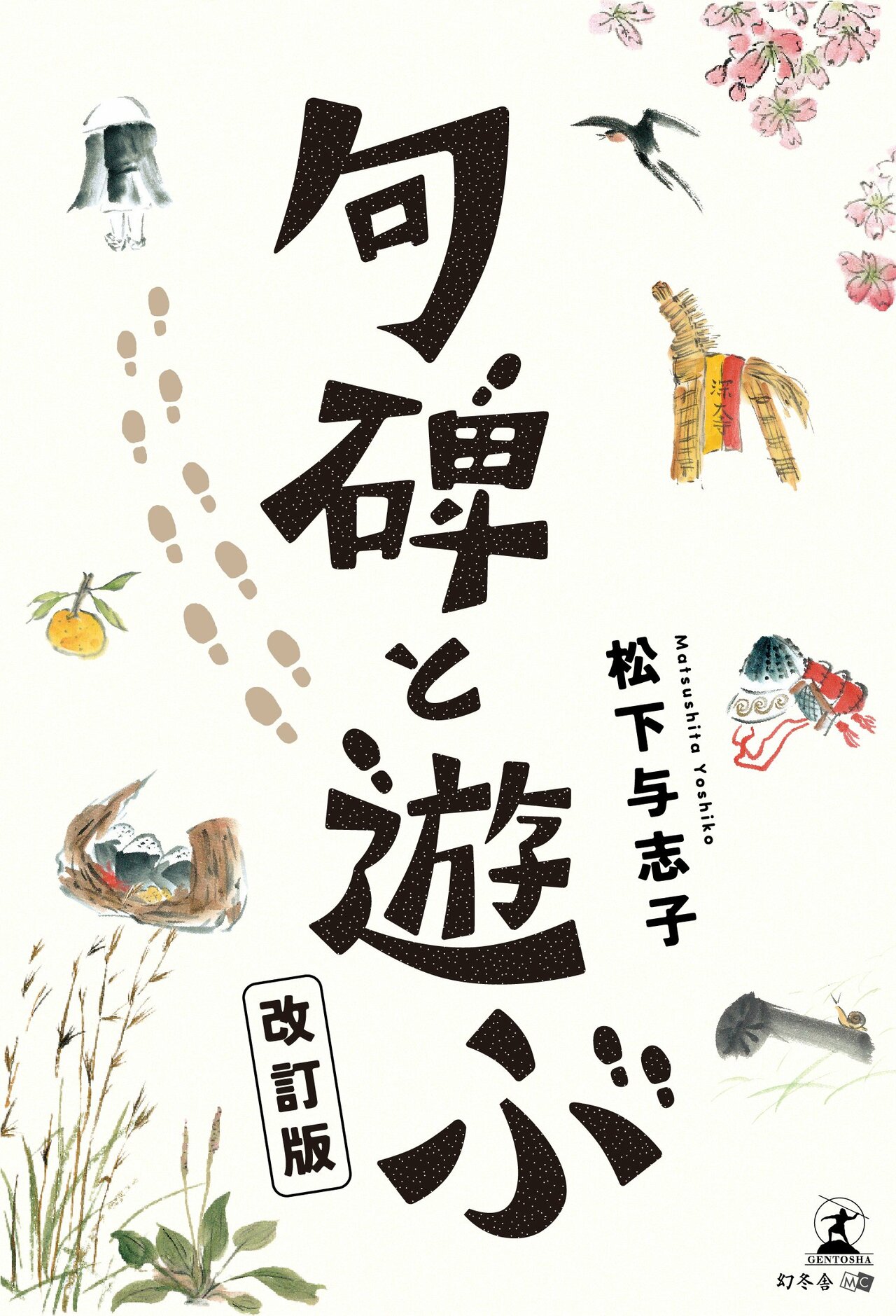【前回記事を読む】風情漂う根岸の里で子規の足跡をたどる! その暮らしぶりと愛した草野球、そしてガラス障子の秘密とは?
子規庵のガラス窓
「ガラス障子にしたのは第一は寒気を防ぐこと、第二はいながら外の景色を見るためである。果たして見える。見えるも見えるも、庭の松の木も見える。…‥物干し竿に足袋のぶら下げてあるのも見える。上野の森も見える。凍ったような雲も見える。鳶の舞うているのも見える。…予想もしない第三の利益は日光を浴びること、この時は病気という感じが全く消えてしまう。」
この他にも幾つもの文章に子規はガラス障子の嬉しさを書き残している。
「去年の暮れ、病室の南側をガラス障子にせしより、何かにつけて嬉しきことぞ大き。いつかはガラス越しに雪も見んなどと出来ぬ贅沢とばかり思いしに、今目の当たりこの楽しみを得て命ものぶ心地なり。」(『俳星』より)
夏目漱石への書簡にも、ガラスを通す陽を浴びる嬉しさを書き送っている。
野が見ゆるガラス障子や冬籠
ガラス窓に上野も見えて冬籠
鳶見えて冬あたたかやガラス窓
ガラス越しに冬の日当たる病間かな
実は、筆者の夫の退職前の勤務会社は大手硝子企業であった。最近、企業主催の会合があり、その席で、虚子の心尽くしの子規庵のガラス障子が当社のガラスであったことが話題に出たのだそうだ。子規庵のガラス障子の話は、日本大学入試や最近のセンター試験にも試験問題として取り上げられたことも夫から聞かされた。
子規を看取った後、子規庵の外に出て見上げた月を虚子は詠んでいる。
子規逝くや十七日の月明に
虚子の万感の思いが伝わる気がする。