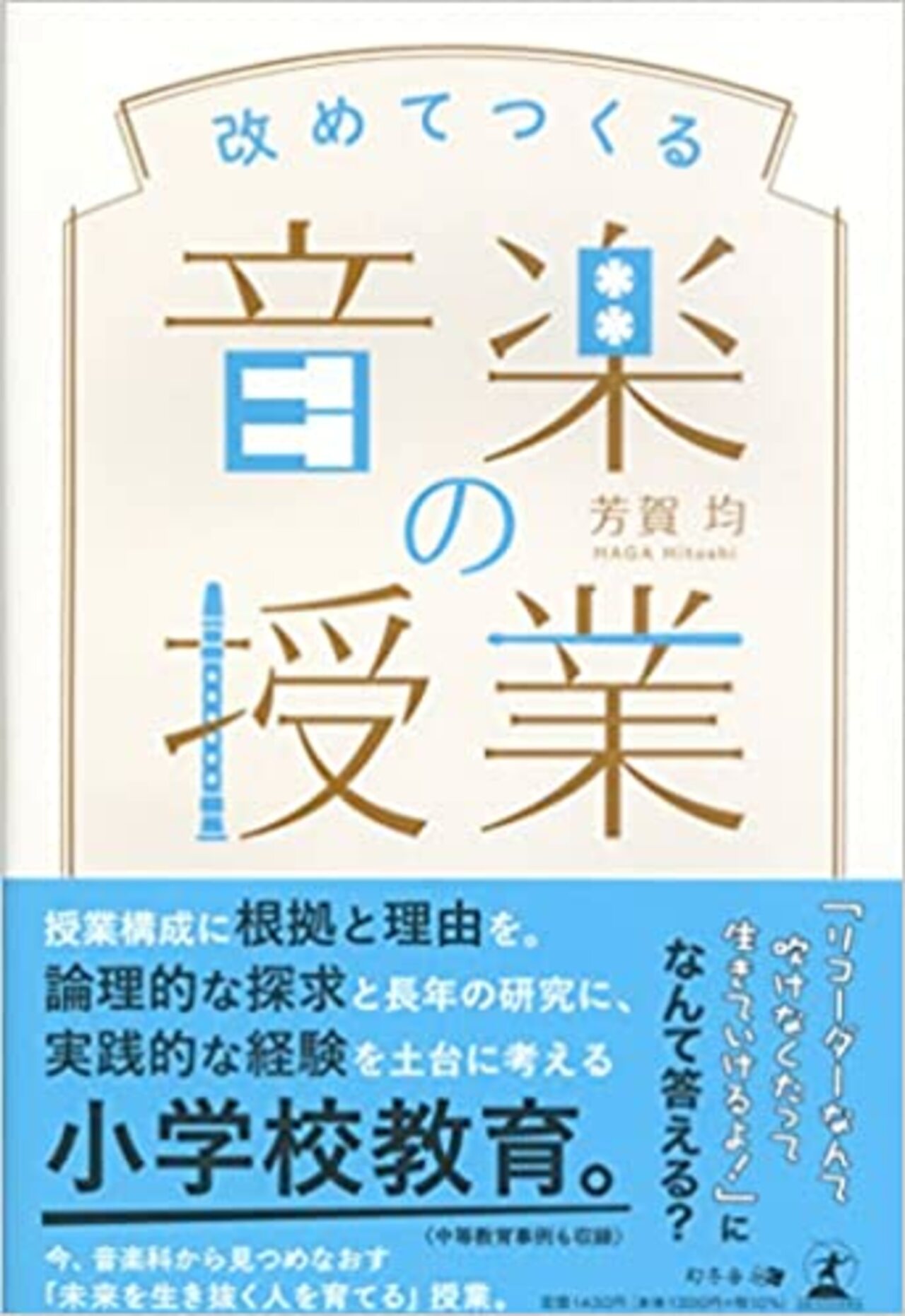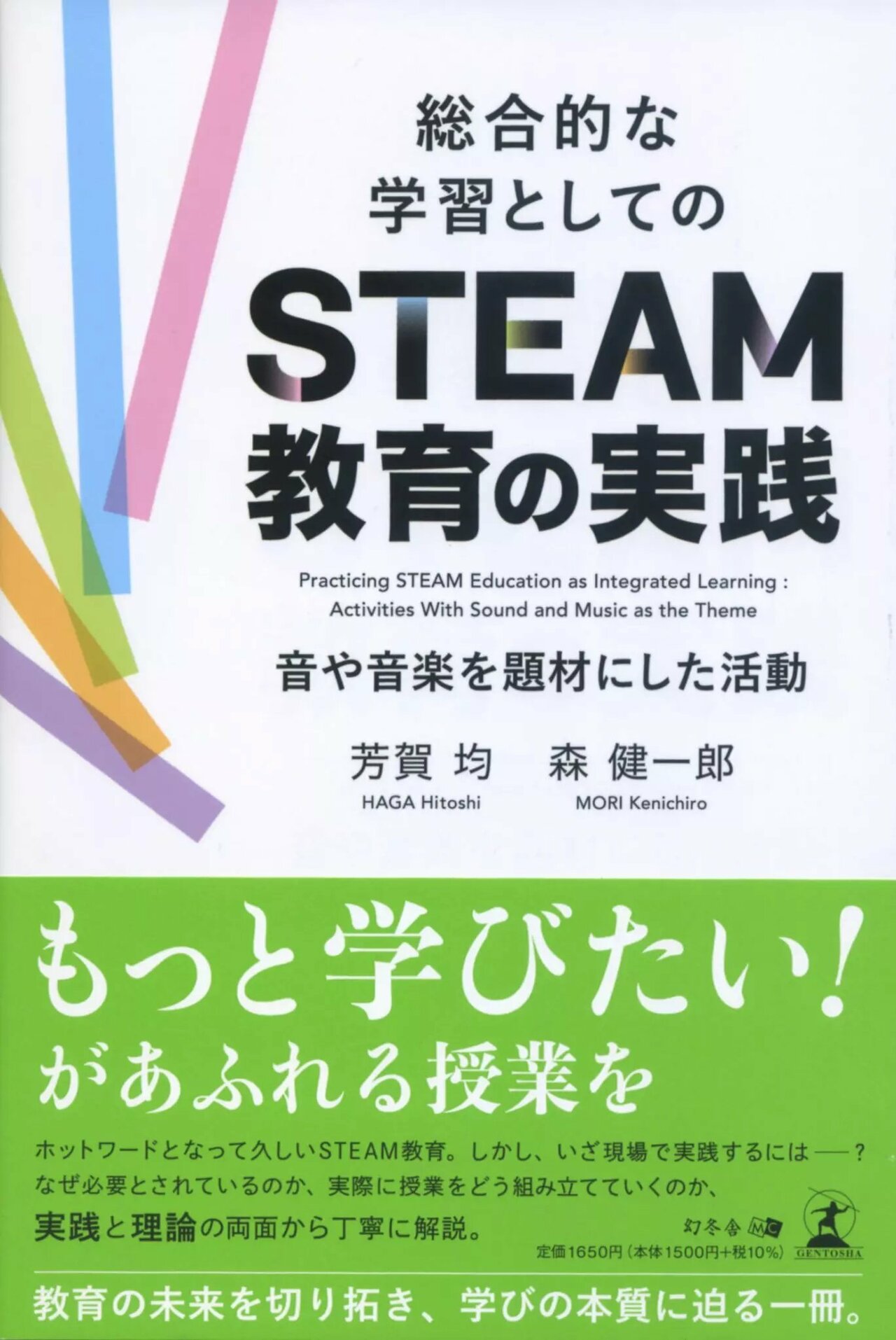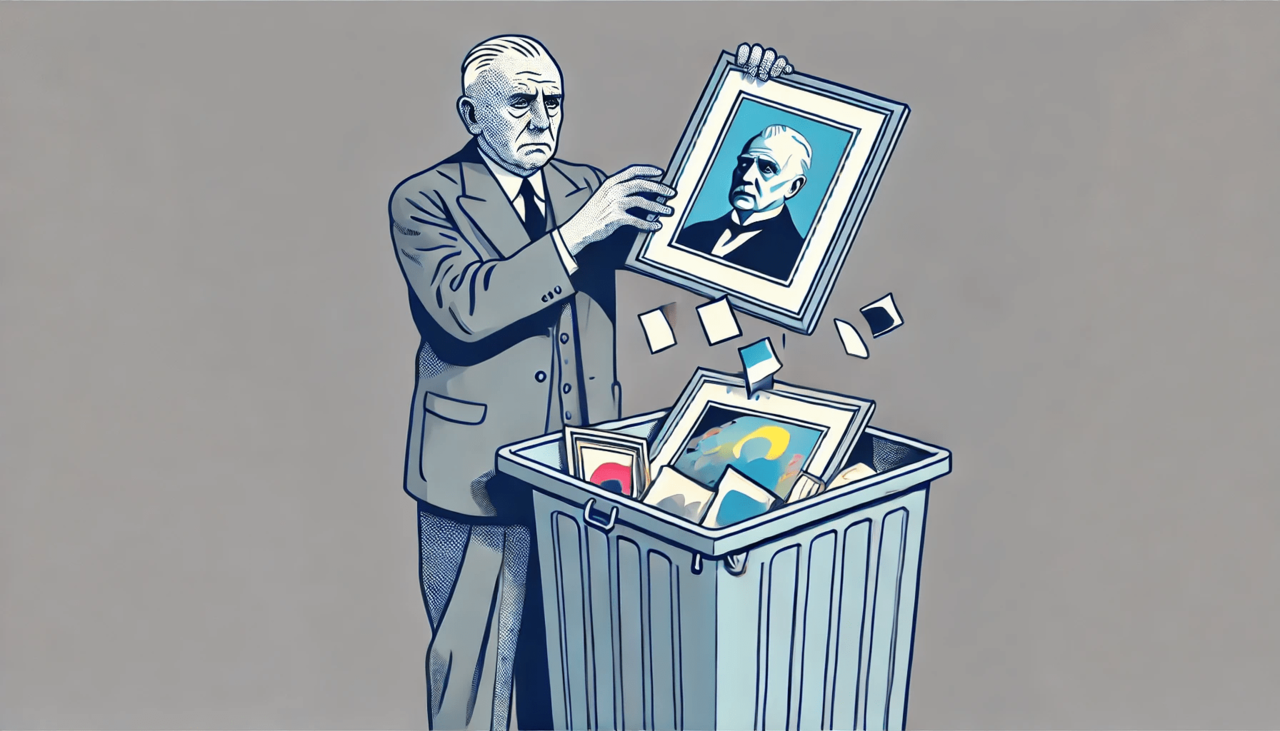5) まず、「音楽は評価できない」という言葉を本当によく聞きますので、そういうイメージが一般にもたれているものと思います。しかしそれは、例えば演奏や作品についての「出来栄え」や、曲を聴いて感じ取った感想等に対することであって、そのことと「お勉強の様子」を評価することとを混同することから起こるイメージであるといえます。
6) 高浦勝義『絶対評価とルーブリックの理論と実際』黎明書房、2004、p.99.
7) 言語化は、様々な立場によって、いいきることができない、という場合もありますが、実践においては、教師も子どもも、物事を曖昧なままでなく明確に認識していくことが、物事に実感や納得をもって臨む安心感につながると考えます。そのことをきっかけに、身の周りの現象を自ら定義しなおしていくような主体性につながっていけば、それこそが、深い学びであるといえるのではないでしょうか。
8) 高浦勝義『絶対評価とルーブリックの理論と実際』黎明書房、2004、p.95.
9) 小林信郎『新指導要録の解説と実際』教育出版、1980、p.13.
10) 高浦勝義『指導要録のあゆみと教育評価』黎明書房、2011、p.53. には、昭和55 年版から平成3 年版への改定の意味について、「各教科の『観点別学習状況』の観点は大人中心主義、教える内容中心主義から、学ぶ子ども中心主義、学び方中心主義へと転換したと考えられる」とある。評価の観点の順序は、学習の構造を表すと考えることができる。
【前回記事を読む】【音楽教育】「オレ、ピアノ弾けないし…」音楽の授業が苦手な青年教師。だけど今日の授業には生徒皆が熱中した! その方法は?
【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...