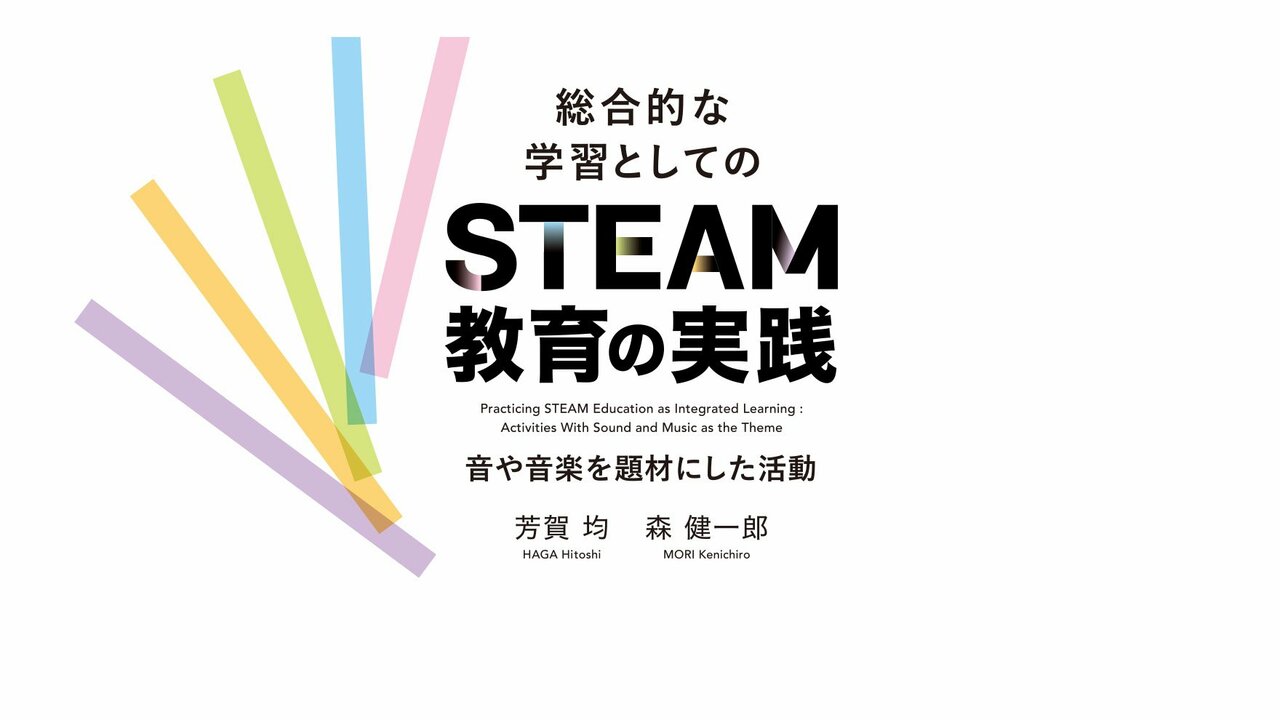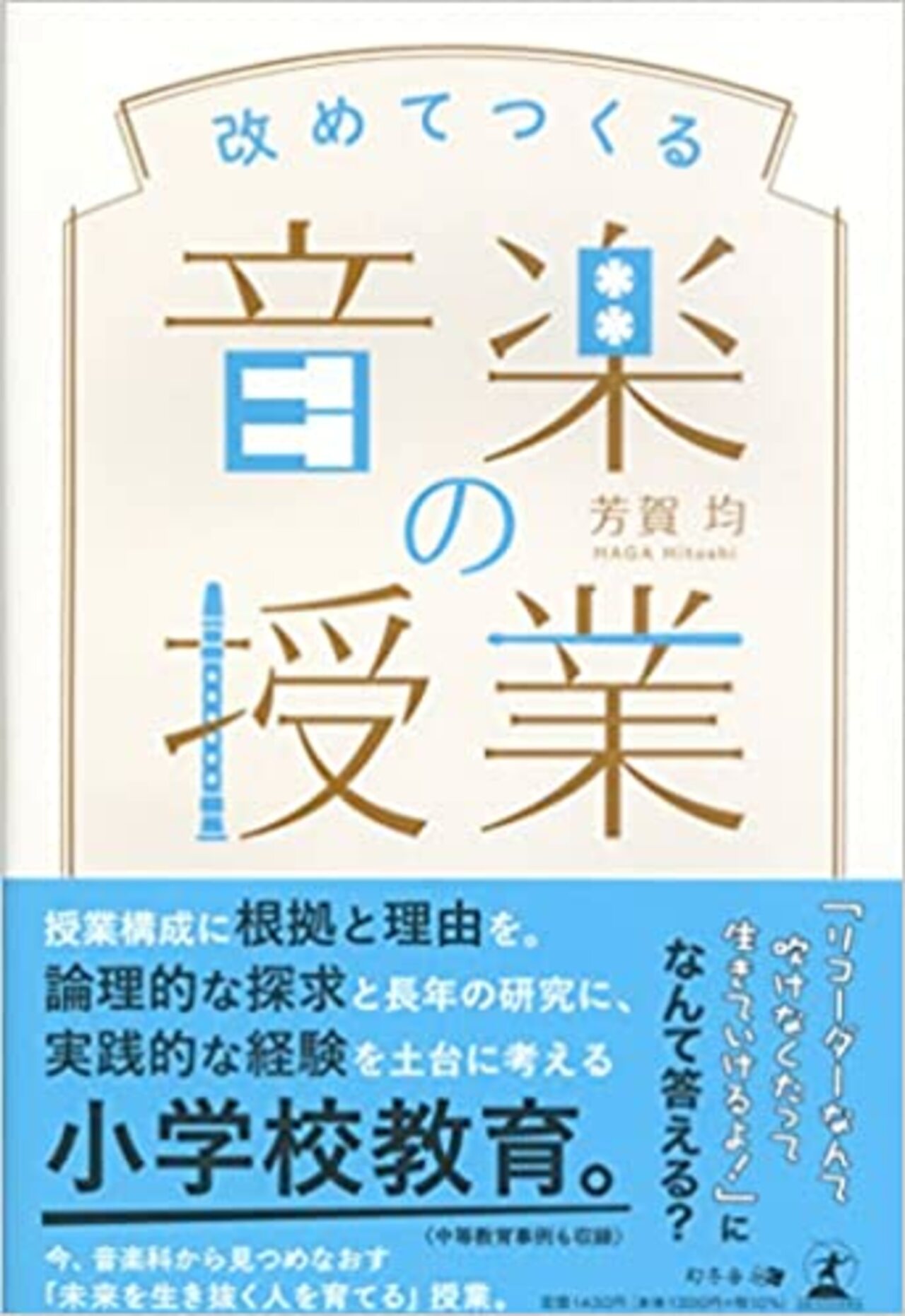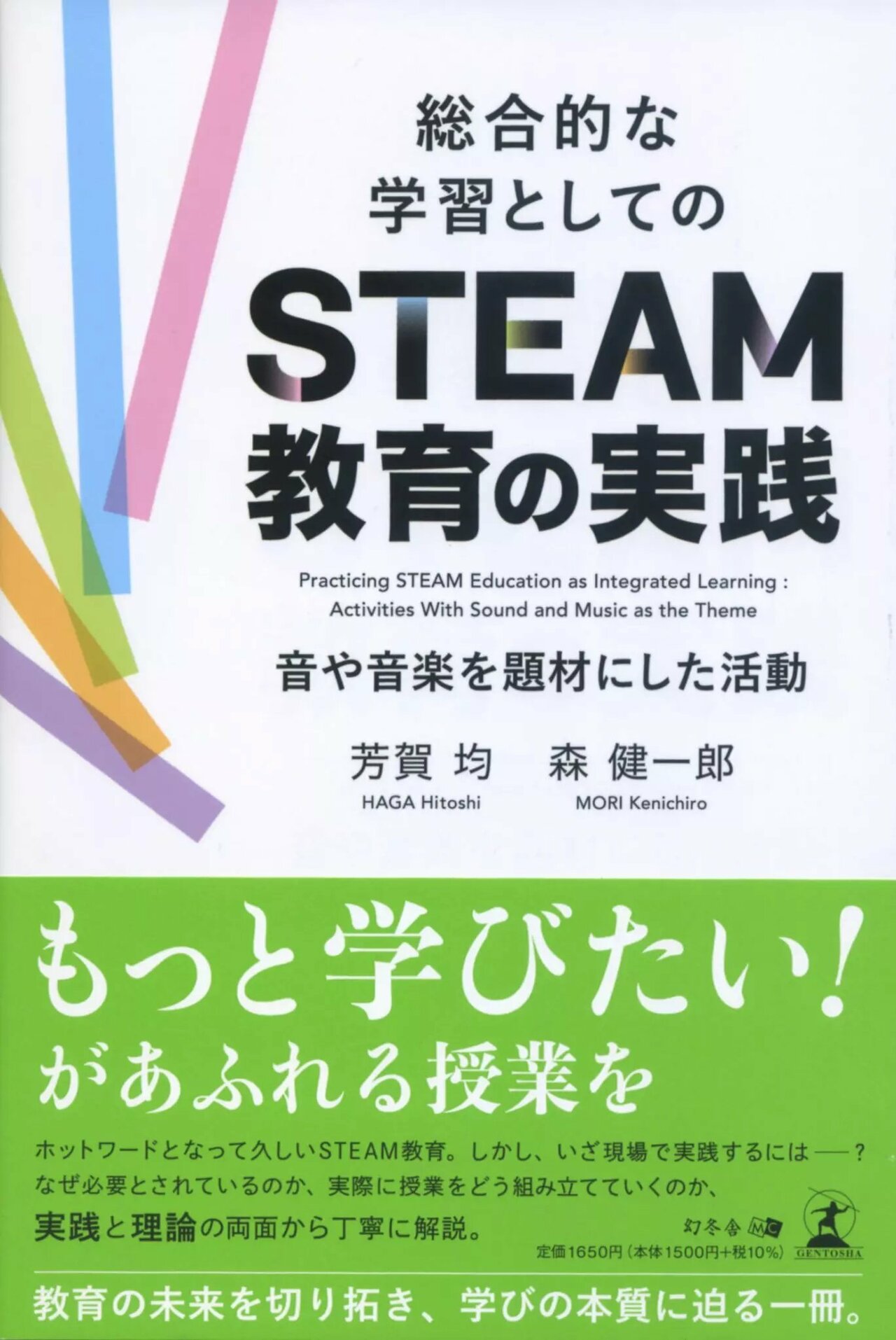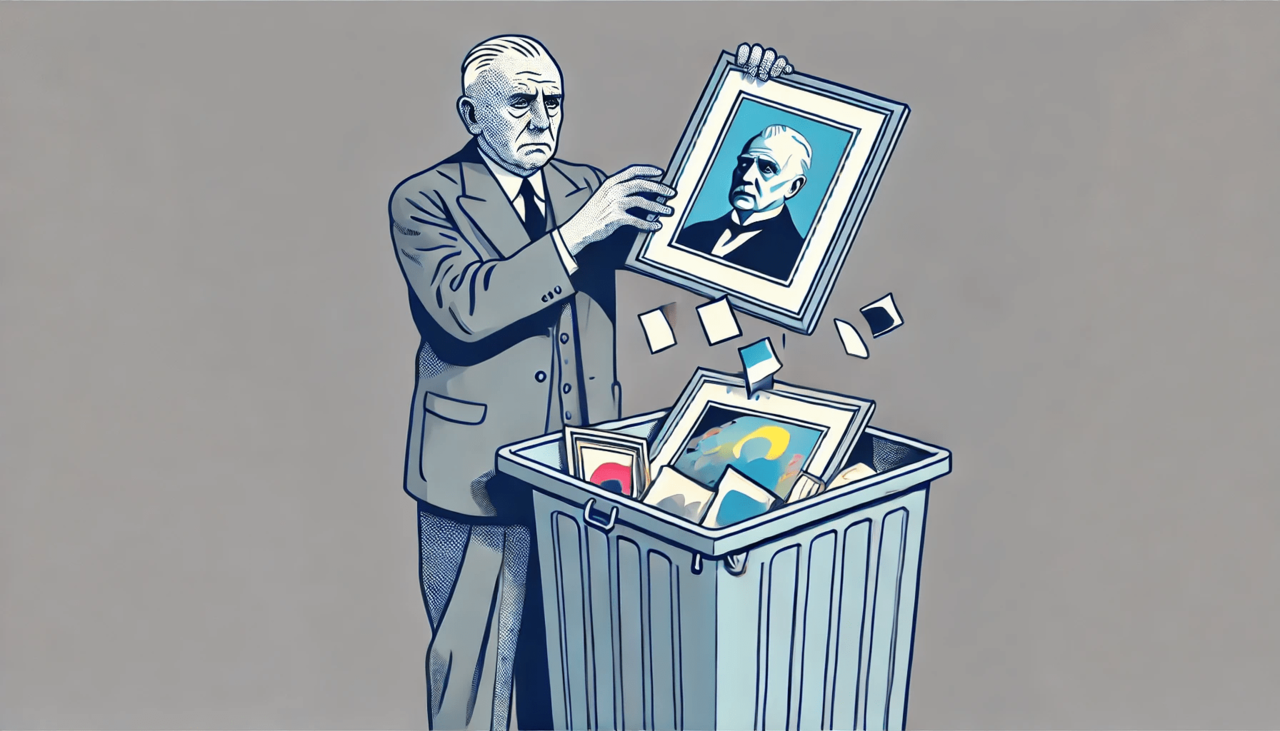【前回の記事を読む】「役に立つ/立たない」という判断基準は万能ではない。アートの歴史を見ると教育のヒントがわかる?
1 変化の激しい時代に向けた教育
1-3 本書で取り上げるSTEAM教育
1-3-2 A(アート)(芸術)とE(エンジニアリング)を重視する
こうした探究や創造ということに馴染む学習として問題解決学習が挙げられます。
ところで、その「問題」をどのように捉えるかについて考慮しておきたいと思います。
「問題」というのは、研究の世界では探究すべき問い、いわゆる「リサーチクエスチョン(research question)」(〈2-1〉教科の話で後述)ですが、現実の世界では実践的な課題、つまり「プラクティカルなプロブレムリサーチクエスチョンとは、研究的疑問のことであり、先行研究を調査・検討し、「明らかになっていることとなっていないこと」を把握した上で、意義があるか否か等のいくつかの条件に基づいて追究される問題(問い)のことです。
リサーチクエスチョンとして掲げる「問題」(問い)は、できるだけ大きな範囲を捉える、生活や社会との連続性をもった問いが望ましいと考えますが、それは生活と結びついていなくても成立するといえます。
一方、本書では、より具体的なプロブレムに立脚したいと考えています。それは、子どもたちには、常に活動を楽しんでもらいたいという思いがあるからです。
筆者(芳賀)の身を置く音楽の立場からは、音の高さ(音高)①は、ある周波数(振動数)の音にラベルを貼ったもの、すなわちドレミ等の呼称を用いて音を捉えることが一般的です。一方、筆者(森)の理科の立場からは、音の高さは 440Hz とか 261Hz といった周波数(振動数)で表現されます。