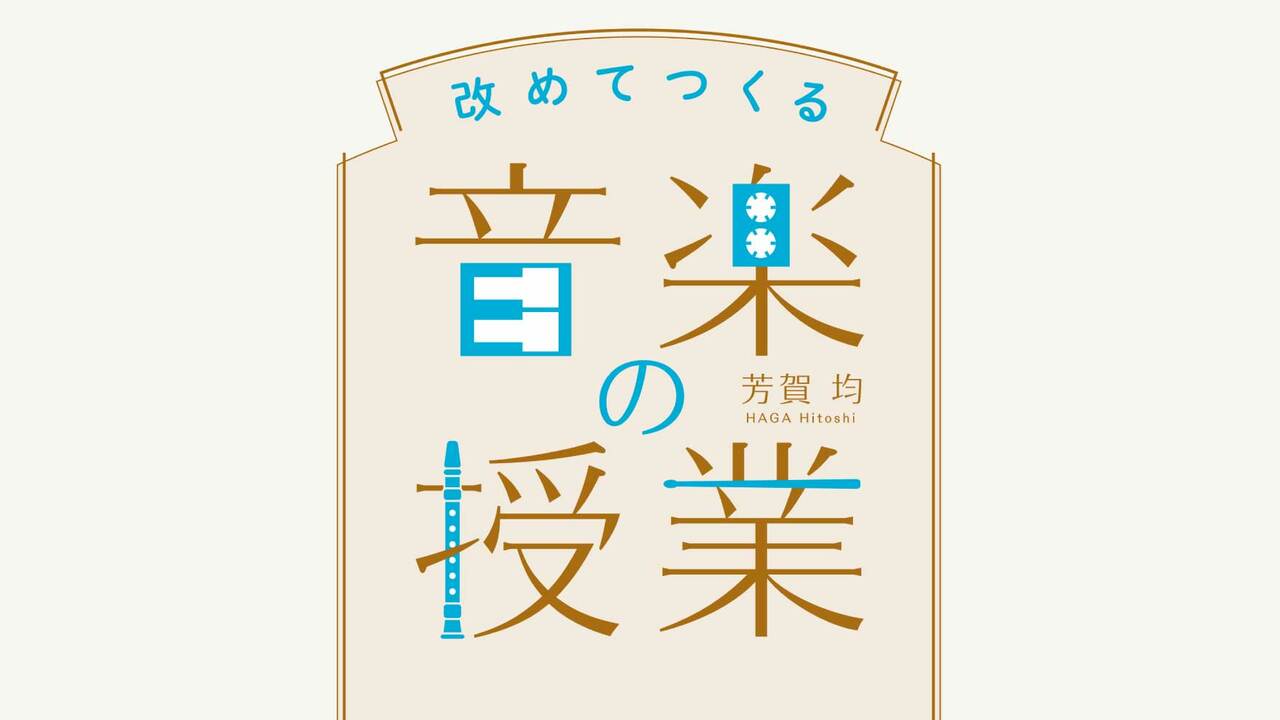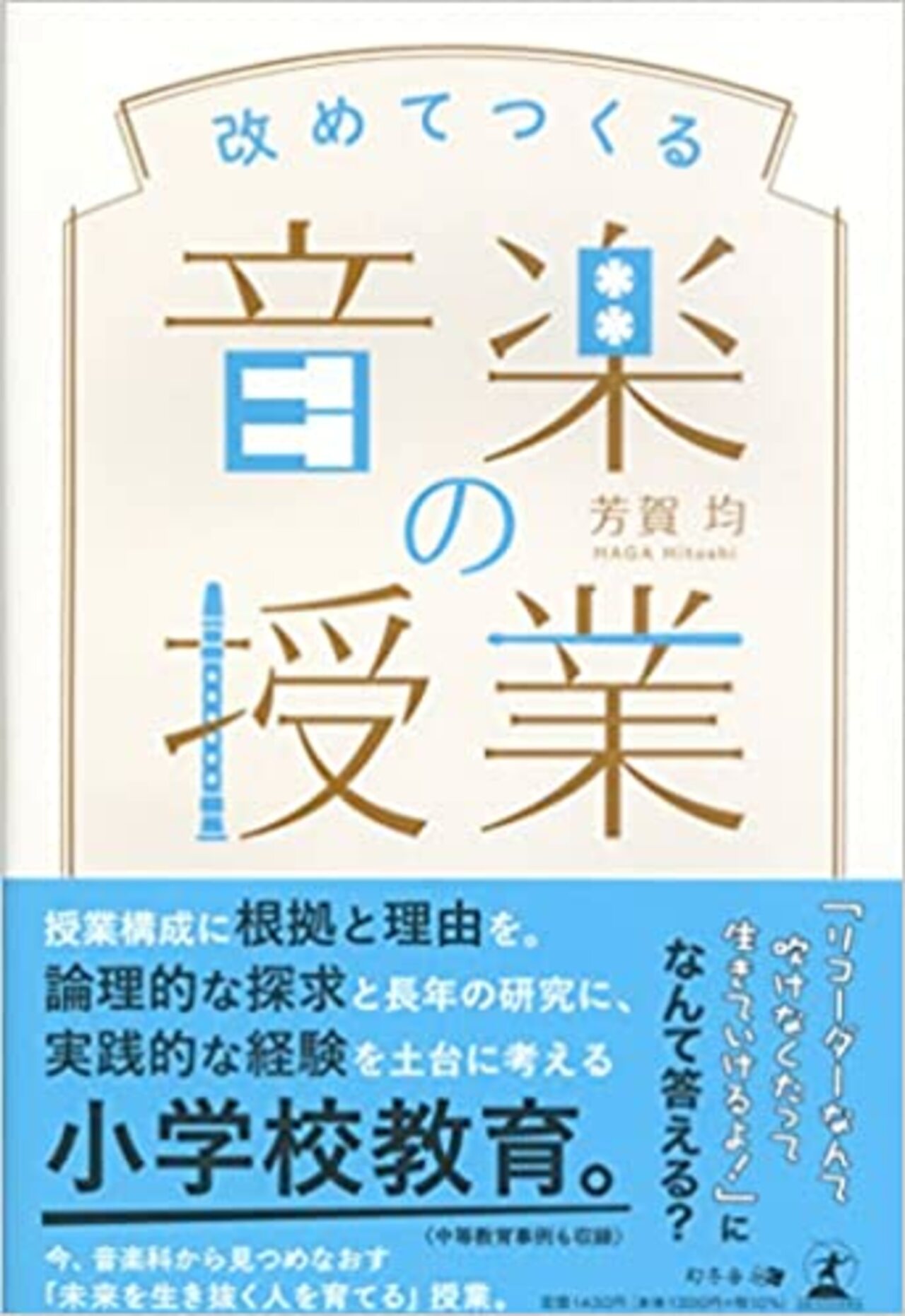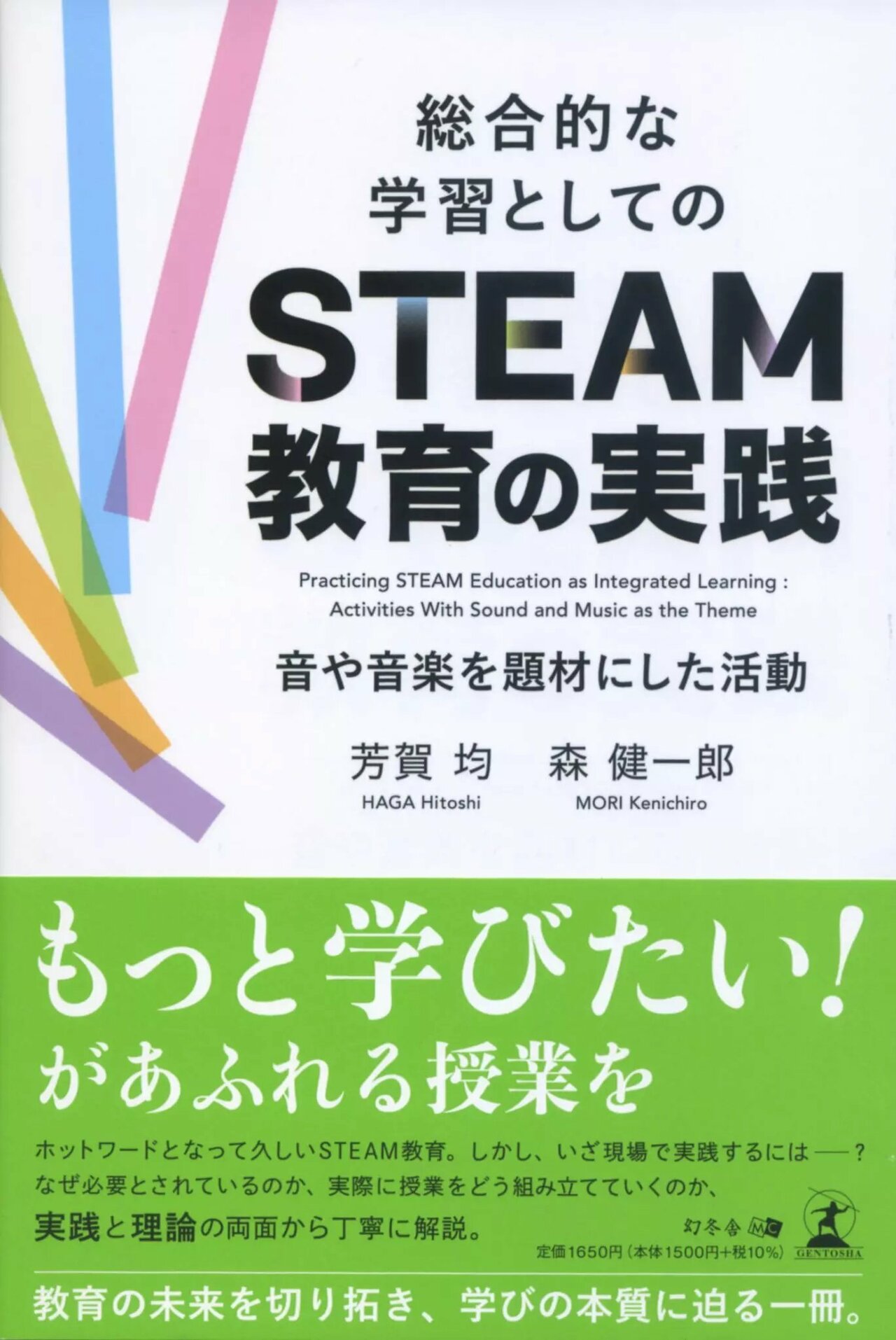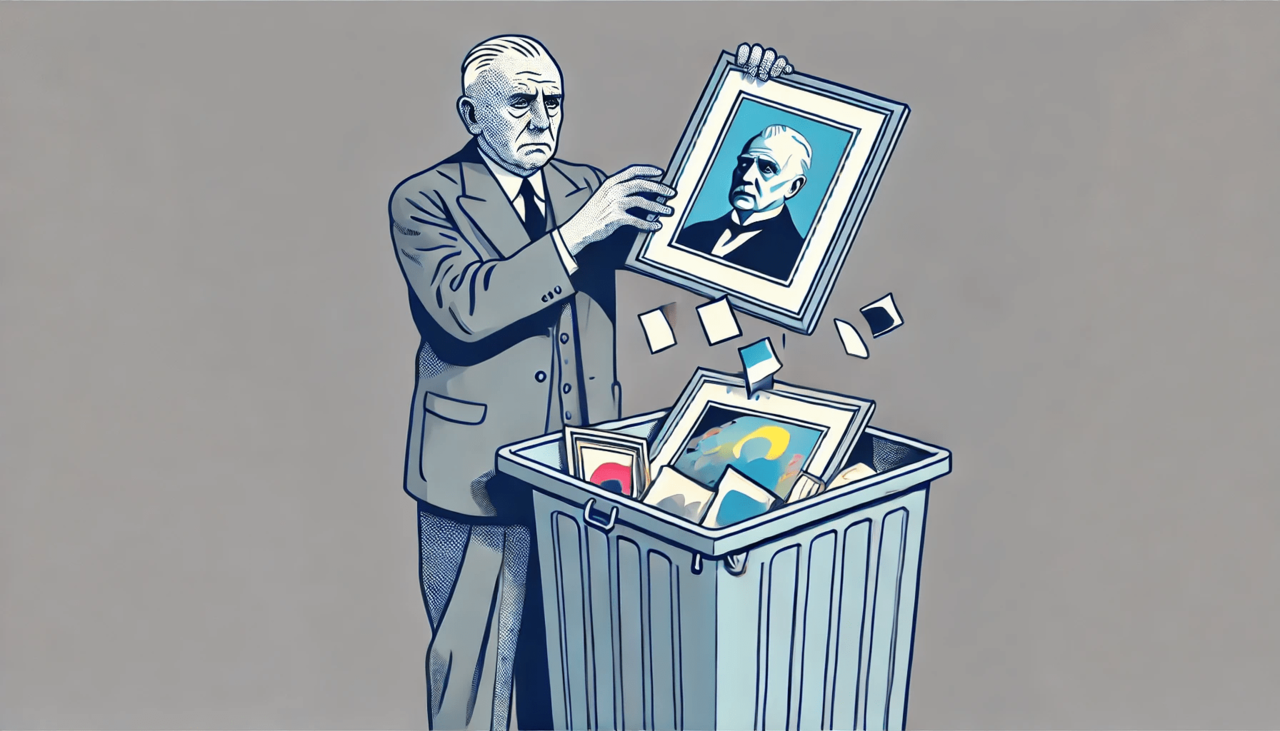第3章 音楽のお勉強は何のため──歌唱の授業を例に
3-2 評価の観点の話
──「関心・意欲・態度」から評価の4つ(3つ)の観点
このエピソードは、評価の観点1)でいえば〈1-3〉で述べた2)「関心・意欲・態度」からスタートした好例です。少し荒っぽいですが、子どもたちから「聴かせて !」と言いたくなる状況をつくりだしています。
しかも、聴取が徐々に正確になっていきますので、聴き取る技能(鑑賞における技能については、〈5-3〉で改めて触れます)も向上します。
音楽科において、評価3)は大変に問題の多い話題4)ですが、そのことについては折に触れて実践例も交えながら述べることにします。本書では、「評価の観点」を切り口にしてお勉強を捉えていくことで、その仕組みや方策が見えてくるということを、実践例を交えながらお話ししていきたいと思います。
なお、その際、あえて平成3・13・22年の指導要録5)における、評価の4つの観点で述べていきます。
現行の3つの観点は学校教育法に掲出されている学力の3要素に基づくものですが、それとは矛盾しません。
〈1-3〉で述べた、結果として得られる知識と技能の2つ6)を「知識・技能」という形でひとつの観点にまとめたという形です。
ただし、本書では、言語化できたものを知識、言葉で説明できなくとも、「こんな感じ」という具合にやってのけられれば技能と分別します7)
評価の観点について、変遷を確認しておきます。
『絶対評価とルーブリックの理論と実際』8)には、昭和 55 年までの指導要録の評価の観点が「内容分析的観点(→教える側の立場から見る)」であったのに対し、平成 3 年の改訂では、学習者中心の「能力分析的観点9)(→学習者の立場から見る)」へと転換したと述べられています。