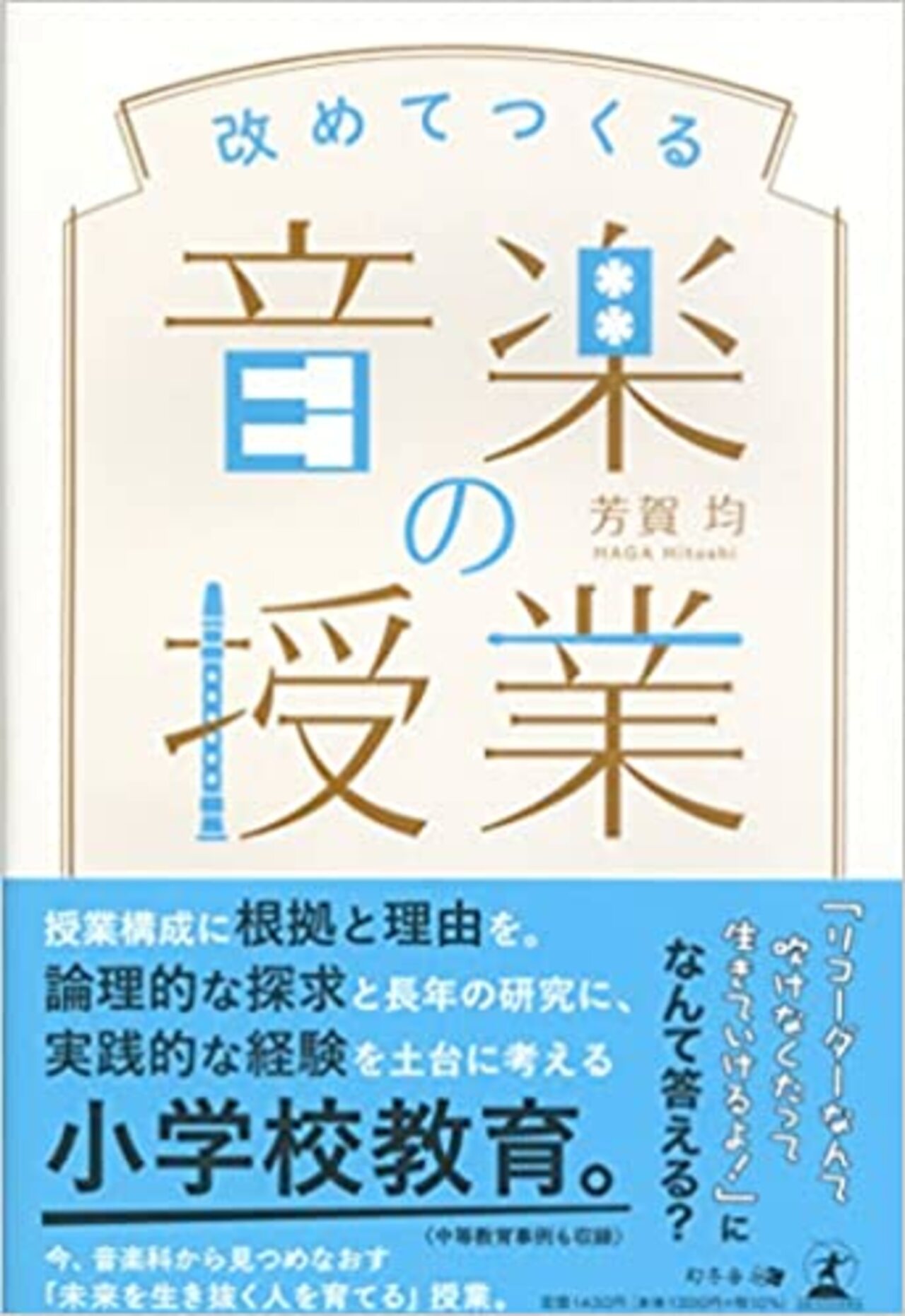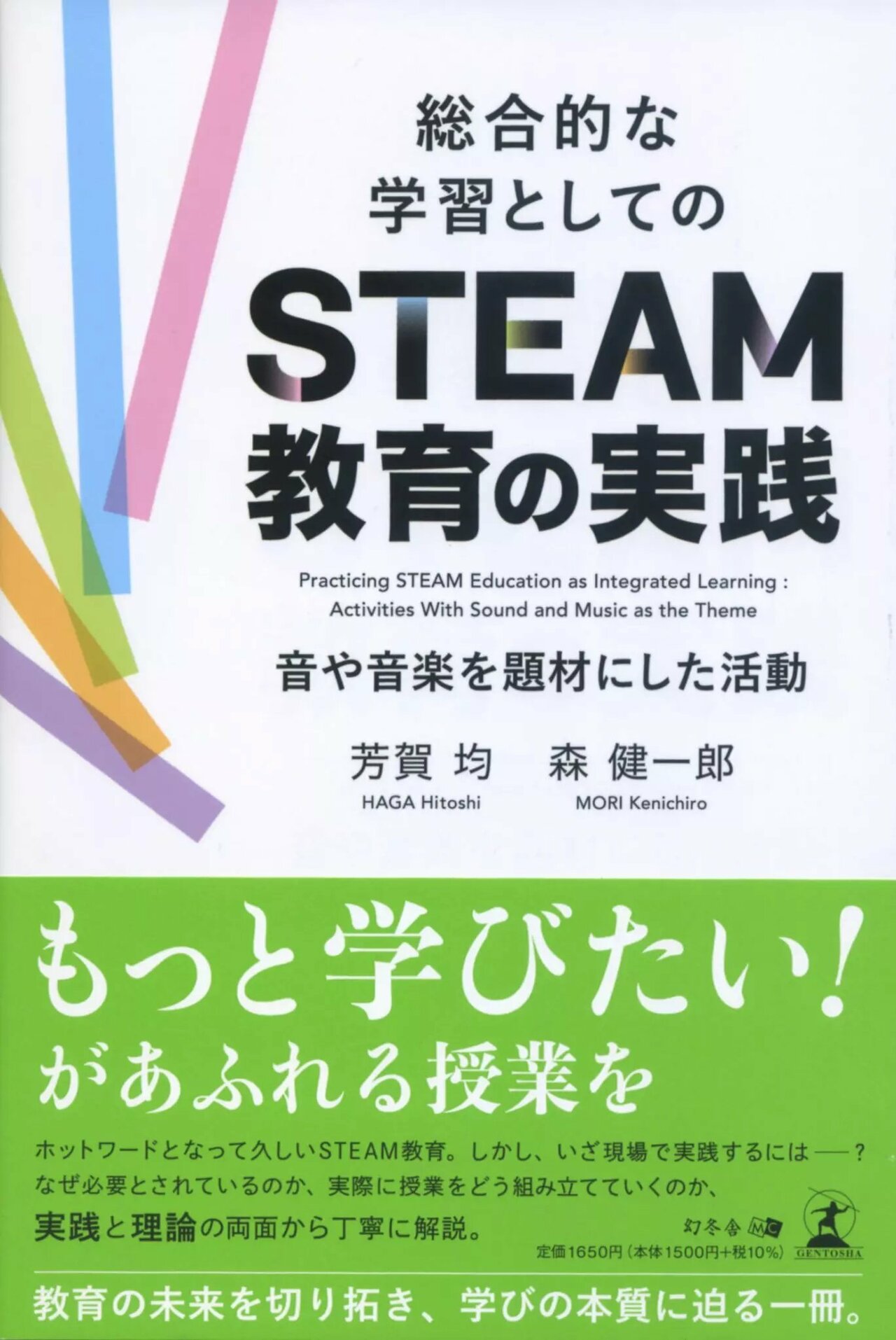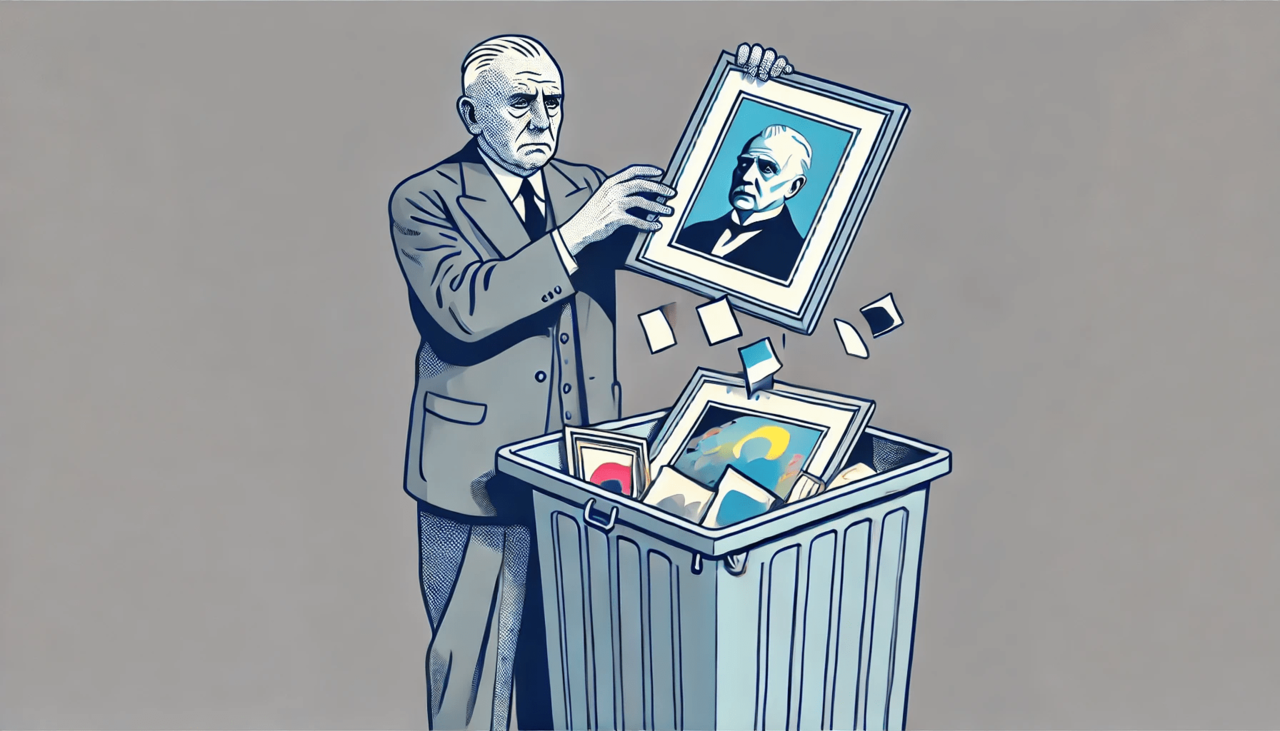これは、多くの知識を教え込むことになりがちであった教育の基調から、子どもの主体的に学ぶ力を身に付ける教育へと転換したことに伴って、評価も「学力の測定」から「学力を育てる評価」へと転換したことを意味しています。
平成元年告示の学習指導要領に対応してのことで、わが国の教育は、(あまり実感がないかも知れませんが)平成の時代に入って大きく変わったということができます。
特に、「知識」が最上段、「関心・意欲」が最下段に配されていたものが逆順になったのでした。こうした記載順は、教育観と関わっていると考えることもできます10)
1) 本書では、評価の観点を、現行の3 つの観点ではなく、主に平成の時代の(知識と技能が分かれている)4 つの観点で話を進めていきます。言語化されないと知識にならない一方、言葉で言い表せなくてもやってのけられることは技能であるため、それらを分けて話を進めていきます(本文中でも、そのことに触れます)。
2) 〈1-3〉で「『関心・意欲・態度』は学習の入り口であり、それに支えられながら調べたり、探したりするのに必要な学習能力が『思考・判断』であり、その成果として身に付けるのが『技能』であり『知識・理解』である」と掲出した、問題解決としての学習におけるサイクル。
3) まず、「音楽は評価できない」という言葉を本当によく聞きますので、そういうイメージが一般にもたれているものと思います。しかしそれは、例えば演奏や作品についての「出来栄え」や、曲を聴いて感じ取った感想等に対することであって、そのことと「お勉強の様子」を評価することとを混同することから起こるイメージであるといえます。
4) 評価に関する問題については、小山真紀「音楽科の評価研究における問題点」『教育目標・評価学会紀要─第4 号』教育目標・評価学会、1994、pp.55-63. において、「①評価に対する先入観の存在」「②『主観・客観』の根底にある問題」「③『評価』の用法に関する混乱」「④評価の観点と方法の未整理」の4 点に整理され、「教師側の論理だけで『客観性を追求できるか否か』を議論することをやめ、学習者の視点に立つこと」および、他教科と「領域や次元が異ならないよう留意すること」「授業場面での評価を中心にして考察すること」「評価の観点や規準、基準、方法などをできるだけ明確にしていく方向をめざすこと」を研究者がまず考えるべき方向であると提示されている。