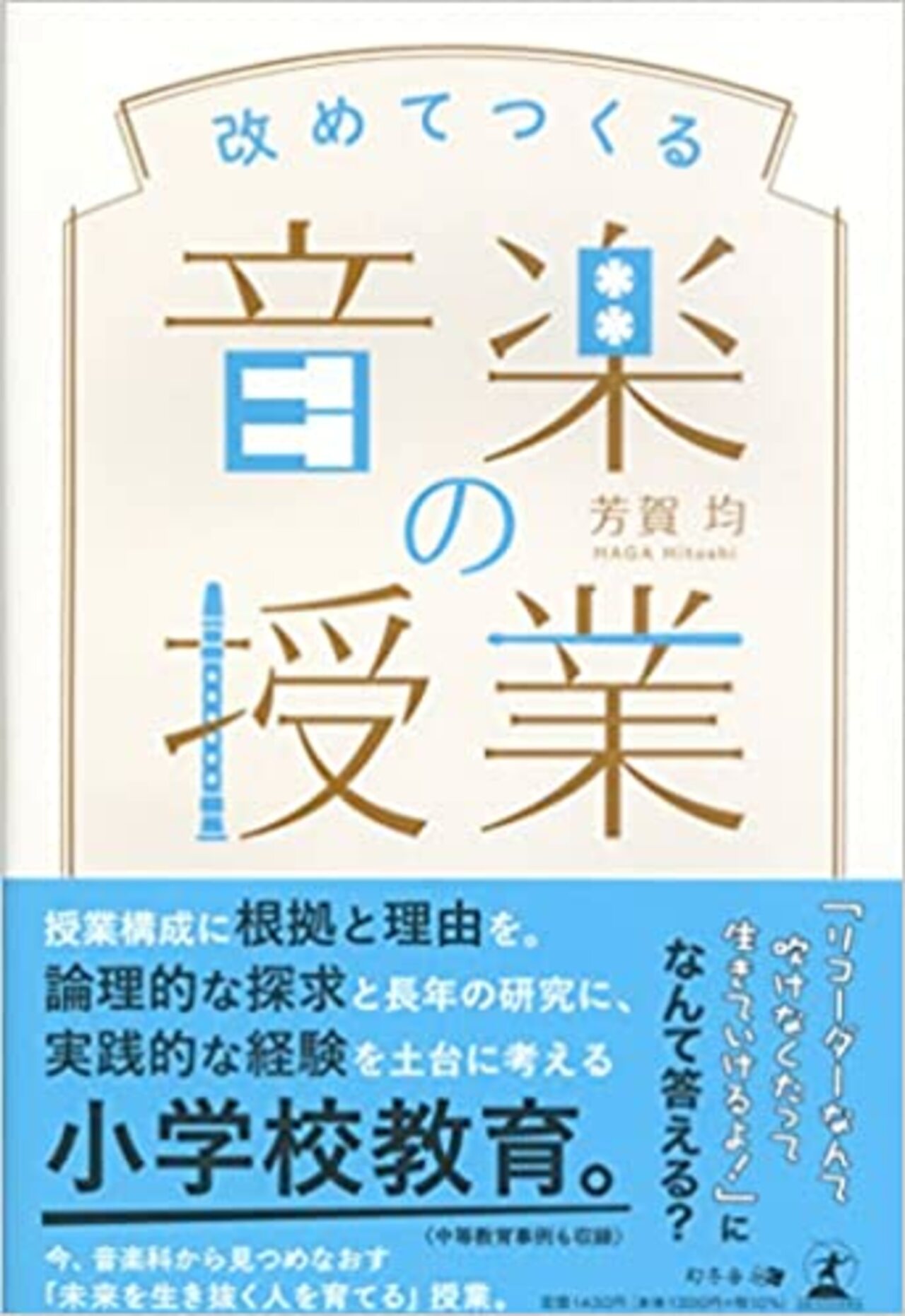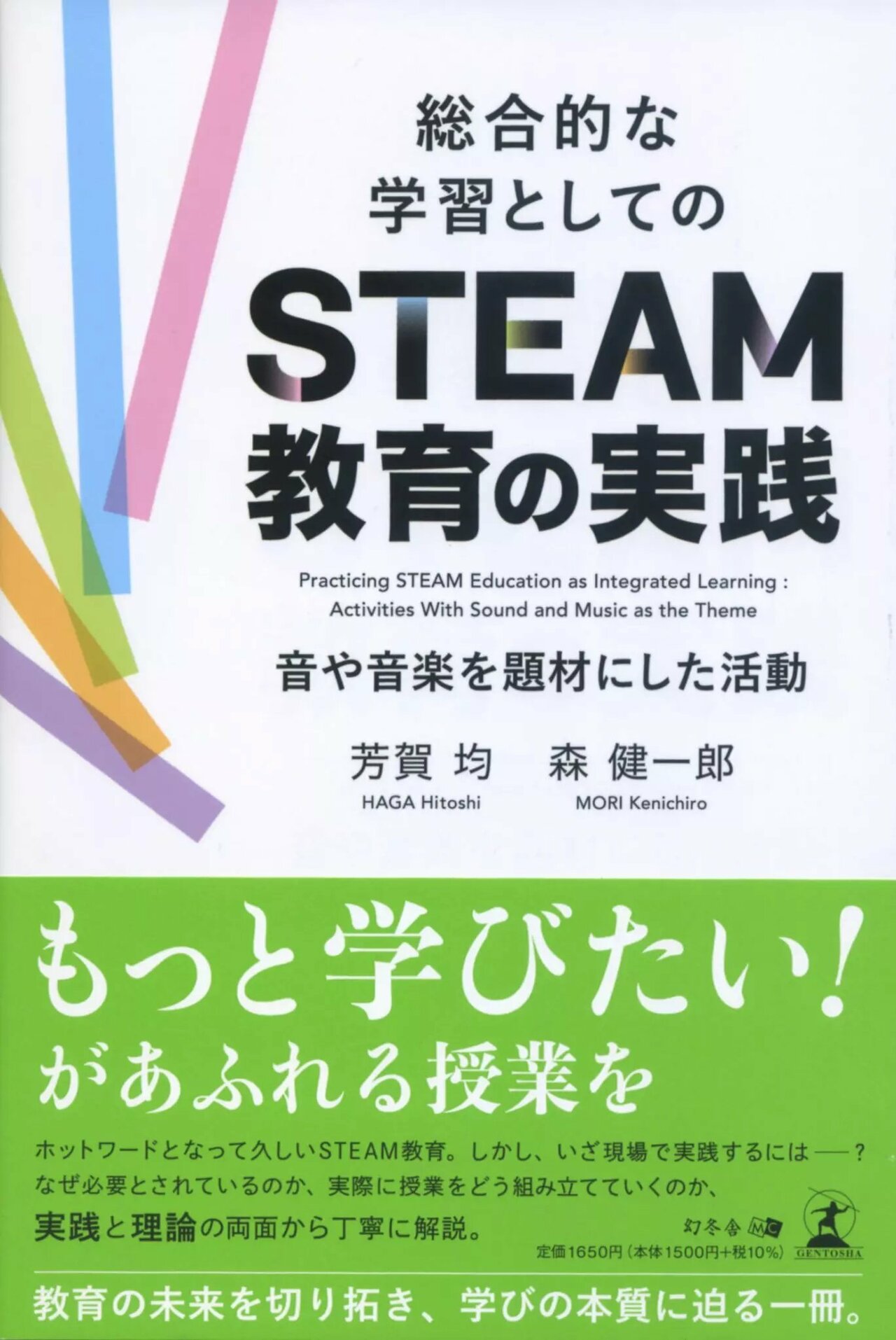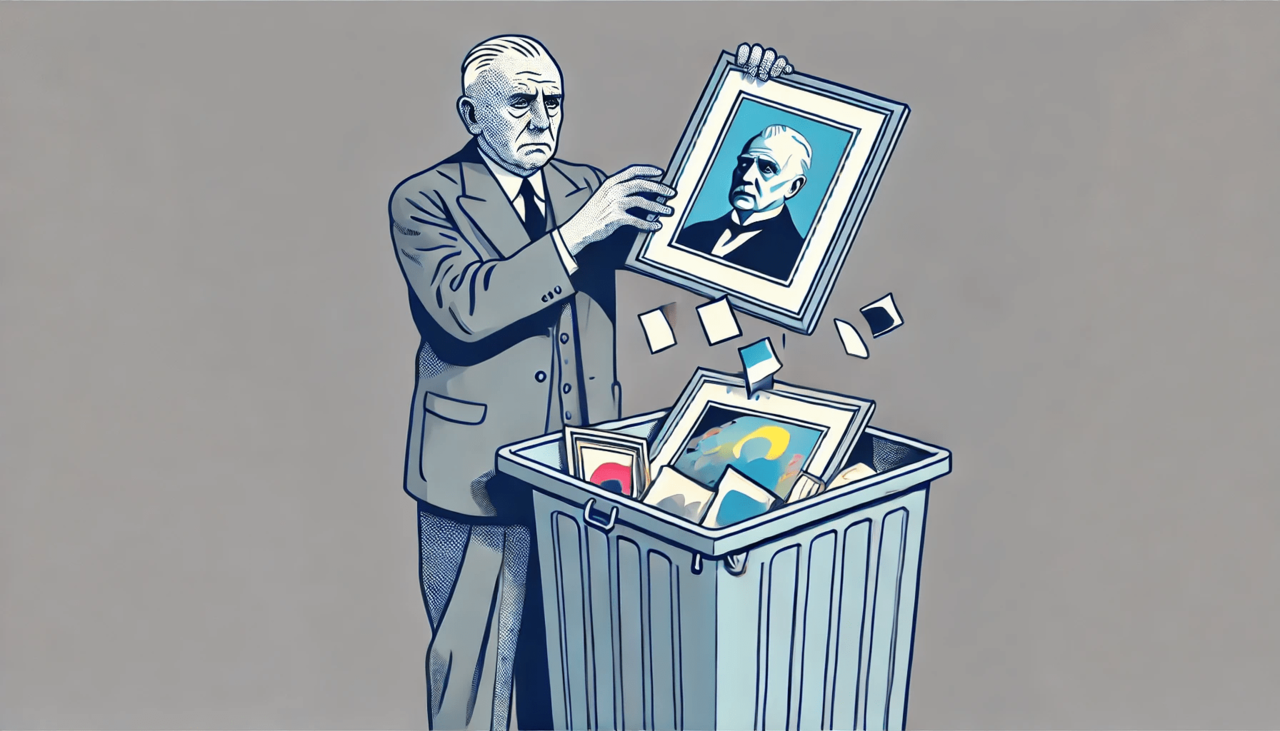そうしたそれぞれの立場に固執すると、専門的になりすぎて、プロブレムではなく、クエスチョン、つまり「研究者」的な在り方になってしまいます。そうした2人の筆者が良好な協力関係で本書の STEAM 教育の実践に取り組むことができるのは、そうしたそれぞれの立場に固執していないからです。
科学者であり優れた芸術家でもあるダ・ヴィンチのような巨人ならいざ知らず、私どものような一般の研究者が新しい教育実践に立ち向かい、切り拓いていくには、協力関係が重要です。しかし現実にはそれぞれが専門的すぎる、あるいは専門②という意識を強くもちすぎる態度がその障害となることを実感しています。
さて、問題解決に必要な技能(スキル)、それはあくまで手段ですが、それをきちんと積み重ねていくことが創造性には必要です。創造性は、単なるひらめきではなく、そのひらめきを実現に至らしめる手続きをきちんと積み重ねていくことです③。
OECD が 2015 年から推進している Education 2030 プロジェクトでは、3つのコンピテンシーのカテゴリー(新たな価値を創造する力、対立やジレンマを克服する力、責任ある行動をとる力)を設定しました1)。
そのうちの一つである「新たな価値を創造する力」は、創造性にあたるものであり、獲得した知識を「未知な状況や変転する状況において適用するため」2)に必要であるとされています。
したがって、これからの教育課程では、創造性の育成に着目した構成を意識することが求められているといえます。このことは、「今日的なコンピテンシーとして重視されているものに創造性がありますが、フィンランドでは、創造性の育成のために、ものづくりを中心とした芸術系教科の重要性に着目して多くの時間を割いている」3)という指摘からも分かります。
本書では、生活との連続性を考慮した総合的な活動から、結果として、各教科の学びに還元されることを意図しています。