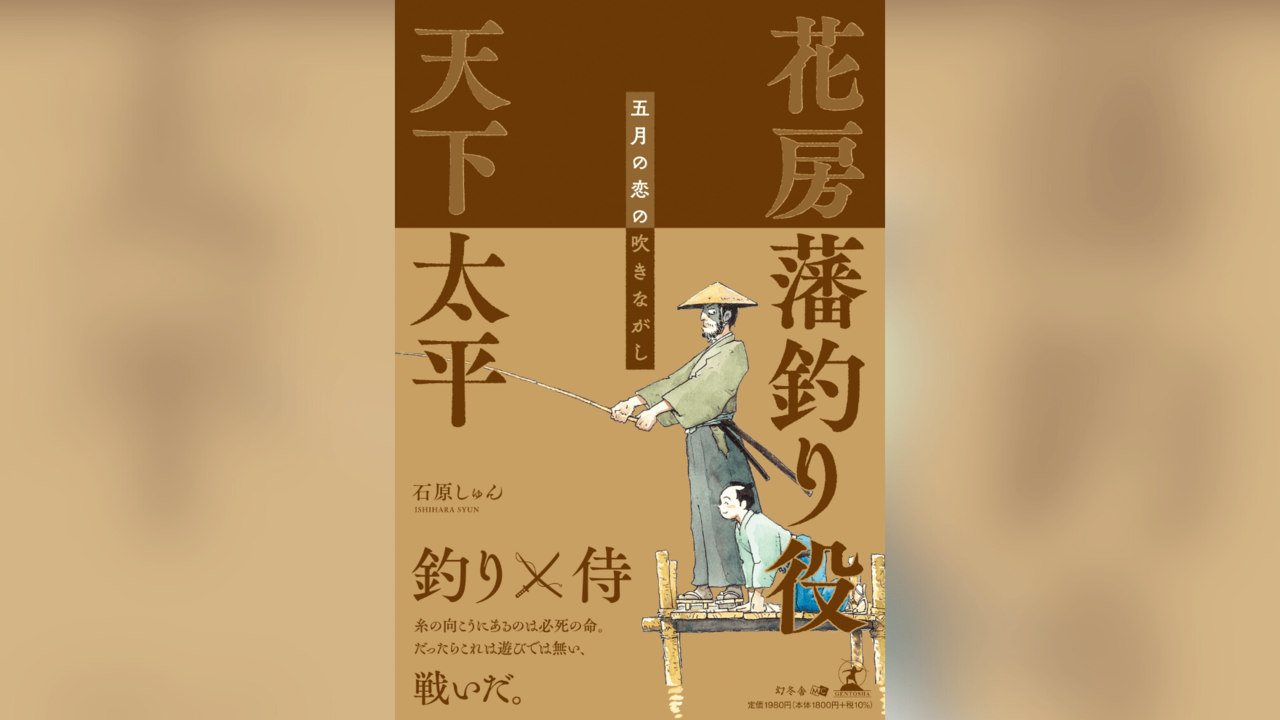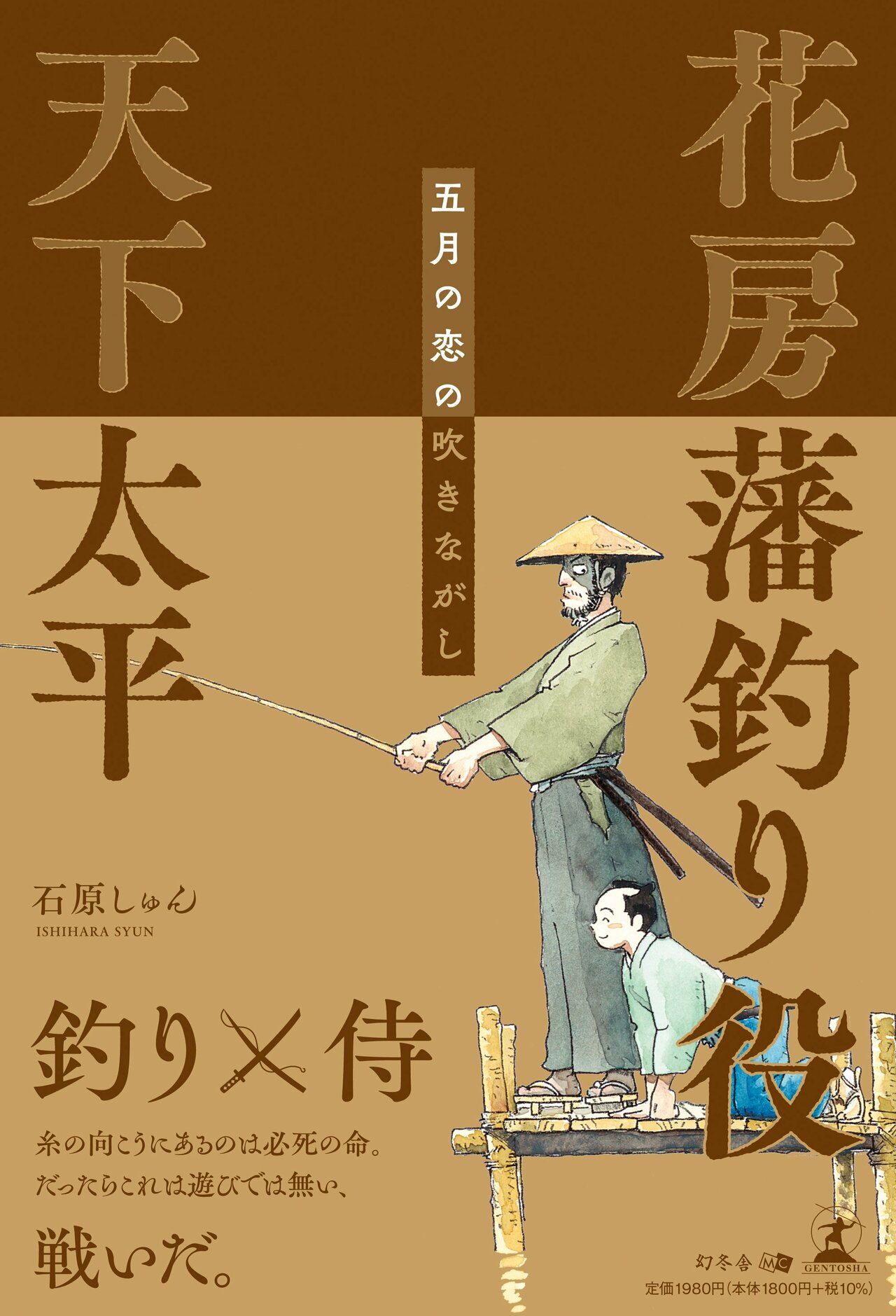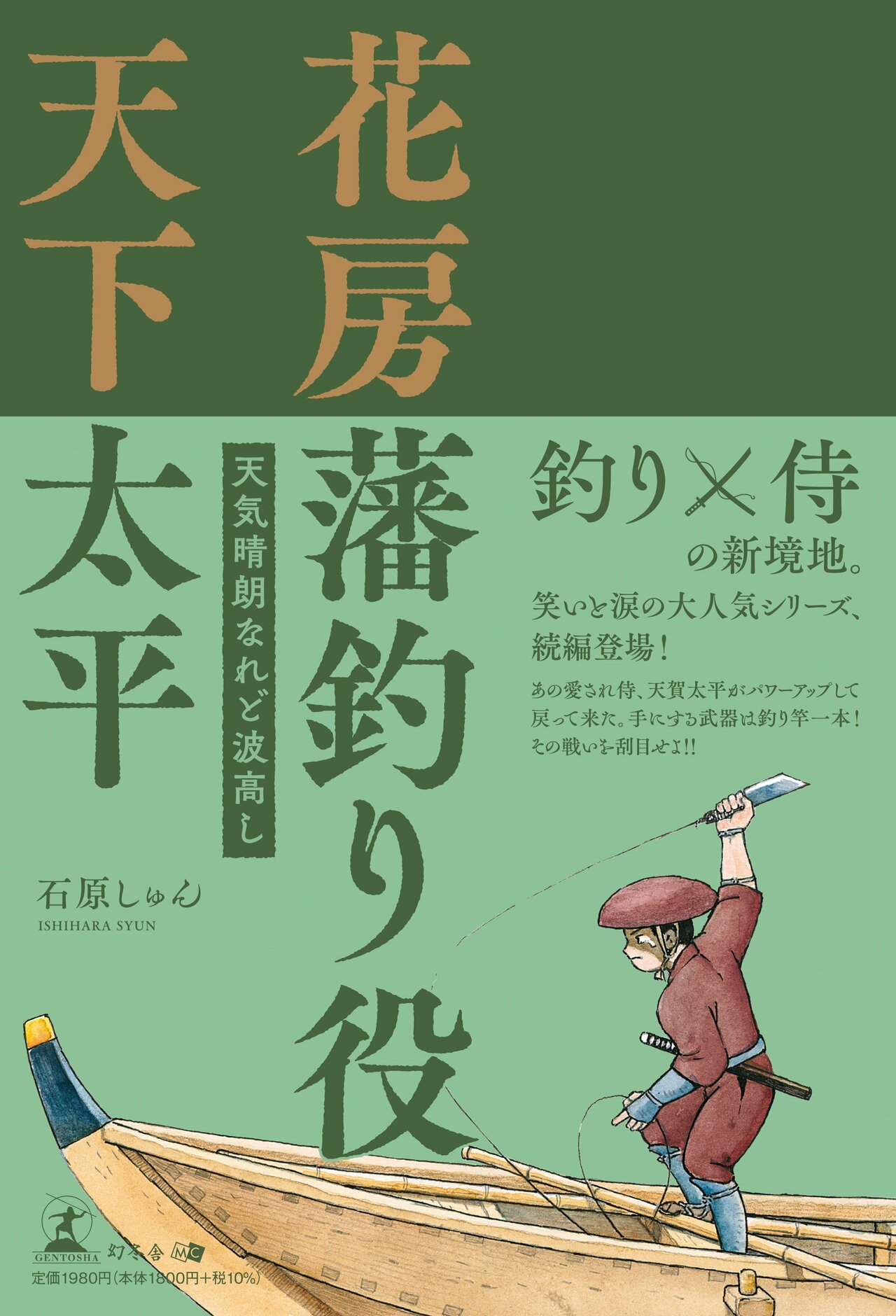【前回の記事を読む】黒鯛は冬は暖い深場で過ごすが春となり、水温が上がるとともに浅場に移り、産卵に向けての荒喰いを始める。それが乗っ込みだ
第一章 いずれあやめかかきつばた
一
和竿(明治に西洋竿が入って来て、和竿という言葉が生まれる。それまではただ「竿」だ)作りは、幕末を迎えるこの時代に大きく発展をしていた。
竿師という職もこの時代に成立する。紀州藩士から竿師に転じた、初代東作がその嚆矢(こうし)とされる。当時、世界一の人口を抱え、海に近く、川も無数に走る江戸だからこそ、竿師という職も成立し得たのだろう。
はぜ竿、鱚(きす)竿、海津(かいづ)竿。釣る魚に合わせて、多種多様な竿が作りだされていった(もちろん、釣られる魚は自分用の竿かどうかは気にしないだろうが)。
江戸時代に作られた、たなご釣り用の釣り箪笥(だんす)という物がある。天板についた金具で持ち運び、腰掛けともなる大きさで、何段かの引き出しがついている。その引き出しには仕掛けや浮子やらの、たなご釣りに必要な一切がおさまっている。
上の蓋を開けると、鯨の髭で作った穂先、竹の先を使った穂持(ほも)ち、布袋竹(ほていちく)の手元が入っている。三段を継いでも二尺(約六十センチ)ほどのその竿で、一寸(約三センチ)ほどのたなごを釣る。
そして大きさではなく、小ささを競う。片手の平にたなごを並べて数を競い、終れば水に返す。
これは正しく本邦初のゲームフィッシングといえる(いや、ひょっとすると世界初かも知れない。最盛期には頻繁に競技会が行われ、賞品まで出たというのだから)。
余談ついでに言えば、和竿の発達は平安時代に端を発する、らしい。平安貴族が庭の池の上に釣殿を建てて、釣りをしながら酒宴をする。ここに遊びとしての釣りが始まり、釣り人が生まれ、和竿へとつながっていく。
竿には三つの形がある。延べ竿、継ぎ竿、振り出し竿の三つだ。
延べ竿は一本の竹をそのまま竿にした物で、これが竿の始まりとなる。そして応仁の乱の頃に継ぎ竿が生まれる。