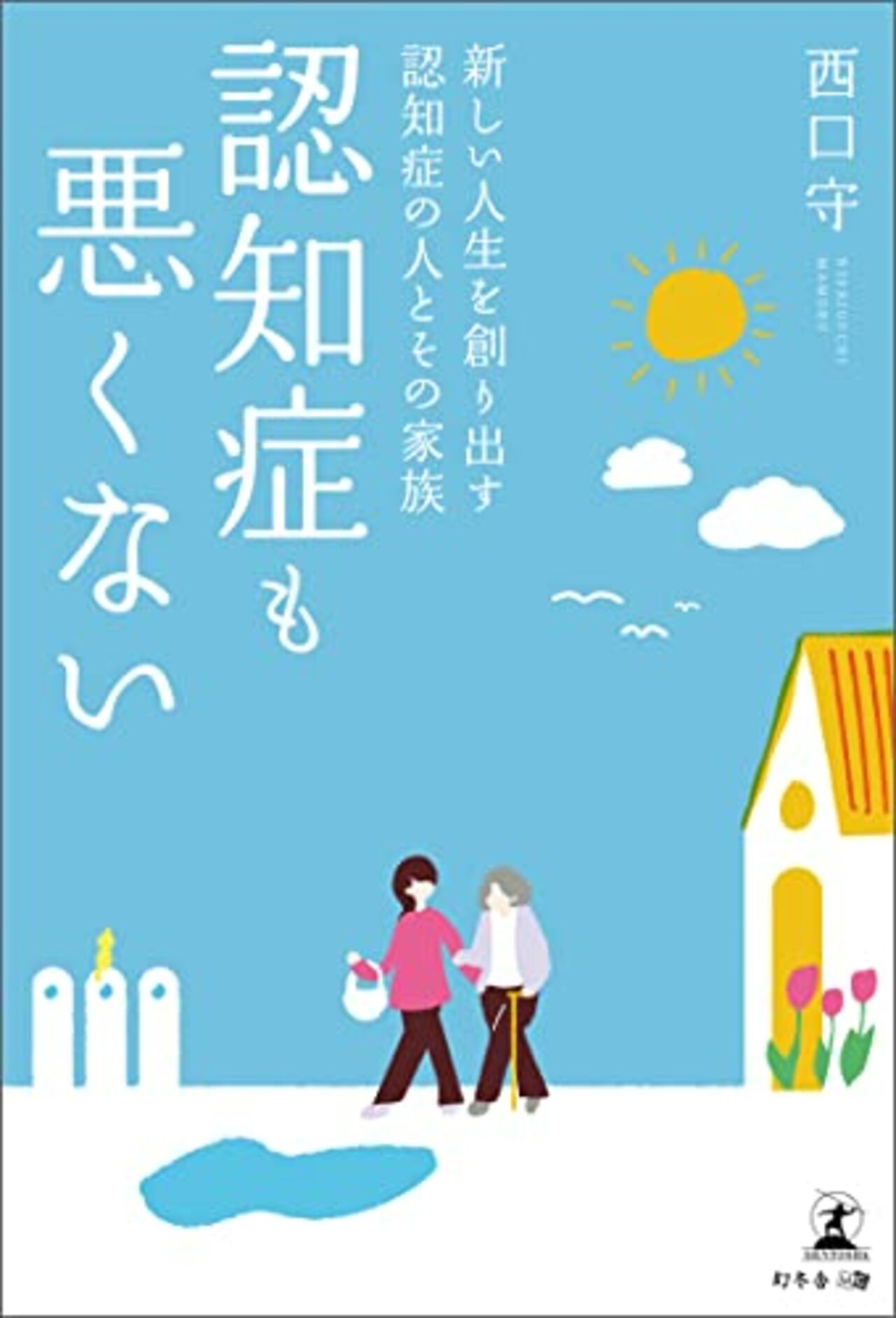私からすればそういう「今、苦しんでいる人には何ら利益にならない議論のための議論」は、痛みある人が集う「現実」とは隔絶された人々しか集まらない場でむなしく、その方々にとっては愉快にやり続ければいいと思います。
でも困難な中で人がなんとか安定して生きるあるいは生きたいと言うことは、いつでも直球を投げればいいのではなく、その躓(つまづ)きに寄り添いながら、あるときは少し「変化球」を用意することも当然意味あることではないでしょうか。
余計なことをいいました。
1 文部科学省は大学設置基準の大幅な緩和を検討している。これが実現すると、ミネルヴァ大学や大胆なコープ制度も実現可能?
2 社会構成主義と言われる考え方がある。社会に存在するありとあらゆるものは人間が対話を通して頭の中で作り上げたものであるという考え方。これがナラティブアプローチにつながったと言われる。本文で述べている「人は事実を生きているのではなく、その“意味を付与した世界”」を生きるという考え方にもなる。
「「現実」は予め自明のごとく存在するのではなく、社会的に構成されるという新たな知識は、そのまま「自己」にもあてはまるというのが、社会構成主義の自己概念である。つまり「本当の自分」がはじめから自明のようにしてあるのではなく、それは常に流動的で社会的に構成される自己としてとらえなおすことができる。自己は自己のことを他者にかたる(モノローグではない)ことによって自己を構成する発想」(ここまで 木原活信 ナラティブ・モデルとソーシャルワーク 加茂陽編 「ソーシャルワークを学ぶ人のために」所蔵 世界思想社 初版2000年)p.69
この後さらに、本文でも説明する。
「シルバー世代応援ピックアップ記事」の次回更新は9月20日(土)、7時の予定です。
▶「シルバー世代応援」イチオシ記事
『終恋 』たとえ何があっても、決して後悔はしない。
一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ。
▶「シルバー世代応援」イチオシ記事
『黒い渦 日の光』語り合うことで、人生がもう一度動き出す
妻を亡くした私は七十歳が目前となった昨冬、四十年以上勤めた外科医の仕事を捨て、日本海側の地方都市に移住した