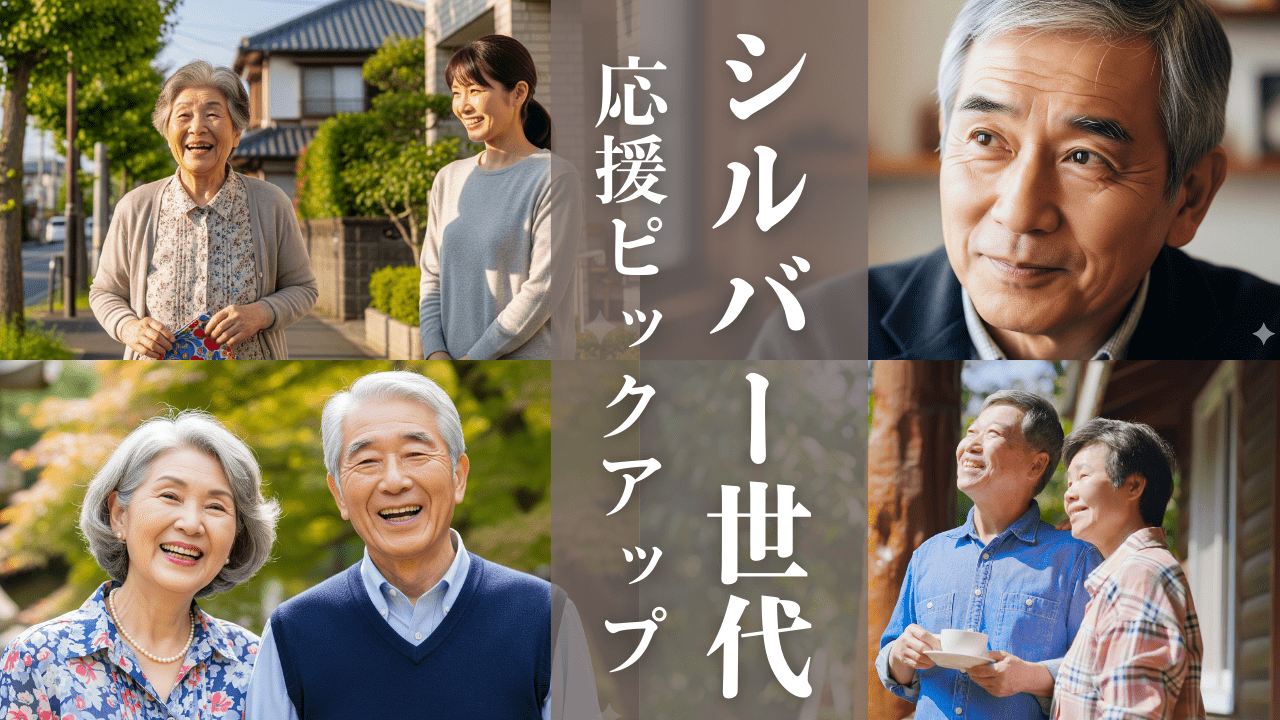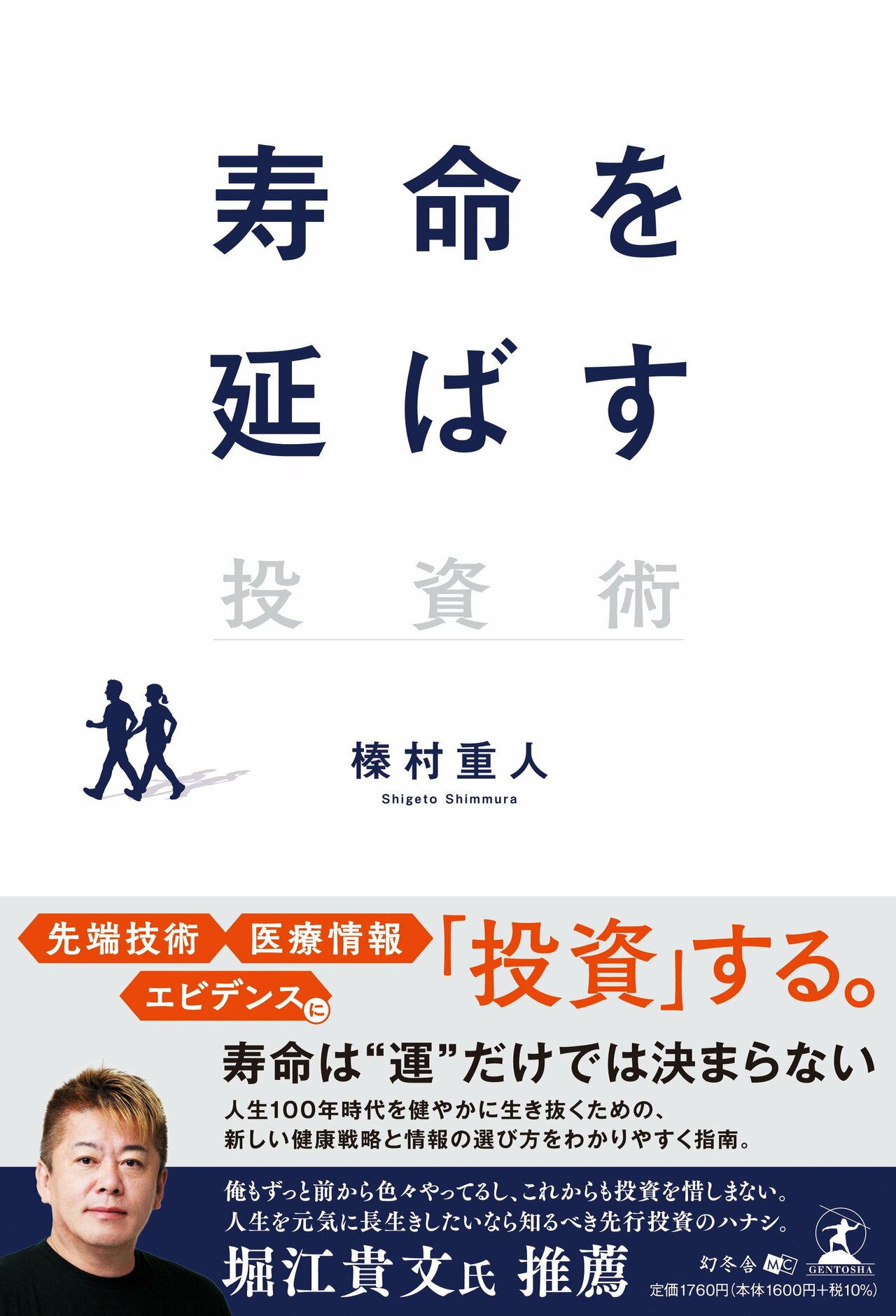はじめに
本書を手にされた方は、おそらく自分があと何年生きるかを少なからず気にされていることでしょう。平均寿命が年々延び、日本は世界屈指の長寿国となりました。
しかし、平均寿命が延びても、自分が長生きするという保障はありません。健康なうちは、自分の健康をあまり意識しないのが人間です。
病気などで最期が現実味を帯びてくるまでは、自分の死についてあまり考えないものです。
しかし、筆者を含め、読者の皆さんにもいつかは必ず人生最後の日が訪れます。いつかは最後の一息を吐き、心臓は最後の鼓動を打つのです。
人類の最高寿命はおおよそ120歳前後で、今後もしばらくは延びることはありません。少なくとも、我々が生きている限りはないでしょう。
ただし、寿命を限界まで延ばすことは今の生命科学の進歩によって可能となりました。
しかも、ただ寝たきりの状態で生き延びるのではなく、健康な身体を最期まで維持する『健康寿命』を延ばすことも不可能ではありません。
本書では、寿命を延ばすための健康への投資戦略を紹介します。もし株式や投資信託に投資している余剰資金があれば、その一部でも健康に投資した方が絶対に人生得をすると考えます。
有価証券の含み益をいくら多く得ても、回収する前に死んでしまっては意味がありません。
投資が満期を迎えて、それをのんびりと余生で使う人生設計には健康への投資が欠かせません。
本書で最も伝えたいのは、皆さん自身の健康と寿命について、自ら積極的に取り組むことがいかに大切かということです。
病気になってから治療するのではなく、病気にならないよう努め、その結果としての幸せを手に入れてほしいのです。人生は一度きりで、寿命は大きく「運」に左右されます。
これを「人生ガチャ」と表現することもできますが、このガチャには、欲しい結果を手に入れるための具体的な手段が存在するのです。それが、寿命を延ばすための「投資術」です。
もう一点だけ理解していただきたいことがあります。本書ではさまざまな投資術を紹介しますが、生命科学は常に進化している分野であり、情報が常に更新されています。
投資の世界では、「情報」が最も価値のある資産です。本書が提供するのは、まさにその価値のある情報です。
また、どのようにしてそのような情報を手に入れるかについても解説します。投資家の方はすでにご存じと思いますが、資産運用はいかに正確な情報を得られるかに大きく依存しています。
また、金融資産と違って、寿命への投資はロスカット(損切り)ができません。そういう意味では、百寿者(センテナリアン)になるための情報は、金融資産を運用するための情報より何倍、何十倍も重要と言えます。
本書を皆さまの健康長寿に活かしていただければ幸いです。
パート1 ベースとなる健康マネジメント
健康への投資は社会貢献
寿命を延ばすための投資は、決して自己中心的な行動ではありません。投資によってあなたの健康寿命が延びれば、その恩恵にあずかるのはあなた自身だけではありません。
仕事やプライベートにおいて関わるすべての人にも恩恵をもたらします。
逆に、あなたの寿命が短くなると家族にとって精神的、あるいは経済的支柱を失うなど大打撃となりますし、企業にとって役員が突如亡くなることは少なからず混乱を招きます。
小さな法人であれば、倒産の危機にさえ発展するかもしれません。
さらに、投資によって健康寿命を延ばすことは、医療費を抑えることにもつながります。進行がんと診断され、手術や放射線療法、緩和療法を行うことになれば高額な医療費がかかります。
こうした医療費を節約できれば、社会全体に貢献することになります。自分の健康寿命が延びて、さらに社会貢献になるのであれば、これほどWin‐Winな投資は他にないでしょう。
株式投資で成功する人の裏には、失敗する人も必ずいます。寿命を延ばすための投資は、自分の健康寿命を延ばすだけではなく、周りのすべての人々の幸せに貢献するのです。
では、具体的に何に投資すれば良いのでしょうか? こうなったら、すぐにでも資金を寿命に投資したいと思うかもしれません。
しかし、金融への投資と同じように、正しい情報に基づいた、自分に合った投資をすることが必要です。
誤った情報を信じて投資をすると、効果がないばかりか、むしろ健康を害するリスクすらあります。
自分の体質(遺伝的背景を含む)を確認し、さらに自分のライフスタイルやニーズを考慮した投資を目指しましょう。
「シルバー世代応援ピックアップ記事」は本日が最終回となります。
▶「シルバー世代応援」イチオシ記事
『終恋 』たとえ何があっても、決して後悔はしない。
一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ。
▶「シルバー世代応援」イチオシ記事
『人生100年 新時代の生き方論』「老後」から「第2の人生」へ
60歳以降のセカンドライフでは、仕事でも趣味でも交流活動が重要。交流の中で「ロールモデル」や「メンター」を探すことができれば…